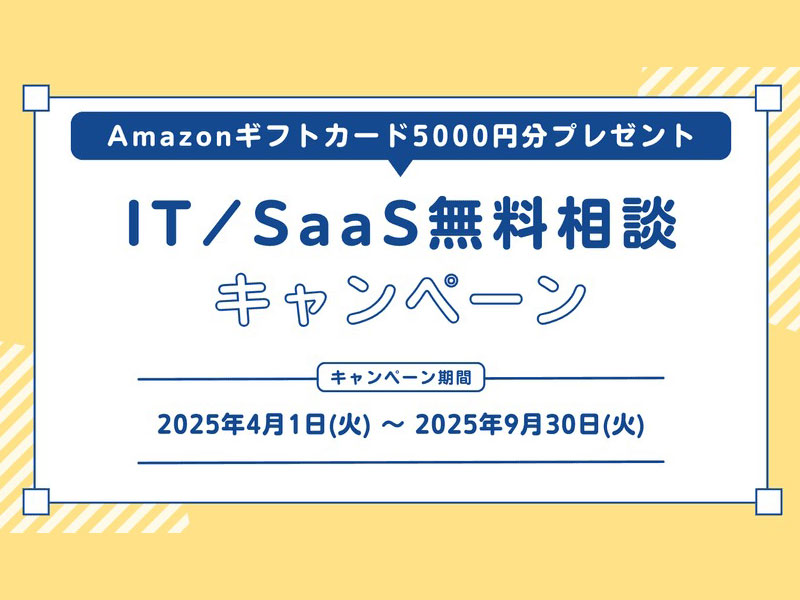- ITmedia ビジネスオンライン
- #SHIFT
- 「高学歴新卒」は本当に優秀? 活躍しているの? 識者が語る“リ...
「高学歴新卒」は本当に優秀? 活躍しているの? 識者が語る“リアル”:リーディングマーク飯田代表に聞く(1/3 ページ)
東京大学、京都大学、大阪大学、早稲田大学、慶應義塾大学――。こうした有名大学の学生から支持されており、年度ごとに約3万人の“高学歴ユーザー”が登録する就活サイトがあることをご存じだろうか(登録者数は2017年卒の実績で2万9693人)。
そのサイトとは、08年創業のベンチャー、リーディングマーク(東京都目黒区)が運営する「レクミー」。登録した就活生は、掲載企業のインターンシップなどに応募できるほか、「東大生向け」「早稲田生向け」など、大学ごとに開催される合同説明会に参加し、各大学出身の社員や人事担当者と接点を持つこともできる。
説明会には、三菱商事、野村総合研究所、トヨタ自動車、日本航空(JAL)など名だたる企業が参加。偏差値上位校の学生は業界のトップランナーから話を聞き、選考に向けた理解を深められるほか、人事担当者は優秀な学生にターゲットを絞って接触できる。両者にメリットがある形で、“ハイクラス”同士を結び付けているのだ。
だが世間では、企業が上位校学生への採用を重視することを批判的に捉える声や、「高学歴だからといって、仕事ができるとは限らない」などとやゆする声も一部から聞こえてくる。
多様な人がいるのに“高学歴”とひとくくりに捉えられてしまう上位校学生だが、実際はどんな能力を持っているのか。就職後は本当に活躍できているのか。そんな“仕事と学歴”を巡るあれこれを、同社代表取締役の飯田悠司氏に聞いた。
“優秀層特化型”の就活サービスはいかにして生まれたのか
――上位校の学生に特化した就活サービスを始めた、そもそものきっかけを教えてください。
飯田代表: 当社は私が東京大学3年生の時に創業しました。きっかけは、社会人に仕事の充実度に関するアンケートを取った際に「仕事にやりがいを感じている」と答えた人が2割しか存在しなかったことです。
この結果を見て「起きている時間の6~7割は仕事をしているのに、社会人はなぜやりがいを持てないまま働いているのか」と疑問を覚え、企業と人材のマッチングの質を高めて状況を変えたいと考えました。
「レクミー」は試行錯誤を経て13年に立ち上げました。知名度が上がるきっかけになったのは、少人数の学生を集めて企業の担当者にじっくり質問できるイベントを企画した際に、三井不動産が参加してくれたことです。大手が手を挙げたことで信頼性が増したようで、口コミを中心に伸びました。
誤解のないようにお伝えしますが、「レクミー」はどんな大学に通っている方でも登録できる仕様で“学歴差別”はしていません。ただ、「自分に合った仕事を探したい」という高いモチベーションを持って就活支援サービスを調べ、大規模な広告を打っていない中でここにたどり着く学生は、結局のところ上位校に集中しているのです。
現在は、旧帝国大学、一橋大学、早稲田大学、慶應義塾大学、東京工業大学の就活生が使っている就活サービスのうち、大手ナビサイトなどがある中で、「レクミー」が4割のシェアを占めるまでになっています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング



 高卒でプロ野球を戦力外 16年後に「公認会計士」になった男の逆転人生
高卒でプロ野球を戦力外 16年後に「公認会計士」になった男の逆転人生 仕事中に「マジ切れ」する日本人が増えている、ちょっと意外な理由
仕事中に「マジ切れ」する日本人が増えている、ちょっと意外な理由 「スーツにリュック」は本当に非常識? プロのマナー講師に聞いてみた
「スーツにリュック」は本当に非常識? プロのマナー講師に聞いてみた 「面接でノック2回」「室内でコート」は本当に失礼? プロのマナー講師に聞いてみた
「面接でノック2回」「室内でコート」は本当に失礼? プロのマナー講師に聞いてみた 「スタバでバイト」「手書きのES」は本当に有利? “就活都市伝説”の真偽を採用のプロに聞く
「スタバでバイト」「手書きのES」は本当に有利? “就活都市伝説”の真偽を採用のプロに聞く