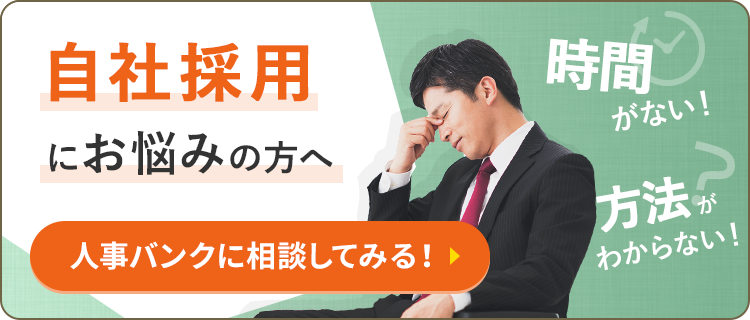新入社員の受け入れでは、書類提出や雇用契約の締結、健康診断の実施、社会保険や税務手続きなど、多くの入社手続きを正確かつ円滑に進める必要があります。
本記事では、企業が入社前後に対応すべき項目を一覧で紹介し、初めて人事を担当する方でも理解しやすいよう詳しく解説していきます。
入社手続きの概要
新入社員を受け入れる際には、企業としておこなうべき入社手続きがあります。
これには雇用契約に関する契約書の作成、各種書類の準備・提出、健康診断の実施、社会保険や税金関連の届出などが含まれます。
また、これらは法律に基づいた義務でもあり、業務の円滑なスタートに欠かせない準備です。
特に小規模な企業では、担当者が総務や経営者を兼ねている場合もあるため、抜け漏れのないチェックリスト管理が重要となります。
入社前に準備が必要な書類

新入社員を迎えるにあたり、企業側と従業員側の両方で用意すべき書類があります。
これらの書類を正しく準備・提出することで、入社後の各種手続きがスムーズに進み、業務開始にも支障が出にくくなります。
企業が交付する書類
採用通知書(内定通知書)
採用通知書は、新入社員に採用決定を伝える重要な書類です。
入社日・職種・給与などの基本情報が記載され、入社準備の指針となります。
文書で交付することで、後々のトラブル防止にもつながり、信頼関係の構築にも役立ちます。
入社誓約書
入社誓約書は、新入社員が企業のルールや就業規則を守ることを誓うための書類です。
主に「機密情報の漏洩禁止」「社内規律の遵守」「業務上の注意事項」などが記載されており、社員としての自覚を促す役割を果たします。
トラブル防止の観点からも重要で、企業と従業員の信頼関係を築く第一歩となるものです。
書類提出のタイミングは、入社日当日またはその直前が一般的で、記名押印を求めるのが通例です。
労働条件通知書
労働条件通知書は、新入社員と企業の間で取り決めた労働条件を明示するための書類です。
具体的には、勤務時間、業務内容、給与、雇用契約の期間、休日や休暇などの基本情報が記載されます。
書面による通知は労働基準法で義務付けられており、口頭での説明だけでは不十分です。
労働条件通知書があることで、トラブルや誤解を未然に防ぐ効果があります。
入社前までに交付することが望ましく、内容に不備がないか確認のうえ、必ず書類提出をおこなうようにしましょう。
雇用契約書
雇用契約書は、企業と新入社員が雇用契約を正式に結ぶ際に取り交わす重要な契約書です。
労働条件通知書と内容が重なる部分もありますが、契約書には両者の署名・押印が必要であり、法的な拘束力を持つ点が特徴です。
記載内容には、業務の範囲や勤務時間、給与、就業場所、雇用期間などが含まれます。
万が一トラブルが起きた際の証拠にもなるため、記載内容をよく確認したうえで、慎重に書類提出をおこなう必要があります。
企業側も正確に準備し、適切に保管しましょう。
従業員が提出する書類
基礎年金番号(年金手帳・基礎年金番号通知書)
基礎年金番号は、公的年金制度に加入していることを証明する個人ごとの識別番号で、入社時に提出が求められる書類の一つです。
通常は「年金手帳」や「基礎年金番号通知書」に記載されています。
この番号をもとに、企業側が健康保険や厚生年金の加入手続きをおこなうため、正確な記載が欠かせません。
年金手帳を紛失している場合は、年金事務所で再発行の手続きが可能です。
スムーズな書類提出のためにも、事前に手元にあるかを確認しておくと安心です。
マイナンバー
マイナンバーは、社会保障や税、災害対策などの行政手続きに利用される個人番号で、入社時の重要な書類のひとつです。
企業は給与支払いや社会保険の手続きでマイナンバーを使用するため、本人からの提出が求められます。
提出の際は、マイナンバーカードや通知カード、もしくはマイナンバー記載の住民票など、番号が確認できる書類と本人確認書類の両方が必要です。
厳重な個人情報のため、企業側も厳格な管理体制を整える必要があります。
提出時はコピーを取るなどして、再確認しておきましょう。
給与振込先届出書
給与振込先届出書は、従業員の給与を正しく支払うために必要な書類です。
企業が給与を銀行口座へ振り込むには、口座情報の正確な把握が欠かせません。
届出書には、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人などを記入してもらいます。
記入ミスがあると振込エラーが発生し、支払い遅延の原因になります。
新入社員に提出を求める際は、通帳やキャッシュカードのコピーを併せて確認し、口座情報に誤りがないかを丁寧にチェックしましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、所得税の計算に必要な情報を企業へ提出するための重要な書類です。
扶養家族の有無や人数によって所得税の控除額が変わるため、正しく記入・提出されていない場合、給与からの税額控除が過剰または不足になるおそれがあります。
書類には、扶養親族の氏名・生年月日・続柄などを記載します。提出のタイミングは入社初日が基本ですが、異動があった場合も速やかに再提出が必要です。
企業側は記載内容を確認し、税務処理に反映させる体制を整えておくことが求められます。
健康保険被扶養者(異動)届
「健康保険被扶養者(異動)届」は、入社する従業員に扶養家族がいる場合、その家族を健康保険の被扶養者として登録するために必要な書類です。
提出がないと、扶養家族が健康保険を利用できないため、医療費が全額自己負担になるおそれがあります。
届出には、被扶養者の氏名や生年月日、続柄、所得の有無などを記載し、必要に応じて住民票や所得証明書などの添付書類が求められることもあります。
企業側は従業員からの書類提出を受けて、健康保険組合または協会けんぽへ速やかに届け出る必要があります。
適切な手続きをおこなうことで、従業員とその家族の医療保障が確保されます。
雇用保険被保険者証(※転職者のみ)
雇用保険被保険者証は、過去に雇用保険へ加入していたことを証明する書類であり、転職者が新たな企業で雇用保険に加入する際に必要となります。
この証明書には被保険者番号が記載されており、企業がハローワークで手続きをおこなう際に欠かせません。
前職の退職時に交付されているのが一般的ですが、紛失した場合は再発行も可能です。
提出を忘れると、雇用保険の加入履歴が正しく引き継がれないリスクがあります。
そのため、入社手続き時に早めの確認と書類提出を従業員へ促すことが重要です。
企業側も、書類管理を徹底し、確実に手続きを進めることが求められます。
源泉徴収票(※転職者のみ)
源泉徴収票は、前職での給与や控除内容、支払った所得税の額などが記載された書類で、転職者の年末調整や所得税手続きに必要となります。
入社時にこれを提出してもらうことで、企業側は正確な給与計算や税額調整をおこなうことが可能です。
とくに年内に複数の企業に在籍していた場合、源泉徴収票がなければ正しい所得総額が把握できず、従業員に追徴課税が発生する可能性もあります。
そのため、人事担当者は必ず入社時に書類の提出を依頼し、回収漏れがないようチェックリストなどで管理することが重要です。
入社初日に必要な手続き
入社初日は、新入社員を正式に受け入れるための重要なタイミングです。この日におこなうべき手続きには、書類提出の確認や社内ルールの説明、業務内容のオリエンテーションなどが含まれます。
対応が不十分だと、社員が不安を感じたり、業務の習得が遅れたりする恐れがあります。円滑なスタートを切るためには、手続きの流れを事前に整理し、チェックリストなどで抜け漏れのないよう準備しておくことが大切です。
従業員が提出する書類の確認
入社初日には、従業員から必要な書類がすべて提出されているかを確認する作業が欠かせません。
提出漏れがあると、雇用契約の締結や社会保険手続き、給与計算などに支障をきたす恐れがあります。
具体的には、雇用契約書や扶養控除等申告書、給与振込先届出書、マイナンバーなどをチェックリストで一つずつ確認していくと安心です。
不備があった場合はその場で再提出を依頼し、コピーやスキャンでの保管体制も整えておくことが重要です。
オリエンテーション
オリエンテーションは、新入社員が企業に早くなじむための大切な機会です。
企業理念や社内ルール、就業規則、福利厚生制度などを共有し、業務への理解と安心感を深めます。
加えて、社内の組織体制や業務フロー、人事担当者や上司との顔合わせを通じて、職場への信頼関係を築くきっかけにもなります。
特に小規模な企業では、限られた時間でも丁寧な説明と質問の機会を設けることで、今後の業務に対するモチベーションを高めやすくなります。
業務説明の実施
新入社員には、入社初日に担当する業務内容や流れについて詳しく説明することが重要です。
どのような作業を日常的におこなうのか、誰と関わりながら進めていくのかを明確にしましょう。
そうすることで、不安を軽減しスムーズな業務開始が可能になります。
また、業務の優先順位や注意点、使用するツールやシステムの操作方法など、実務に直結する情報を整理して伝えると、早期戦力化にもつながります。
初日の説明では、質問しやすい雰囲気をつくることも意識しましょう。
入社後におこなう手続き
新入社員の受け入れ後も、企業側ではいくつかの重要な手続きを進める必要があります。
社会保険や雇用保険といった行政への届け出に加え、社内での労務管理体制の整備も欠かせません。
これらの対応を早めにおこなうことで、トラブルの回避や法令順守につながり、従業員も安心して業務に集中できる環境を整えることができます。
行政手続き
社会保険の加入
新入社員が入社した際には、健康保険と厚生年金保険への加入手続きが必要です。
これは企業が法律上の義務としておこなうもので、従業員の医療や将来の年金に関わる重要な制度です。
手続きには「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が求められます。
書類提出は原則として入社日から5日以内に年金事務所へおこないます。
雇用保険の加入
雇用保険の加入は、新入社員が失業した際の給付や教育訓練給付などを受けるために必要な手続きです。
企業は「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出しなければなりません。
通常、入社から10日以内の提出が求められます。
提出には「雇用保険被保険者証」やマイナンバーの情報が必要です。
労災保険の適用
労災保険は、業務中や通勤中のケガや病気に対して補償をおこなう制度です。
企業は、従業員を一人でも雇った時点で自動的に適用対象となります。
特別な手続きは不要ですが、労働基準監督署への事業開始届や労働保険関係成立届の提出が必要です。
労災時のスムーズな対応のため、事前に制度内容を把握しておきましょう。
所得税の手続き
新入社員を迎える際、企業は給与から適切に所得税を源泉徴収し、税務署へ納付する必要があります。
そのためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必須です。
この申告書が未提出の場合、税額が高くなる可能性があるため注意が必要です。
住民税の手続き
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、新入社員が中途入社や転職者であれば、前職からの「特別徴収切替届出書」などの手続きが必要です。
企業はその情報を基に、住民税を給与から天引きする「特別徴収」の設定をおこないます。
正しい書類提出と自治体への届出が、納税のトラブル回避につながります。
特に提出漏れがないよう、早めの確認と対応を心がけましょう。
社内手続き
労働者名簿の作成
労働者名簿は、労働基準法に基づいて作成が義務付けられている重要な書類です。
氏名・生年月日・性別・入社日・雇用契約の内容などを正確に記載し、従業員ごとに管理します。
企業が労働条件を把握し、万が一トラブルが発生した際の証拠資料にもなります。
作成後は適切に保管し、内容の変更があった際には速やかに更新することが求められます。
賃金台帳の作成
賃金台帳は、従業員に支払う給与の詳細を記録する法定帳簿です。
氏名、支給日、労働日数、残業時間、支給額、控除額などを記載し、企業が給与管理や税務対応を正確におこなうために必要不可欠です。
作成・保存が法律で義務付けられており、記載内容が不備だと行政指導や罰則の対象となる場合もあります。
給与に関するトラブルを防ぐためにも、内容を正確かつ定期的に更新して保管しましょう。
出勤簿の作成
出勤簿は、従業員の出勤日数や労働時間、遅刻・早退・欠勤の有無などを記録する書類です。
正確な勤務実績を把握することで、適切な給与計算や残業代の支払い、労働時間管理が可能になります。
また、労働基準監督署からの調査が入った際にも重要な確認書類となるため、企業としては日々の記録を怠らず、タイムカードや勤怠管理システムと連携しながら整備しておく必要があります。
業務用備品や作業環境の準備
新入社員がスムーズに業務を開始できるように、パソコンや電話、デスク、社用携帯などの業務用備品を事前に準備しておくことが大切です。
必要なソフトウェアのインストールやネットワーク設定も済ませておきましょう。
また、作業スペースの整理やロッカーの用意など、快適に働ける環境づくりも重要です。
こうした配慮が、入社初日の不安を軽減し、良好なスタートにつながります。
まとめ
新入社員の入社手続きは、企業にとって重要なスタート地点です。
書類の準備や提出内容の確認、雇用契約の取り交わし、健康診断の実施、社会保険や税金に関する事務処理など、やるべきことは多岐にわたります。
特に小規模な企業では担当者が兼務しているケースも多いため、事前に流れを整理しておくことでミスや遅れを防ぐことができます。