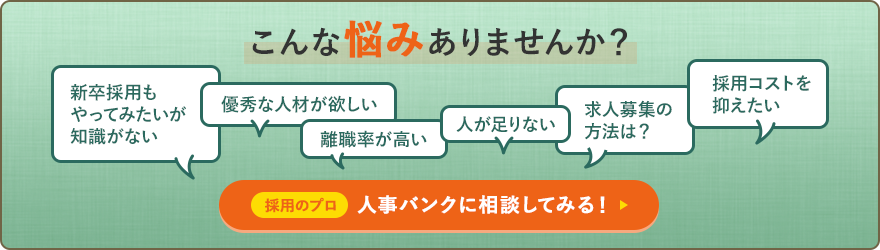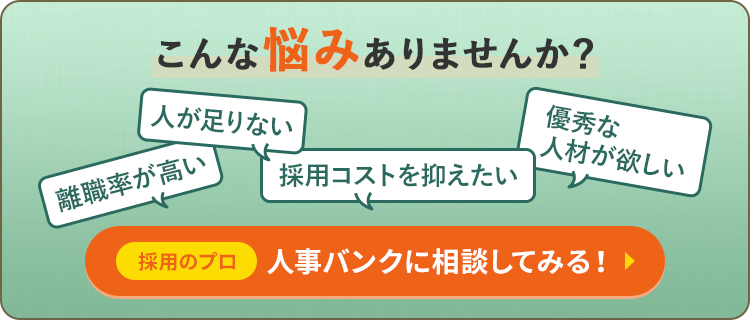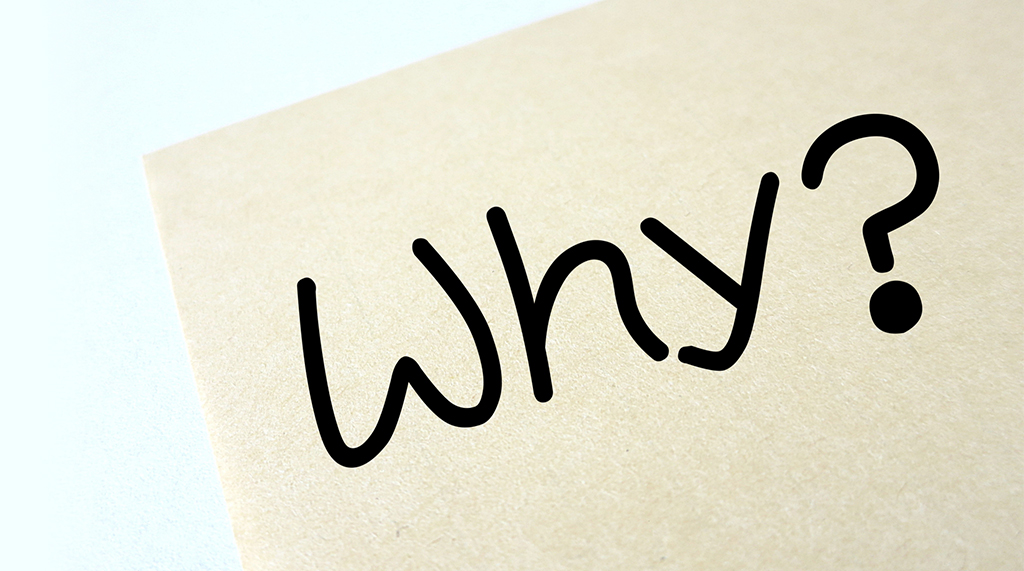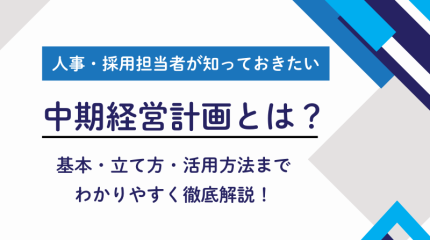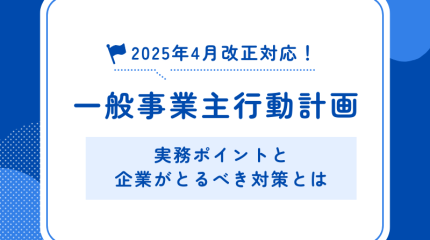休日や就業後にも会社から連絡が来ることはありませんか。
スマートフォンやタブレットの普及により、社員同士のコミュニケーションが円滑になりましたが、業務時間外にメールや電話の対応に追われる方も少なくないそうです。
気軽に連絡できる時代だからこそ、ついつい業務時間外に連絡を入れてしまう方もいるかもしれません。
今回は、業務時間外の連絡に関するリスクについて述べていきます。
業務時間外の電話は労働基準法違反 ?
労働基準法の観点から勤務時間外に業務に関する電話は、基本的にアウトです。
労働基準法では、下記のように規定しています。
|
「会社は従業員に対して少なくとも週1日休日を与える(労働基準法 第35条)」 「PM10:00~AM5:00の間の労働は通常の労働時間の賃金より0.25倍以上の割り増し賃金を支払う(労働基準法第37条)」 |
連絡を受けた本人が業務と感じたのであれば、間違いなく労働です。
メールやLINEの場合は判断が難しいですが、返信を強要した場合は、れっきとした業務時間になります。
とはいっても、「連絡」を「業務」と意識している会社が少なく、従業員も対応せざるを得ない状況ということであまり問題視はされてきませんでした。
やむを得ない理由で、どうしても業務外に連絡しなければならないシーンもあるかもしれませんが、受け手の気持ちを考えて連絡をするようにしましょう。
また、休日などの業務時間外に職場から連絡があっても、出る必要はありません。
多くの人が業務時間外の連絡をストレスに感じている
フリーター・既卒向けの就職支援サービス「ハタラクティブ」を運営するレバレジーズは、2018年12月14日に勤務時間外の業務連絡に関するアンケート結果を発表。
正社員経験のある18~30歳の96名から回答を得たところ、業務時間外に連絡を受けたことがある方は約6割、連絡を受けた約9割の方は対応するというデータが出ました。
勤務時間外の連絡をストレスと感じる方は約8割。
あまり意識をしていないかもしれませんが、業務外の連絡も立派な業務になります。
従業員のストレスを減らすためにも、業務外の連絡は極力控えるべきでしょう。
業務時間外の連絡が及ぼす悪影響
業務時間外の連絡を頻繁に行った場合、どういった影響を及ぼすのか見ていきましょう。
従業員に大きな負担がかかる
業務時間外の連絡は、従業員の“心身”に悪影響を及ぼす可能性があります。
実際に、「過労死」や「過労自殺」が原因で亡くなる方の多くは、業務外にも上司からの叱責や取引先からのクレームといった精神的な負荷が大きい連絡が頻繁にあったことが多いそうです。
死亡事故に至らないまでも、不眠や頭痛、不安神経症など、さまざまな不調や病気を呼び起こす原因となり得ます。
業務時間外の連絡が多い会社は、従業員の人生を左右しかねないということを肝に銘じて、意識を変えていくことが大切です。
取引先から連絡を受けることが多い場合は、会社側が「時間外の対応はできない」と伝えることも、必要でしょう。
生産性が低下する
退勤後や休日など業務時間外に電話・メールの対応が続くと、仕事とプライベートの境目が曖昧になります。
当然ですが、本来休むべき時間に休めなければ、従業員はストレスを溜めるでしょう。
ストレスによって心身に疲労が溜まっていくと、集中力や判断力、モチベーションの低下につながります。
その結果、ミスを起こしやすくなったり、効率が悪くなったりするため、生産性も低くなるのです。
パワハラになる可能性がある
上司が部下に対して、業務時間外の電話やメールでの対応を催促することも問題です。
終業後や休日の対応を強要する行為はハラスメントにあたり、離職リスクの向上につながります。
基本的には業務時間外に対応させないことが重要です。
企業側から管理職や指導を担当する社員に教育・研修を実施することも、業務時間外の対応による悪影響を減らせます。
海外の事例
世界に先駆けて、業務外の連絡に歯止めをかけたのはフランスです。
2017年1月から、業務時間外に仕事用電子機器の電源を切る権利を法律で定めました。
そもそもフランスでは、国民のプライベートを守るという意識が強く根付いており、2000年には週の労働時間を35時間にする体制が導入されています。
業務時間外の連絡に規制をかけたこの法律は、国民のプライベートを守る体制をより強固にしました。
フランスの流れを受けて、アメリカのニューヨークでも業務外の連絡に関する法案が協議されています。
2018年に提案された法案の内容は、「従業員10名以上の企業で、休日や欠勤、有給休暇中の従業員にメールで連絡を取ることを禁止にする」というものです。
違反した雇用者に対して、250ドルまたは500ドルの罰金が科せられるそうです。
企業単位で業務外の連絡に関して取り組んでいる企業もあります。
ドイツのフォルクスワーゲンでは、夜間のメール送受信を制限するためにサーバーをオフ。
エスティローダーでは金曜日夜から月曜日朝までメールの送受信を禁止にしています。
もちろん賛否両論ではあるので、今後も業務外の連絡の規制に関して、各国で議論されていくことでしょう。
まとめ
LINEやSkypeといったツールの普及により、今まで以上に業務連絡が手軽にできるようになりました。
しかし、業務時間外の連絡はストレスが徐々に蓄積されていき、従業員の心身に悪影響をもたらします。
利便性だけに目を向けるのではなく、起こる可能性があるリスクを理解しておくことが大切です。
業務時間外の連絡は、労働基準法違反になりうる可能性があるので、会社全体で意識して取り組んでいきましょう。