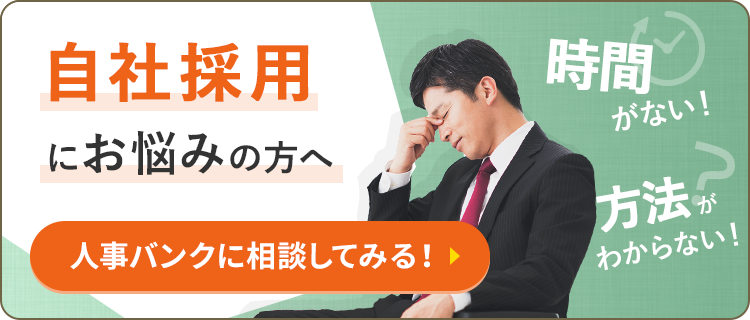1on1面談は、上司と部下が定期的に対話し、業務課題やキャリア、モチベーションを共有する重要な場です。
しかし、質問内容や進め方を誤ると形骸化し、効果が薄れてしまいます。
本記事では、人事担当者が押さえるべき成功の原則や定着のコツ、そして面談を活性化させる質問30選を紹介します。
そもそも1on1とは?人事評価面談との違いと目的
1on1とは、上司と部下が定期的におこなう1対1の対話で、業務課題やキャリアの方向性、モチベーションなどを率直に話し合う場を指しています。
評価や査定を目的とする人事評価面談とは異なり、信頼関係の構築や成長支援を重視するのが特徴です。
ここでは、両者の違いと1on1の本来の目的を解説します。
1on1と人事評価面談の決定的な違い
「1on1」の目的は部下の成長支援や業務改善、心理的安全性の確保であり、評価や査定ではなく信頼関係の構築と課題の洗い出しをおこなうのが特徴です。
対して、「人事評価面談(査定面談)」は、一定期間の成果や行動を評価し、昇給・昇格・賞与などの処遇に反映するための公式な場を指しています。
この2つは目的も進め方も異なるため、混同すると効果が半減してしまうので注意してください。
それぞれの違いは下記の通りです。
| 種目 |
1on1面談 |
人事評価(査定)面談 |
|
目的 |
部下の成長支援、課題解決、信頼関係構築 |
成果・行動の評価と処遇決定 |
|
主なテーマ |
業務課題、キャリア相談、モチベーション、悩み共有 |
過去の成果・行動評価、査定結果の説明 |
|
実施頻度 |
週1回〜月1回など高頻度 |
半期・年度など評価期間ごと |
|
進め方 |
部下が話しやすい雰囲気で傾聴・対話中心 |
上司が評価を伝達し、必要に応じてフィードバック |
|
時間 |
30分前後 |
30分〜1時間 |
|
評価の有無 |
評価はしない |
評価が必ずおこなわれる |
|
記録の目的 |
成長支援や課題解決の継続的フォロー |
処遇決定のための公式記録 |
企業が1on1を導入する3つの目的(人材定着・成長促進・課題発見)
1on1は、部下との定期的な対話を通じて、組織や人材の質を高める重要な取り組みです。
その目的は「人材定着」「成長促進」「課題発見」の3つです。
・人材定着 悩みや不安を早期に把握して解消し、離職を防ぐこと
・成長促進 フィードバックや助言により、スキルアップやキャリア形成を支援するのが目的
・課題発見 現場視点で業務や組織の問題をいち早く見つけ、改善に結びつけるかが肝心
これら3つの目的が、企業の持続的な成長を後押ししてくれるでしょう。
1on1がもたらす組織へのメリット
1on1は、個々の社員だけでなく組織全体にも多くのメリットをもたらします。
定期的な対話によってコミュニケーションが活性化し、部署間や上下間の信頼関係を強化させることが可能です。
また、現場の声を経営層や管理職が直接把握できるため、意思決定の精度やスピードが向上します。
さらに、社員のモチベーションやエンゲージメントが高まり、生産性やチームワークの向上につながるでしょう。
結果として、組織の健全性と競争力が持続的に強化されます。
目的別・1on1でそのまま使える質問テンプレート集
1on1面談を効果的に進めるには、目的に応じた質問が欠かせません。
漠然と話を始めると、表面的なやり取りに終始してしまい、成長支援や課題解決の機会を逃してしまいます。
ここでは、目的別・1on1でそのまま使える質問テンプレートを紹介します。
信頼関係を築くための質問(アイスブレイク)
1on1の冒頭で軽いアイスブレイクを取り入れると、部下が安心して話せる雰囲気をつくることができます。
信頼関係を築くための質問の例は、下記の通りです。
・最近プライベートであった嬉しいことは?
・今ハマっている趣味や活動は?
・休日はどのように過ごしてる?
こうした質問は、仕事以外の話題から自然に会話を始められるため、緊張を和らげる効果があります。
また、部下の価値観やライフスタイルを理解するきっかけとなり、日常的な関心や信頼感の積み重ねにつながるかもしれません。
心身の健康やコンディションを把握する質問
1on1で部下の心身の状態を確認することは、働きやすい環境づくりや早期の問題発見につながります。
具体的にどのような質問が効果的なのか、例は下記の通りです。
・最近、仕事やプライベートでストレスを感じていることはある?
・今の体調や気分はどう?
・仕事の負荷やペースについて問題ない?
こういった質問は、部下の健康状態や精神的な負担を把握しやすくなります。
早めに問題を察知できれば、適切なフォローや業務調整ができるので、長期的なパフォーマンス低下や離職リスクの軽減につながるでしょう。
モチベーションの源泉と阻害要因を探る質問
部下のやる気の源泉や逆にモチベーションを下げる要因を理解することは、適切なサポートや環境整備に欠かせません。
具体的な質問例は、下記の通りです。
・仕事で一番やりがいを感じる瞬間はどんなとき?
・最近、仕事でモチベーションが下がったことはない?
・どんな環境やサポートがあれば、もっと力を発揮できる?
少し込み入った質問を通じて、部下の内発的な動機や外部環境の課題が把握できるケースがあります。
モチベーションの源泉を知れば、適切な目標設定や評価ができるでしょう。
業務の課題や改善点を発見する質問
1on1で部下が抱える業務上の課題や改善点を引き出すことは、組織全体の効率化や品質向上につながります。
業務の課題や改善点を発見する質問例は、下記の通りです。
・今の仕事で特に困っていることや障害になっていることはある?
・業務の中で改善したいプロセスや方法はある?
・チームや部署内での連携で課題を感じている部分はある?
仕事に直結する質問は、現場での具体的な問題点を明らかにしやすく、上司が迅速に支援や調整をおこなうための情報収集に役立ちます。
課題を共有すれば、部下のストレス軽減やモチベーション向上にもつながり、結果的に業務の質やスピードアップにつながるでしょう。
キャリアプランと成長意欲を引き出す質問
部下の将来の目標や成長への意欲を把握することで、効果的な支援やモチベーションアップが期待できます。
キャリアプランと成長意欲を引き出す質問例は、下記の通りです。
・今後、どのようなキャリアを目指している?
・新しく挑戦してみたい仕事やスキルはある?
・会社や上司に期待するサポートや環境はある?
キャリアに関する質問により、部下の長期的なビジョンや成長意欲を明確にできます。
また、上司が支援姿勢を示すことで信頼感が高まり、継続的な成長を促進します。
部下のタイプ別|質問の使い分けとアプローチ法
部下一人ひとりの性格や状況は異なるため、画一的な質問や対応では効果が十分に得られません。
タイプに応じて質問内容やアプローチ方法を変えれば、より深い理解と信頼関係の構築が可能になります。
ここでは、タイプ別の特徴と、それぞれに効果的な質問例や対応ポイントを解説し、1on1の質を高めるヒントを紹介していくので参考にしてみてください。
新入社員・若手社員向け:安心感を与え、成長を促す質問
新入社員や若手社員は、業務に慣れていないことから不安や緊張を抱えやすいです。
安心感を与える質問例は、下記の通りです。
・今の仕事で分からないことや困っていることはある?
・最近、うまくいったことや嬉しかったことはある?
・今後チャレンジしてみたいことや身につけたいスキルはある?
仕事や将来の悩みに関する質問をすることで、安心して話せる環境を作りあげられます。
成功体験を共有すれば、自己肯定感を高めるきっかけになるでしょう。
上司は焦らず丁寧に話を聞き、成長のペースに合わせたサポートを心がけることが重要です。
特に若手は、ワークライフバランスを重視する傾向があるので、慎重に面談を進めていきましょう。
これにより若手社員の自信と意欲を引き出し、長期的な成長につなげることができます。
中堅社員向け:中だるみを防ぎ、キャリアの再認識を促す質問
中堅社員は経験を積む一方で、仕事への熱意が薄れがちになる「中だるみ」の時期でもあります。
キャリアの方向性を再認識させるための質問例は、下記の通りです。
・最近、仕事に対してどんなやりがいや達成感を感じている?
・今後のキャリアで挑戦してみたいことや目標はある?
・仕事を進める上で、改善したい点や新たに取り入れたい方法はある?
これらの質問を通じて、中堅社員自身が自分の仕事やキャリアを見つめ直すきっかけをつくることができます。
上司は押し付けにならず、対話を重視しながら、社員の意欲を引き出しサポートする姿勢を持つことがポイントです。
自己評価と周囲の評価が大きく離れていないか、話を聞くことも重要になってくるでしょう。
ハイパフォーマー向け:さらなる挑戦意欲と権限移譲を促す質問
ハイパフォーマーは高い成果を出している一方で、さらなる成長や役割拡大への意欲を引き出すことが重要です。
適切な質問で挑戦意欲を刺激し、責任ある仕事を任せる準備を整えましょう。
・次に挑戦したい業務やプロジェクトはある?
・現在の仕事でさらに裁量を広げたい分野はある?
・上司や組織に期待するサポートや権限移譲のポイントはある?
これらの質問は、ハイパフォーマーの自己成長欲求を明確化し、役割の拡大や権限移譲をスムーズに進める助けとなります。
上司は信頼していることを示しながらも、過度な負担を避けて、期待していると伝える質問をおこなうことが肝心です。
課題を抱える社員向け:原因を共に探り、解決策を考える質問
課題を抱える社員には、一方的な指摘ではなく、共感と協力を通じて問題の本質を理解したうえで質問をおこなうことが大切です。
解決に向けた具体的なアクションを一緒に考えましょう。
・現在感じている困難や課題はある?
・その課題の原因を理解していてサポートできることはある?
・どのようなサポートや改善策があれば、状況が良くなると思う?
これらの質問を通じて、社員自身が問題を整理しやすくなると同時に、上司も課題の背景を深く理解できます。
上司は批判せず、寄り添う姿勢で対話を進め、解決に向けた協働の意識を高めることが重要です。
これにより、社員の自己効力感が向上し、課題克服のための具体的な行動を促せます。
こんな1on1は逆効果!よくある失敗事例とNG質問
1on1は正しく運用すれば大きな効果を発揮しますが、進め方や質問の内容次第では逆効果になることもあります。
形式的になったり、一方的な評価や詰問が続いたりすると、信頼関係が崩れ、部下のモチベーション低下やコミュニケーションの停滞を招く恐れがあるでしょう。
ここでは、よくある失敗事例と避けるべきNG質問を紹介し、効果的な1on1運用のポイントを解説します。
失敗事例1:尋問・詰問の場になってしまう
1on1が尋問や詰問の場になると、部下は萎縮して本音を話せなくなり、信頼関係が損なわれます。
これは、上司が評価や問題点の指摘に偏りすぎて、一方的に責めるような態度を取ってしまうことが原因です。
部下は「怒られる」「責められる」と感じると、防御的になり、問題の本質や改善のヒントを共有しなくなります。
上司はまず部下の話にしっかり耳を傾け、共感的な姿勢で接することが大切になります。
また、課題を共有しながら一緒に解決策を考える協働的なスタンスを持つことで、部下の安心感と積極的な発言を促せます。
失敗事例2:上司が一方的に話し、アドバイスしてしまう
1on1は部下の話を聞き、考えを引き出すことが主目的です。
一方的な話やアドバイスが続くと、部下は自分の考えを深めるチャンスを失い、主体的な行動や成長意欲が低下します。
また、コミュニケーションが一方通行になり、信頼関係の構築も難しくなるでしょう。
上司は「聴く」姿勢を徹底し、部下が話しやすい環境を作ることが重要です。
具体的には、質問を投げかけて考えを促し、部下の意見や感情に共感的に応答します。
アドバイスは必要最低限にとどめ、部下自身が解決策やアクションプランを考えられるようサポートしましょう。
失敗事例3:ただの世間話で終わり、何も残らない
軽い話題は緊張をほぐすために有効ですが、それだけで終わると面談の意味が薄れてしまいます。
1on1は部下の現状把握や課題発見、成長のための時間です。
雑談だけでは具体的な問題や目標設定ができず、次のアクションに結びつかないため、継続的な改善やモチベーション向上に寄与しません。
結果的に、部下の信頼や満足度も低下しやすくなります。
雑談で場を和ませた後は、目的に沿った質問で具体的な話題へと導きましょう。
また、面談の最後には次回までの具体的な課題や目標を設定し、振り返りにつなげることで、1on1の効果を高められるでしょう。
まとめ
1on1面談を効果的に運用するためには、多様な質問パターンを知ることが大切ですが、それだけでは不十分です。
部下との信頼関係を築き、成長を促すには、対話の質を高めるための成功の原則を理解し、継続的に実践することが求められます。
また、組織全体で1on1を定着させるための仕組みや文化を整えることも欠かせません。
1on1の成功は、良い質問を知ることだけでなく、それを支える原則の理解と、組織としての仕組み作りが鍵であるということを忘れずに進めましょう。