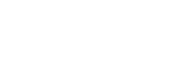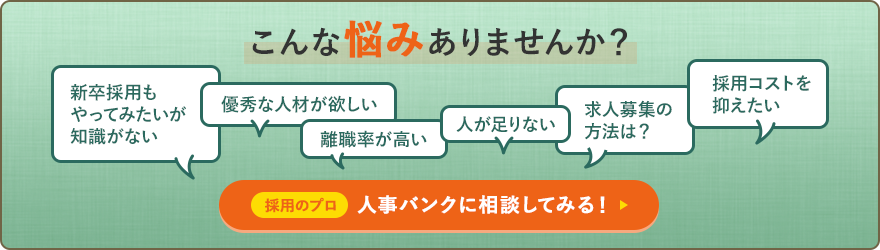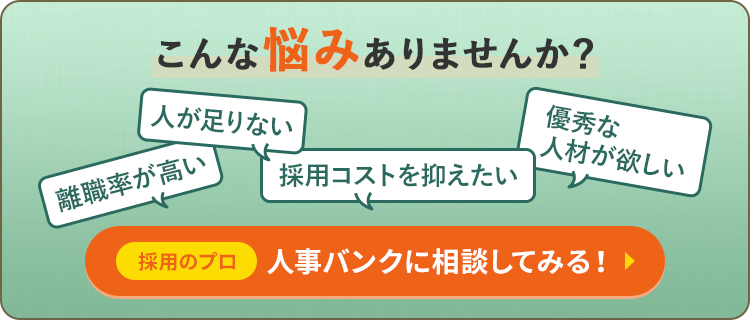コンティンジェンシー理論は、リーダーシップ理論の一種です。
現代のビジネス環境は先行き不透明な要素が増えており、それに応じてリーダーシップの役割も変化を求められています。
このように、変化に合わせた柔軟な対応が求められる現在、注目されているのがコンティンジェンシー理論です。
本記事では、コンティンジェンシー理論の概要や誕生の背景について解説し、そのメリットやデメリット、活用する際のポイントについてもお伝えします。
コンティンジェンシー理論とは?
コンティンジェンシー(contingency)は、「偶然性」や「偶発性」を意味します。
コンティンジェンシー理論とは、リーダーシップ理論の一種で「どのような環境や状況にも適応できるリーダーシップは存在しない」という理論です。
リーダーシップの効果性は状況に応じて変化するという考え方で、1つのリーダーシップスタイルが全ての状況に適用できるわけではありません。
企業の経営スタイルは市場や競合状況などの影響を受けます。
そのため、リーダーシップはリーダー個人の資質ではなく、「環境や状況に応じて組織の管理方法を変えていく必要がある」というのが、この理論の特徴です。
リーダーは状況に応じたスタイルの変化を求められるため、「状況適合理論」とも呼ばれています。
コンティンジェンシー理論の類義語
コンティンジェンシー理論に似た意味を持つ言葉に、
- 条件適合理論
- SL理論
があります。それぞれの特徴とコンティンジェンシー理論との関係性は、以下の通りです。
条件適合理論
組織の環境によって優れたリーダーの定義が変わるという考え方が、条件適合理論です。
条件適合理論は、コンティンジェンシー理論を含む現在のリーダーシップ理論の基礎となっています。
この理論の特徴は、成果を生むためにはリーダーの行動だけでなく置かれている環境も重要であり、環境条件に適した行動のみがリーダーシップ効果を発揮すると考える点です。
条件適合理論では、リーダーが力を発揮するためには、職場の人間関係と業務の難易度を考慮する必要があるとされています。
SL理論
SL理論は、状況に合わせて対応するリーダーシップ(Situational Leadership)のことで、コンティンジェンシー理論をさらに掘り下げ、部下の習熟度に焦点を当てた理論として発展しました。
コンティンジェンシー理論とSL理論の違いは、リーダーシップを変化させる要素です。
コンティンジェンシー理論では、外部環境や組織内の要因など、外部や内部の要素によってリーダーシップを変えます。
一方、SL理論では、部下の成熟度に着目することが特徴です。
部下は知識、経験、スキル、モチベーションなどの観点から4段階に分類され、リーダーは部下の成長段階に応じてリーダーシップを変化させます。
コンティンジェンシー理論の誕生背景
コンティンジェンシー理論が生まれた背景には、既存のリーダーシップ理論であるリーダーシップ資質論や、リーダーシップ行動論なども関係しています。
ここでは、コンティンジェンシー理論が誕生した背景について、1940年代と1960年代、1960年代以降に分けてリーダーシップ論を解説します。
1940年代までのリーダーシップ論
1940年までのリーダーシップ論は、「リーダーシップ資質論」が主流でした。
リーダーシップ資質論は、優れたリーダーは共通した資質や特性を持っているという考え方です。
「リーダーは作られるものではなく、生まれつき持つ資質による」という視点から、優れた才能を持つ人こそがリーダーとして成功する可能性が高いと考えられたのです。
身体的特徴や精神的特徴、性格的特徴や知能などがリーダーの資質とされ、徳川家康やリンカーン、ケネディなどの人物が研究の対象となりました。
しかし、研究結果からは特性や資質とリーダーシップの相関関係を見いだせず、「リーダーの資質」を特定できませんでした。
1960年代までのリーダーシップ論
1940年代から1960年代まで提唱されたリーダーシップ論に、「リーダーシップ行動論」があります。
リーダーシップ行動論は、1940年代以前のリーダーシップの資質論とは反対に、「リーダーは行動によって作られる」という考え方です。
リーダーシップ行動論は「機能論」または「職能論」とも呼ばれ、訓練によって必要な行動を身につけた人がリーダーになるとされます。
組織力を向上させるために、課題を達成するための機能(Task)と、人間関係に配慮し集団を維持する機能(Relation)の両方が必要だという考え方です。
1960年代以降のリーダーシップ論
1960年代に入ると、技術の進歩や需要の多様化により、企業や他の組織における生産や販売のプロセスがますます複雑化しました。
また、企業の国際化に伴って事業が世界中に広まり、より複雑な経済・文化状況下に置かれるようになりました。
こうした多様で複雑な環境では、従来のリーダーシップ論で言われていた「1つのリーダーシップスタイルがすべての状況に適応できる」という考えが通用しなくなったのです。
多様化する時代に対応するため、リーダーシップ論はさまざまな条件下での研究が行われるようになり、その中で「コンティンジェンシー理論」が生まれました。
コンティンジェンシー理論を発展させた概念
コンティンジェンシー理論を発展させた概念として、
- バーンズ&ストーカーの「有機的組織」
- ローレンス&ローシュの「組織の条件適合理論」
- フィドラー「コンティンジェンシー・モデル」
が挙げられます。
バーンズ&ストーカー「有機的組織」
イギリスの社会学者バーンズと、心理学者ストーカーによる事業組織の構造に関する研究です。
バーンズとストーカーは、イギリスの20の企業の組織構造と業績の関係を調査しました。
官僚的な「機械的組織」と柔軟な「有機的組織」の2つの組織構造を定義し、それらが異なる状況下でどのように機能するかを調べたのです。
研究によると、
- 技術革新や顧客ニーズが多様化している環境…個人が自発的に判断し行動する「有機的組織」
- 外部変化が穏やかな環境…ピラミッド構造を持つ「機械的組織」
が有効だとしています。
つまり、これらの2つの組織構造は外部要因によって有効性が変化するため、状況に応じて望ましいリーダーシップのスタイルが異なるのです。
ローレンス&ローシュ「組織の条件適合理論」
ハーバードビジネススクールの教授であるローレンスとローシュの研究です。
コンティンジェンシー理論の名が一般化したのは、彼らが1967年に著した『組織の条件適応理論』がきっかけです。
ローレンスとローシュは、環境の異なる3つの業種を対象に、「分化」と「統合」という観点から組織の構造と業績の関連性を調査しました。
その結果、組織内部の状況やプロセスが外部環境に適合していれば、高い業績を上げられるという結論が出ました。
また、企業組織の内部状態・プロセス・外部状況はぞれぞれ異なるため、「唯一最善の方法」は存在しません。
リーダーシップの観点においても、どのような環境・状況にも適合するリーダーシップスタイルは存在しないとの見解を示しています。
フィドラー「コンティンジェンシー・モデル」
アメリカの心理学者フィドラーによる理論で、リーダーシップスタイルは集団が置かれた課題状況に応じて異なるという考え方です。
この理論では、リーダーシップの有効性に関連する条件を「状況好意性」という概念で定義されています。
状況好意性の「状況変数」は、
- リーダーが組織の他のメンバーに受け入れられる度合い
- 仕事・課題の明確さ
- リーダーが部下をコントロールする権限の強さ
の3つの要素で表されます。
フィドラーは、この3つの変数が高い場合にはリーダーシップを発揮しやすくなり、低い場合はリーダーシップの発揮が困難になると提唱しています。
コンティンジェンシー理論のメリット
コンティンジェンシー理論には、以下のようなメリットがあります。
- 環境に合わせて柔軟に対応できる
- 組織変革を進めやすい
- ヒエラルキーの影響を受けづらい
- ゼネラリストの力が身に付く
それぞれについて見ていきましょう。
環境に合わせて柔軟に対応できる
コンティンジェンシー理論は、環境に応じて役割を変えるため、組織の状況や環境の変化にも柔軟に対応できます。
コンティンジェンシー理論によれば、どのような状況でも常に正しいリーダーは存在しません。
リーダーに求められるのは「柔軟性」です。状況を十分に理解し、望まれる行動を適切に取る能力が求められます。
組織変革を進めやすい
組織は環境の変化に対応する必要があり、そのためにはリーダーや組織自体が進化する必要があります。
変化することで組織は常に進化して現状維持を避けられるため、組織改革を進めやすくなるでしょう。
コンティンジェンシー理論は、企業の成長ステージに合わせて組織を柔軟に変化させていくため、不透明な環境下でも適応力のある組織を作れます。
ヒエラルキーの影響を受けづらい
コンティンジェンシー理論では、環境に順応する組織作りを行うため、上下関係に依存しない組織が求められます。
バーンズ&ストーカーの研究でも紹介した通り、不安定な環境下において、ヒエラルキー組織は有効とはなりません。コンティンジェンシー理論は、この問題点を引き継ぎ、組織の成果は組織環境と構造によって異なるとしています。
ゼネラリストの力が身に付く
ゼネラリストとは、ある分野に特化せず、幅広い知識や技能を持っている人のことをです。
常に変化する状況に適応するためには、その時々に必要な行動や知識、考え方を変える必要があります。
そのため、コンティンジェンシー理論に基づくリーダーは、幅広い知識やスキルを身につけることができ、ゼネラリストとしての力が身に付きます。
コンティンジェンシー理論のデメリット
コンティンジェンシー理論は、多くのメリットを持つ一方で、以下のような欠点もあります。
- 組織管理が難しい
- ノウハウが蓄積しづらい
組織管理が難しい
組織の方針や理念が状況に応じて変化するため、組織を管理することが難しくなるのがデメリットです。
周囲の変化に合わせて常に組織構造を変える必要があるため、正確に現状把握できない場合、誤った方向に進む可能性があります。
そのため、組織を主導する側には適切な手腕が求められます。
ノウハウが蓄積しづらい
リーダーの方針や組織の変化によって組織の状況が不安定になると、組織内にノウハウが蓄積しにくくなります。
その結果、企業独自の競争力が低下し、長期的な成長が妨げられる可能性もあるでしょう。
ノウハウを蓄積させるためには、業務の記録や知識の共有を全従業員で積極的に行うことが不可欠です。
コンティンジェンシー理論を活用する方法
コンティンジェンシー理論の効果を実感するためには、どのように活用すれば良いでしょうか。以下に、コンティンジェンシー理論を利用する際の3つのポイントをご紹介します。
多様な人材を採用する
時代の変化や顧客の多様なニーズに対応するためには、社内でさまざまな背景や価値観を持った従業員に活躍してもらうことが必要です。
したがって、特定の人材のみに着目するのではなく、多様な人材を獲得することが重要です。
コンティンジェンシー理論の導入と併せて、国籍や年齢、性別や障害に限定されない多様な人材を採用しましょう。
多様な人材が活躍できる環境を整えることで、新たな価値の創造や生産性、企業としての競争力の向上などが期待できます。
グローバル化に対応する
「異文化を理解する能力」と「異文化コミュニケーション能力」は、急速に進むグローバル化に対応するために必要な要素です。
これらのスキルを向上させるためには、リーダー個人に任せるのではなく、企業全体もグローバル化の推進に取り組む必要があります。
グローバル化に対応できるリーダーの存在は、企業のグローバルな成長を促進する役割を果たすでしょう。
人事制度を見直す
組織の体制やリーダーシップを変える場合、社内にさまざまな影響があるため、コンティンジェンシー理論を導入する際は、社内環境の整備も同時に進める必要があります。
特に重要なのは、人事制度の見直しと、適切な評価基準や項目の策定です。
従来の評価制度に固執すると、優れた人材がいてもリーダーに選ばれない可能性があります。
組織の潜在力を最大限に引き出すためにも、人事制度を見直し、現状に合わせた評価基準や項目を設定することが大切です。
まとめ
コンティンジェンシー理論とは、組織やリーダーシップの効果性は状況に応じて変化するという考え方です。
コンティンジェンシー理論を利用すれば、組織や従業員が環境の変化に柔軟に対応できます。
ヒエラルキーの影響が少なくなり、ゼネラリストの力が身に付くなどのメリットを得られるでしょう。
ただし、変化によって組織管理が難しくなったり、ノウハウが蓄積しにくくなったりすることもあります。
ご紹介したコンティンジェンシー理論のポイントを参考に、自社に合ったリーダーシップのスタイルを検討してみましょう。