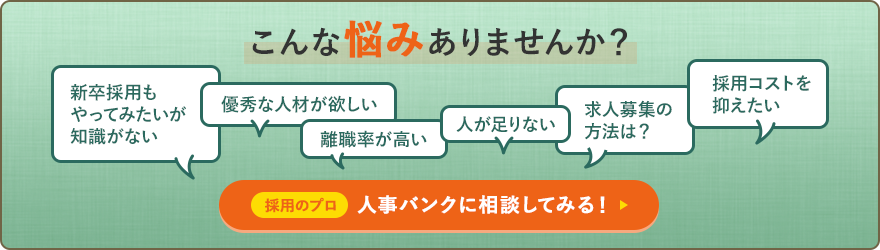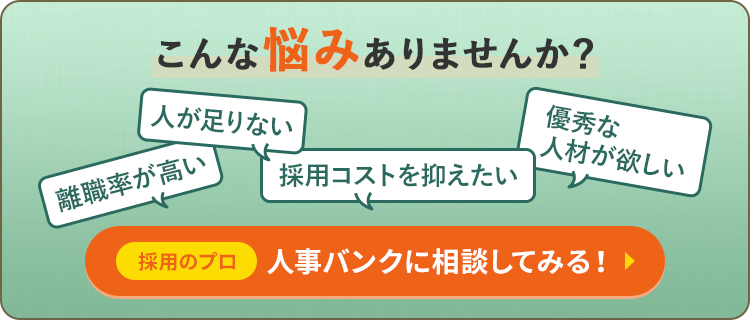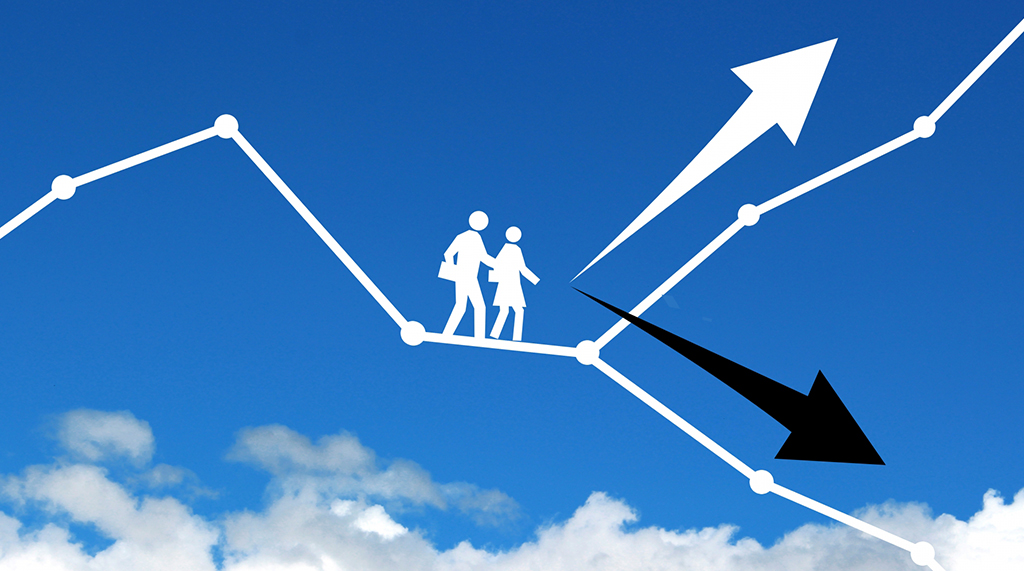組織の活性化や生産性の向上において、働きやすい会社環境を整えることが企業の使命となりつつあります。
そんな現代において、従業員の健康管理を経営課題として捉え、企業が健康増進を掲げる戦略、『健康経営』が注目を集めています。
企業ブランディングにも効果を発揮する健康経営とは一体どのような取り組みなのか、一緒に確認していきましょう。
健康経営が推進される理由とは?
健康経営とは、1992年にアメリカで出版された「The Healthy Company」の著者、ロバート・H・ローゼンによって提唱されたと言われています。
将来的に労働人口の減少が見込まれていることから、企業単位で従業員の肉体的・精神的な健康を増進させ、一人当たりの生産性を高めることが主な目的です。
従業員の活力が向上すれば、結果的に企業の業績改善や株価上昇へ繋がると期待されています。
また、この取り組みは日本再興戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」の1つでもあります。
健康寿命とは単に寿命を延ばすことではなく、健康を維持したまま年を重ねていくことを指しています。
内閣府が発行した『平成27年版高齢社会白書』によると
・女性の平均寿命:86.61歳 / 平均健康寿命:74.21歳
・男性の平均寿命:80.21歳 / 平均健康寿命:71.19歳
上記のような結果がでており、男女ともに平均10年程の不健康寿命があるとされています。
高い医療技術によって平均寿命が世界一となった日本は、今後、健康寿命を延ばしていくことが課題になるでしょう。
健康で生き生きと働ける人が増えれば、労働人口が減少していったとしても、経済の生産性低下を抑えられると考えられるからです。
健康経営のよって生まれる4つのメリット
健康経営を導入することによって、企業は4つのメリットを手にすることができます。
順を追って、1つずつ確認していきましょう。
組織の生産性向上
前述したように、従業員一人ひとりの生産パフォーマンスが向上すれば、おのずと組織全体の生産性が高まり、業績UPや株価上昇といったプラスの効果を得られるはずです。
組織力の向上
健康経営に取り組むためには、従業員とのコミュニケーションが必須となります。
必然的に職場の風通しも良くなるため、組織本来の力を引き出すことができるでしょう。
外部評価の向上
生産性や組織力が向上し、将来的に発展していく企業だと認識されれば、社会的信用が高まります。
また従業員への長期的な投資を行う企業として、採用活動への好影響も見込まれます。
社会の活性化
健康経営に取り組む企業が多ければ多いほど、地域全体の活性化にも期待できます。
このような活性地域が増加していけば消費活動の活発化へと繋がり、景気回復を助長するきっかけとなることでしょう。
健康経営は株式市場でも高い評価を得る
経済産業省と東京証券取引所は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる会社を上場企業の中から選定し、『健康経営銘柄』として公表しています。
この認定は2015年からスタートし、初年度は22社が選定されました。
これまでに選定された企業
・2015年 全22社/花王株式会社、株式会社大和証券グループ本社、TOTO株式会社 等
・2016年 全25社/株式会社ワコールホールディングス、リンナイ株式会社 等
・2017年 全24社/味の素株式会社、株式会社デンソー、バンドー化学株式会社 等
・2018年 全26社/住友林業株式会社、コニカミノルタ株式会社、フジ住宅株式会社 等
健康経営銘柄は、「健康経営が経営理念・方針に位置づけられているか」「健康経営に取り組むための組織体制が構築されているか」「健康経営に取り組むための制度があり、施策が実行されているか」「健康経営の取り組みを評価し、改善に取り組んでいるか」「法令を遵守しているか」という5つの観点で選考されます。
経営者から現場従業員までの意見を総合的に判断しているため、全社を挙げた取り組みとなっているかを厳しく評価されるようです。
健康経営に取り組む企業事例
健康経営銘柄に4年連続認定されている企業が実際に取り組んでいる事例をご紹介したいと思います。
花王株式会社
健康経営銘柄が施行される前、2008年度から健康経営に取り組んでいる同社。
「ヘルステラシーの高い社員を増やす」を目標として掲げ、外部専門家による協力体制を構築することで組織的な健康経営に取り組んできました。
2017年からは中期経営計画「K20」が始動し、従業員とその家族の健康維持を推進するGENKIプロジェクトや、生活習慣病、メンタルヘルス、禁煙などへ個別にアプローチを行う健康経営施策をスタートさせています。
株式会社大和証券グループ本社
「社員が長期にわたって元気に生き生きと働き続けられる環境を整備すること」を目指している同社では、「KA・RA・DAいきいきプロジェクト」という独自の取り組みが評価に繋がっています。
ウオーキングチャレンジ(3ヶ月間1日1万歩を目標にウォーキングに挑戦)や腹八分目プログラム(1ヶ月間腹八分目に挑戦)、Breakfast Everyday(朝食を毎日摂る)など、さまざまなイベントへの取り組みに応じてポイントを付与。
このポイントは健康関連グッズや社会貢献活動への寄与等と交換することができるため、楽しみながら健康増進できる環境が整っています。
まとめ
今後、ますます労働人口が減少していく日本では、『健康経営』を導入して従業員を長く活躍させる企業が増えていくと考えられます。
必要な人数を新たに確保するのではなく、今いる人材に投資し、従業員一人ひとりの生産性を向上させる時代へと突入して行くのです。
また、労働者側も長期的な働き方ができる企業を慎重に選ぶことになるでしょう。
そんなときに注目されるのは、企業自身のブランド力に他なりません。
今回ご紹介した『健康経営銘柄』や中小企業と上場していない大手企業を対象とした『健康経営優良法人認定制度』は、企業ブランディングに大きく寄与しているため、人材採用において差別化を図れるポイントとなりそうです。