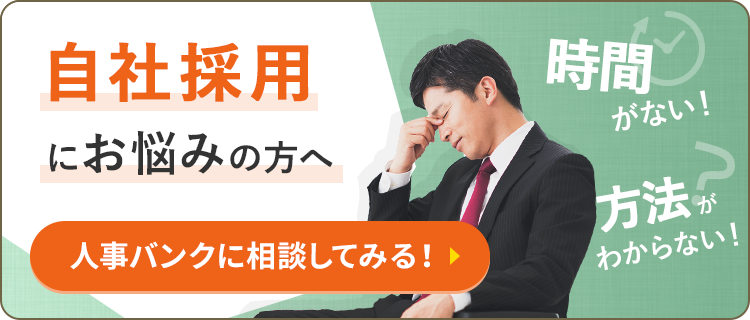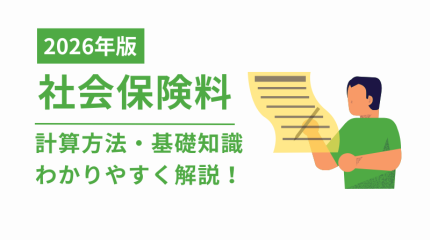パートやアルバイトで働く際によく耳にする「年収の壁」とは、収入額に応じて社会保険の加入義務や税金の負担額が変わる仕組みのことです。
一定の年収を超えると、社会保険料の負担が発生し、扶養から外れて税金が増える場合があります。
本記事では、「年収の壁」の種類やそれぞれの壁で何が起きるのかに加え、2024年からの変更点を含めて、分かりやすく解説します。
年収の壁を正しく理解し、自分に合った働き方を選ぶための参考にしてください。
あわせて読みたい
「年収の壁」とは?
年収に関する壁(103万円、106万円、130万円、150万円、201万円)の概要
|
基準となる年収 |
影響を受ける人 |
主な影響 |
2024年からの変更点 |
|
103万 |
配偶者 |
税金(所得税・住民税) |
|
|
106万 |
パート・アルバイト |
社会保険(健康保険・厚生年金) 税金(所得税・住民税) |
従業員数51人以上の企業のパート・アルバイトも対象に |
|
130万 |
配偶者(被扶養者) |
社会保険(健康保険・厚生年金) |
|
|
150万 |
親(被扶養者) |
税金(所得税・住民税) |
|
|
201万 |
子(被扶養者) |
税金(所得税・住民税) |
・103万円の壁: 配偶者の年収が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
これを超えると控除が受けられなくなり、扶養から外れ、所得税と住民税の負担が発生します。
・106万円の壁: パート・アルバイトの年収が106万円を超えると、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生します。
2024年10月からは、従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトにも適用範囲が拡大されます。
・130万円の壁: 配偶者の年収が130万円を超えると、健康保険の被扶養者から外れる可能性があります。
一定の条件を満たすと厚生年金の加入義務も発生します。
・150万円の壁: 親の年収が150万円以下であれば、扶養控除が受けられます。
これを超えると控除が受けられなくなり、所得税と住民税の負担が発生します。
・201万円の壁: 子の年収が201万円以下であれば、扶養控除が受けられます。
これを超えると控除が受けられなくなり、所得税と住民税の負担が発生します。
扶養・社会保険・税金に影響する仕組み
年収の壁では、一定の年収を超えると扶養控除が適用されなくなったり、自身で社会保険に加入する必要が生じたりするため、手取り収入が減る可能性があります。
特に社会保険の適用基準は、勤務時間や勤務先の規模によって加入義務が決まるため、同じ年収でも人によって負担額が異なります。
年収の壁は単なる収入の区切りではなく、働き方や家計に直接影響を与える要素のひとつです。自分のライフプランに合わせて、最適な働き方を選ぶことが重要です。
「130万円の壁」とは?扶養に入れる条件
「130万円の壁」とは、年収が130万円を超えると健康保険や年金の「被扶養者」から外れ、自身で社会保険に加入する必要があるため基準のことです。
会社員や公務員の配偶者の扶養に入っている人が対象であり、主にパートやアルバイトで働く人に影響があるでしょう。
年収130万円未満であることが扶養に入る条件ですが、これは「収入見込み額」で判断されるため、一時的な増減ではなく年間を通した収入が基準です。
年収130万円を超えるとどうなる?

年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自身で健康保険や年金に加入する必要があります。
その結果、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で支払うことになるため、手取り収入が減少する可能性があります。
しかし社会保険への加入は、将来受け取れる年金額が増加する、病気や怪我で働けなくなった際に傷病手当金が支給されるといったメリットもあります。
健康保険の被扶養者から外れる可能性
年収が130万円を超えると、配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、自身で健康保険に加入しなければなりません。
一般的には勤務先の健康保険組合に加入することになりますが、健康保険組合がない勤務先の場合は国民健康保険に加入する必要があります。
保険料の負担は発生しますが、健康保険に加入することで、病気や怪我をした際の医療費の自己負担を軽減できます。
厚生年金の加入義務が発生する場合
年収130万円を超え一定の条件を満たすと、厚生年金の加入義務が生じます。
具体的には、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上である場合、厚生年金への加入が必要です。
そのため、パートやアルバイトの場合でも、勤務時間や日数によっては、厚生年金に加入しなければならないケースが出てくるでしょう。
厚生年金への加入により、保険料の負担は増えますが、将来受け取る年金額が増えるというメリットがあります。
また障害年金や遺族年金といった保障も受けられるようになります。
130万円を超えても扶養に入れる条件
配偶者の年収が130万円を超えても、一定の条件を満たせば扶養に入れる場合があります。
たとえば、被扶養者の年収が130万円を超えていても、その収入が「一時的なもの」と認められる場合です。
具体的には賞与や退職金などが挙げられます。
「年収130万円の壁」を超えても扶養に入れるケース
年収130万円の壁を超えても扶養に入れるケースは、主に以下の2つです。
・一時的な収入による超過:一時的な収入(賞与、退職金、傷病手当金、出産手当金など)によって130万円を超えてしまった場合
・健康保険組合の認定基準:独自の基準を設けている企業では、年収が130万円を超えていても被扶養者として認められる場合がある
企業の健康保険組合による認定基準の違い
標準的な基準は年収130万円ですが、健康保険組合によっては、被扶養者の認定基準が異なる場合があります。
たとえば、被扶養者の年齢や世帯全体の収入状況などを考慮して、130万円を超えていても被扶養者として認めるケースです。
これは、各健康保険組合が独自の裁量を持っており、地域の物価水準や家族構成、その他の収入状況などを総合的に判断するためです。
組合の規定によっては、収入超過の理由や家族構成を考慮し、特例として扶養が認められる場合もあります。
「106万円の壁」とは?(2024年から対象範囲が拡大)
「106万円の壁」とは、社会保険加入義務に関わる基準のことです。具体的には、月収88,000円(年収約106万円)を超えると、健康保険と厚生年金保険への加入が必要になることをいいます。
2024年10月からは、従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトにもこの基準が適用され、対象範囲が拡大されました。
その結果、より多くの企業で働くパート・アルバイトが社会保険加入の対象となります。
106万円の壁を超えるとどうなるのか?
106万円の壁を超えた場合の手続きとして、社会保険加入手続きをおこなう必要があります。
社会保険料の負担が発生し、毎月の給与から差し引かれる金額が増えるということです。
一方で、その分将来受け取れる年金額が増加したり、病気やケガで働けなくなった場合に傷病手当金が支給されるなど、保障が手厚くなるというメリットもあります。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生
106万円の壁を超えた場合、パート・アルバイトでも、健康保険・厚生年金保険への社会保険適用が義務付けられます。
企業側はパート・アルバイトの社会保険加入手続きをおこない保険料を負担することとなり、従業員は給与から社会保険料が天引きされます。
保険料の金額は給与額や加入する健康保険組合によって異なりますが、一般的には給与の15%程度が目安です。
そのため、106万円を超えて働き社会保険に加入すると、手取り収入が減少する可能性があります。
保険料負担が発生するが、手取りはどれくらい変わる?
社会保険加入により健康保険料と厚生年金保険料の負担が発生し、手取り額は減少します。
たとえば月収20万円のパート・アルバイトが106万円の壁を超えて社会保険に加入した場合、健康保険料は約1万円、厚生年金保険料は約2万円となり、合計で約3万円が毎月給与から天引きされます。
つまり手取り額は17万円程度です。
加入前は社会保険料の負担がなかったため、手取りは20万円でしたが、加入後は約3万円減少することになります。
企業の対応としては、社会保険適用の対象者が増えるため、企業側の負担も増加する点を考慮する必要があります。
まとめ
特に「106万円の壁」「130万円の壁」は、社会保険の加入義務や税金の負担が関わるため事前にしっかりと理解しておくことが必要です。
2024年10月からは、106万円の壁の適用対象が広がり、より多くのパート・アルバイトが社会保険対応が求められるようになりました。
壁を超えると保険料の負担が発生する一方で、将来受け取れる年金額の増加や医療費の負担軽減といったメリットもあります。
各従業員とどのような働き方を目指しているのかしっかりと話し合うことが大切です。