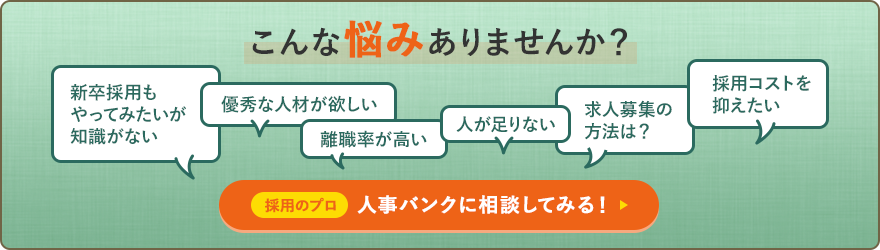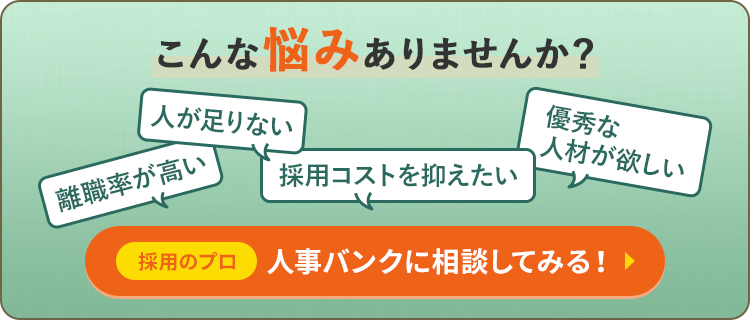ノーレイティングとは、従業員をランク付けせずに評価することです。
アメリカでは大企業を中心に導入されており、日本でも注目が高まっています。
しかし、ノーレイティングとはどのような仕組みなのか、まだわからない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ノーレイティングの概要から、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
導入方法や企業事例もあわせてご紹介するので、参考にしてください。
ノーレイティングとは
ノーレイティングは、従業員をランク付け(レイティング)しない評価制度のことを指します。
とはいえ、全く評価をしないわけではありません。
従業員ごとに設定した目標に対して上司がフィードバックを行い、その都度評価される仕組みです。
アメリカでは、2012年あたりから大手企業がノーレイティングを導入し始めました。
アクセンチュア社やマイクロソフト社を始めとする大手企業での成功事例があり、日本でも大手企業を中心に注目が集まっています。
従来型の評価制度(レイティング)との違い
従来型の評価制度である「レイティング」では、あらかじめ決められた基準や目標に対する1年間の達成率などをもとに評価します。
評価に応じて「S・A・B」のようにランク付けされ、賞与や給与、昇進などが決まる形式です。
また、ランク付けと共に上司からのフィードバックがあり、これをもとに次の目標を設定します。
一方でノーレイティングは、このようなランク付けを行いません。
リアルタイムでの目標設定と上司からのフィードバックにより、都度評価します。
そのため、レイティングよりも上司との面談回数が多く、密にコミュニケーションを取っていくことになります。
したがって、ノーレイティングは各従業員の状況をリアルタイムで把握しながら業務を進め、一人ひとりの良さを活かしていくことが可能です。
従来の評価制度
・年度目標の設定
・中間レビュー
・年次評価
・期末フィードバック
ノーレイティング
・リアルタイムの目標設定
・リアルタイムのフィードバック
・年次評価の廃止
従来型の評価制度(レイティング)の課題
従来型の評価制度(レイティング)には、
- 専門性が高い尖った人材は評価されにくい
- 従業員の成長を阻む可能性がある
- 評価のタイミングにズレが出る
- モチベーションが上がりづらい
という4つの課題があります。
専門性が高い尖った人材は評価されにくい
画一的な基準によって相対評価するレイティングでは、特定の分野に対して専門性が高い人材が評価されにくいです。
例えば、「尖っている」と表現される人材は、一般的な評価制度の枠にはまらず、結果的にランクが低くなることもあります。
自分の頑張りが評価につながらなければ、必然的に離職リスクは高まるでしょう。
従業員の成長を阻む可能性がある
レイティングでは、従業員同士の競争心を盛り上げ、相乗効果を見込めます。
とはいえ、必ずしも従業員全員が競争心をプラスのパワーにして成長できるわけではありません。
例えば、評価やランク付けを気にするあまり、本領を発揮できず納得のいく結果が出せないケースがあります。
「やってみたいことはあるけれど、失敗して評価に響くのが怖いから程々の仕事しかしない」という考えの人もいるでしょう。
また、努力と評価が直結せずにやる気をなくしてしまうこともあれば、競争心が強くなるあまり、従業員同士が攻撃的になる場合もあります。
このように、レイティングは、従業員全員の成長を見込める制度ではないことが課題の1つです。
評価のタイミングにズレが出る
レイティングは年間の実績を評価するため、現在ではなく過去を評価します。
積み重ねてきたものに対する評価はもちろん必要ですが、リアルタイムで現在の頑張りを評価してもらえない点が、レイティングの課題です。
というのも、「今まで結果につながらなかったから、現在は違う方法で努力している」という人でも、レイティングの場合「結果につながらなかった」部分しか評価されません。
特に現代ではSNSの普及により、「現在」にフォーカスする人が増えています。
レイティングで過去だけを評価すると、人によっては良くない影響を与えてしまうことがあります。
モチベーションが上がりづらい
レイティングで高いランクを獲得した人は、モチベーションが上がるため、楽しく仕事を続けられるでしょう。
しかし、レイティングではあらかじめ「どのランクに、どれくらいの人数を置くか」が決められているため、高いランクを得る人は多くありません。
そのため、大多数の人は「ほどほど」の中間的なランク付けとなります。
中間ランクに位置する人数が多いほど、ランクアップするのは難しく、長年同じランクをキープすることも多いです。
いわゆる「可もなく不可もない」と捉えられる中間的なランクになると、モチベーションは上がりにくくなります。「来年も同じくらいで良い」と考える従業員も増えるでしょう。
ノーレイティングが注目されている背景
ノーレイティングが注目されるようになったのには、
- アジャイル(俊敏)化が求められるようになったから
- 人材流動性が高まっているから
という2つの背景があります。
アジャイル(俊敏)化が求められるようになったから
IT化やグローバル化が進む近年では、企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化します。
従来のように1年ごとに目標を立てて評価していくスピード感では、到底時代の変化についていけません。
そこで求められるようになったのが、「アジャイル(俊敏)化」です。
アジャイル化とは、状況に合わせてスピード感を持って意思決定を行うことです。
目まぐるしい変化に対応するために、俊敏に対応していくことを意味します。
ノーレイティングは、1年単位ではなくリアルタイムで目標設定やフィードバックを行うため、アジャイル化の実現に欠かせません。
人材流動性が高まっているから
一昔前と違い、近年では転職が一般的化しています。
会社に対して不満があったり、もっと成長できる場所を求めたりする人は、転職してより良い環境に身を置こうとします。
そのため、企業としては、せっかく採用した人材が流出しないように工夫しなければなりません。
レイティングは、一部の人にとっては良い影響を生み出しますが、マイナスの影響を受ける人も多くいます。
そこで、さまざまな環境の人がそれぞれに合った評価を得られるノーレイティングが注目されているのです。
ノーレイティングのメリット
時代に合わせた評価制度とも言える、ノーレイティングを導入すると、
- 評価への納得感が高まる
- 従業員のモチベーションが高まる
- ダイバーシティにも対応できる
- 外部環境の変化に対応しやすくなる
- 人材確保につながる
といったメリットがあります。
それぞれの内容について、見てみましょう。
評価への納得感が高まる
ノーレイティングの特徴は、上司と密にコミュニケーションを取り、こまめな評価とフィードバックがある点です。
これにより、リアルタイムでの働きを評価・フィードバックしてもらえるため、従業員も評価に対する納得感が高くなります。
また、不明な点があればこまめに上司に確認できるので、評価について不透明な部分が少なくなる点もメリットです。
レイティングの場合、会社の業績やほかの従業員の功績が評価に影響することがあります。
自分がどんなに頑張っても、相対的な評価によってランクが上がらないこともあるでしょう。
ノーレイティングであれば、相対的な要素がなく、従業員一人ひとりを評価できるため、納得感が高くなります。
従業員のモチベーションが高まる
ノーレイティングは、従業員のモチベーションUPにもつながります。
というのも、ノーレイティングはリアルタイムでの目標設定とフィードバックを通して、今の努力を評価するからです。
レイティングのように年単位での目標設定ではないので、状況に合わせた目標修正も行えます。そのため、常に効果的な目標を立てて仕事に取り組むことも可能でしょう。
また、分からない部分はサポートしてもらえるという安心感も、モチベーションアップにつながります。
ダイバーシティにも対応できる
働き方の多様化が進む近年では、ダイバーシティに対応できる評価制度が必要です。
ノーレイティングなら、短時間勤務や在宅勤務など勤務形態が違っても、従業員それぞれの状況に合わせて柔軟に評価できます。
また、結果だけでなく、過程についての理解が深まり評価につながる点も、大きなメリットです。
「あと1歩で大きな商談がまとまるはずだったのに、先方都合で破談になった」などのケースでは、結果としてはゼロになってしまいます。しかし、ノーレイティングなら過程を検証して評価し、次につなげることもできます。
このように、ダイバーシティはもちろん、一人ひとりに寄り添った評価ができることがノーレイティングの魅力です。
外部環境の変化に対応しやすくなる
外部環境の変化によって目標達成が著しく難しくなるようなケースでも、ノーレイティングなら対応しやすいです。
ノーレイティングは年単位ではなく、こまめに1on1などを実施して上司と部下が対話するため、外部環境の変化に合わせて目標を修正できます。
これにより、従業員は仕事に打ち込みやすくなり、会社全体の生産性向上も見込めます。
人材確保につながる
ノーレイティングによって上司とのコミュニケーションが活発化することで、離職率を下げる効果も期待できます。
分からない部分はすぐに聞けて、努力をしっかりと評価してもらえる環境であれば、働きやすいと感じる人が多くなるためです。
また、コミュニケーションを取っていく中で、従業員の隠れた才能に気付き開花させられることもあるでしょう。
才能を伸ばし優秀な人材に育てることができれば、新しく採用活動を行うことなく人材を確保できる点もメリットです。
ノーレイティングのデメリット
魅力的なメリットが多いノーレイティングですが、デメリットもあります。
- 管理職の負担が増える
- 高いマネジメント能力が求められる
- 現場が混乱することもある
- 全ての企業に適した評価手法ではない
どのようなデメリットがあるのかを十分に理解した上で、ノーレイティングの良さを活かせるよう導入することが大切です。
管理職の負担が増える
レイティングの評価・フィードバックであれば年に1~2度で済みますが、ノーレイティングは都度行います。
部下との密なコミュニケーション機会が格段に増えるため、管理職の負担は増大するでしょう。
ノーレイティングを成功させるためには、上司と部下がしっかり時間を取って質の高いコミュニケーションを取る必要があります。
また、一人ひとりに合わせて評価を出す必要があるため、作業は簡単ではないこともデメリットです。
ただし、認識のすり合わせや部下をサポートする機会が増えれば、人材育成につながるため、長期的に見れば大きなリターンを期待できるでしょう。
高いマネジメント能力が求められる
ノーレイティングを行う上司には、高いマネジメント能力が求められます。
というのも、部下の悩みを聞いたり問題を解決したりする能力、一人ひとりの努力を正当に評価する能力が必要なためです。
決められた基準について評価を出すのは難しくありませんが、従業員それぞれに適切な評価を出す仕事は、誰でもできるものではありません。
したがって、ノーレイティングを導入するのなら、マネジメントやコーチングなどの研修を行い、評価する側の教育も必要です。
評価する人の能力によってノーレイティングが成功するかどうかが決まるため、まずは高いマネジメント能力を育てられる環境を整備しましょう。
現場が混乱することもある
ノーレイティングでは、目標設定が従業員ごとに異なります。
加えて、その時々の状況に応じて目標が変化するため、チームとして働く場合に混乱を招くことがあります。
そのため、従業員ごとその個人目標とは別に、チームとしての目標を掲げておくことが大切です。
また、今までとは違う評価制度に戸惑い、従業員が混乱することもあるでしょう。
ノーレイティングでは、こまめな面談でコミュニケーションを積極的に取るなど、レイティングよりも自主性が求められるため、苦手意識を持つ従業員もいるかもしれません。
このような混乱を避けるためには、従業員に対する事前の説明を丁寧に行い、少しずつ制度を浸透させていくことが大切です。
全ての企業に適した評価手法ではない
メリットが多く時代に則しているとも言えるノーレイティングですが、全ての企業に適しているわけではありません。
例えば、
- 少人数の会社でこまめなコミュニケーション、評価、フィードバックに割ける時間がない
- 外部環境の変化に対応する必要がなく、レイティングからの転換が難しい
などのケースでは、ノーレイティングが適切ではない場合もあります。
ノーレイティングが自社に適しているかどうかは、試験的に小さな部署から導入して、検証してみると良いでしょう。
ノーレイティング制度の導入方法
ここからは、ノーレイティング制度の導入方法を、手順を追ってご紹介します。
- 現状の課題分析
- 管理職への周知・研修
- 上司と部下の信頼関係構築
- 実施内容の検討・体制の構築
- 従業員への周知
- ノーレイティング制度の導入
- 評価決定権の委譲
レイティング制度からの移行では変更点も多々出てくるので、1つずつ丁寧に進めていきましょう。
現状の課題分析
自社にとって、ノーレイティングの導入が有効なのか、分析してみましょう。
現状で自社が抱える人事評価制度の課題を、従業員にヒアリングしながら洗い出していきます。
課題に対する解決策として、ノーレイティングが適切だと判断できれば導入の準備へと進みます。
管理職への周知・研修
ノーレイティングでは、評価する側である管理職の負担が大きくなります。
そこで、まずは導入することを管理職へ周知し、ノーレイティングの目的や実施方法などを丁寧に説明しましょう。
また、意識改革を含めた研修の実施も欠かせません。
ノーレイティングは今までとは全く違う評価制度となるため、評価に対する考え方はもちろん、マネジメントやコーチングなどのスキルも求められます。
評価する側である管理職の力量がノーレイティングの成功の鍵となるといっても過言ではありません。
上司と部下の信頼関係構築
上司と部下が密にコミュニケーションを取ることで成立するノーレイティングでは、信頼関係が構築されていることが大前提となります。
そこで、ノーレイティング導入に先立ち、上司と部下1on1での対話の機会を積極的に設けてみましょう。
この対話の目的は評価ではなく信頼関係の構築ですが、ここがノーレイティングの礎となります。
できるだけ時間をかけ、しっかりと土台を作っていくと良いでしょう。
実施内容の検討・体制の構築
次は、ノーレイティングをどのように実施していくのか、詳細を検討して、体制を構築するステップです。
面談の方法や場所、頻度をはじめ、移行期間や本格的な導入時期についても決定します。
このとき、表彰制度など、ノーレイティング導入で変えていかなければならない体制については、新しい体制を構築する必要があります。
一定基準による表彰を廃止する代わりに、感謝の気持ちを気軽に伝え合える体制を構築するなど、代替案を用意しておくと良いでしょう。
また、実際にノーレイティング制度を導入すると、さまざまな課題が出てくると予想されます。
そのような事態にも対応できるよう、余裕のある体制を構築しておくと安心です。
従業員への周知
ここまで準備ができたら、従業員にノーレイティングの導入を周知します。
この時のポイントは、丁寧にしっかりと説明することです。
今までのレイティングとはまったく違う制度なので、多くの従業員は戸惑うと予想されます。
従業員一人ひとりに納得してもらえるよう、導入の目的や進め方、メリットや実施方法、評価方法などを細かく説明しましょう。
ノーレイティング制度の導入
いよいよ、ノーレイティングを導入するステップです。
導入してすぐは、混乱や不具合が発生することもあるでしょう。
課題が出てくることも多いため、その都度修正しながら進めていくことが大切です。
コミュニケーションツールを使うなど、制度をスムーズに運用していく方法も検討してみましょう。
評価決定権の委譲
ノーレイティングでは、上司による評価が給与や昇進を決めることになります。
そのため、評価決定権を一部委譲する必要も出てくるでしょう。
上司と部下の信頼関係が重要となるノーレイティングでは、評価する側の上司に評価決定権があれば、従業員も納得しやすくなります。
状況を見ながら、適切に評価決定権を委譲しましょう。
ノーレイティング制度導入のポイント
ノーレイティング制度を導入して成功させるためには、
- 管理職のサポート体制を整備する
- 評価者のマネジメント能力を高める
- 給与資源に限りがあることを認識させる
の、3つのポイントを押さえておくと安心です。
管理職のサポート体制を整備する
ノーレイティングを導入すると、管理職の仕事は一気に増えます。
そこで、管理職が今抱えている仕事をサポートする体制を整備しなければなりません。
管理職がノーレイティング制度に十分対応できるサポート体制を作り、現在の仕事も問題なくこなせる環境を整えましょう。
評価者のマネジメント能力を高める
評価する側には高いマネジメント能力が求められるため、適宜研修を行います。
部下の頑張りを正しく評価し、安心して働ける環境を作るためには、上司のマネジメント能力が必要不可欠です。
- コミュニケーション力
- 分析力
- 判断力
上記をはじめ、コーチング力などもしっかりと身に付け、部下が納得できるノーレイティング制度に仕上げましょう。
給与資源に限りがあることを認識させる
ノーレイティング制度によって、上司は部下の給与に対する決定権を持つことになります。
しかし、「どこまで昇給していいのか」という上限が分からなければ、評価も出しにくいでしょう。
そこで、「給与資源がどれくらいなのか」「どこまでなら昇給可能なのか」について、評価者に伝えておくことが大切です。
また、金銭的な報酬だけでなく、貢献度の可視化や能力開発などの非金銭的な報酬も組み合わせた設計にすると、ノーレイティング制度を活かしやすくなります。
ノーレイティングを導入している企業事例
ここからは、実際にノーレイティングを導入している企業の事例を見ていきましょう。
- カルビー株式会社
- 日本マイクロソフト株式会社
- アドビ株式会社
上記3社のケースについて、それぞれご紹介します。
カルビー株式会社
カルビー株式会社では、「Commitment & Accountability (C&A 約束と結果責任)」を全従業員が締結しています。
上司と部下で決めた個人のC&A、つまり「目標」が全体へ公開され、達成具合によって賞与が出る仕組みです。
この仕組みは10年以上前から始まっており、上司と部下がしっかりコミュニケーションを取った上で目標を設定し、達成度を評価します。
また、カルビー株式会社は2020年には「バリュー評価」を導入したことでも有名です。
- 挑戦
- 好奇心
- 自発
- 利他
- 対話
の5つの項目を「バリュー」と定めていて、短期間では成果が出ない場合などでも評価しやすくなっています。
日本マイクロソフト株式会社
日本マイクロソフト株式会社では、より生産性を高めるためにノーレイティング制度を導入しています。
というのも、相対評価がベースとなる「スタック・ランキング」を採用していましたが、不健全な社内競争が生まれていたと考えられたためです。
同社ではノーレイティング制度を「コミュニケーションのバリアを取り払う」ために導入し、日常的なフィードバックの延長に人事評価があると定義づけました。
1on1ミーティングによりこまめなフィードバックが受けられ、仕事の業績だけでなく、ほかのメンバーへのサポートやチームへの貢献なども評価の対象となります。
他部門との協力関係を推奨していることも特徴で、個人の視点だけでなくチームの視点でも評価されます。
アドビ株式会社
アドビ株式会社も、レイティング制度を廃止し、独自評価制度として「Check-in(チェックイン)」を導入しています。
Check-inは、マネージャーと従業員がこまめに対話をしながら目標を決め、都度フィードバックを行う制度です。
従業員の給与や昇進に関する一定の権限をマネージャーが持っており、Check-in導入以降、定職率が高まったとされています。
Check-inを導入したことで、従来の評価制度よりもマネージャーの業務負担が軽減され、従業員の評価への納得感も向上したそうです。
「評価は日常的な対話の延長にある」との考えで導入された新しい人事評価制度によって、アドビ株式会社はより働きやすい企業になったと言えるでしょう。
まとめ
まだ日本では主流ではない「ノーレイティング」ですが、導入にはさまざまなメリットがあります。
導入する際には評価する側の教育や業務分担など、やるべきことが多々ありますが、それ以上に大きなメリットを得られるケースもあります。
働き方が多様化し、IT化やグローバル化も進む現代社会において、ノーレイティング制度の導入は優秀人材の確保や企業の生産性向上の一助となるでしょう。
全ての企業に適している評価制度ではありませんが、一度検討してみても良いかもしれません。