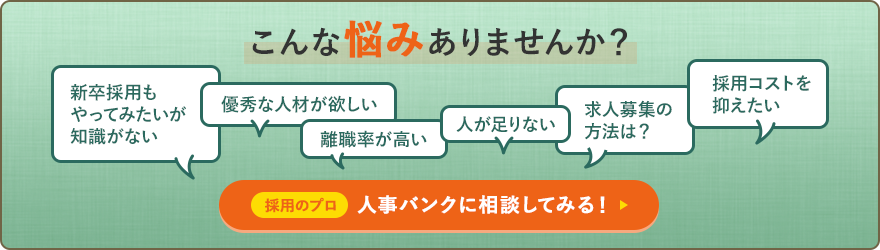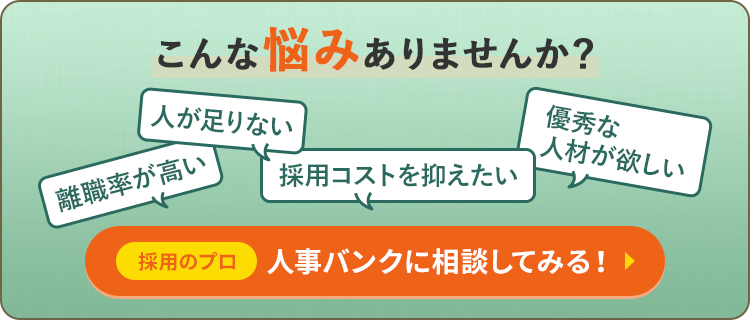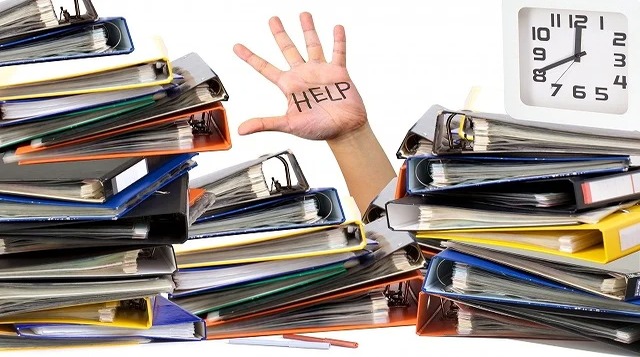
「持ち帰り残業」という言葉を聞いたことがありますか?
現在、日本では働き方改革の一環として、残業時間の削減が進められています。しかし、一方では持ち帰り残業の増加が懸念されています。
この記事では、持ち帰り残業に潜むリスクと、その対策について解説します。
「持ち帰り残業」とは?
持ち帰り残業とは、労働時間内で終わらなかった業務を時間外に自宅やカフェなどの外部で行うことです。
かつては、必要な資料や書類を風呂敷に包んで持ち帰ることから「風呂敷残業」とも呼ばれました。
現代では、パソコンやインターネットの普及により、自宅から会社のサーバーにアクセスするなどの方法が一般的です。そのため、「クラウド残業」「モバイル残業」「Eメール残業」といったさまざまな表現が使われています。
「持ち帰り残業」が増えている理由
現在、大企業をはじめとする日本中の企業において、『ノー残業デー』や『プレミアムフライデー』の導入、『オフィスの20時一斉消灯』の実施など、残業削減に向けた様々な取り組みが行われています。
しかしながら、実態として働き方の“本質”そのものは全く変わっておらず、業務量自体が減るわけではありません。
そのため、“これまでは残業をすることで、やっと仕事を仕上げることができていた”という社員からすると、会社で残業ができないとなれば自宅やカフェなど外部で残業をせざるを得なくなります。
根本的な業務削減の取り組みをしないまま“在社時間の減少”ばかりが訴えられることで、実際には業務量をカバーするために現場で業務を行う労働者が自ら「朝型勤務」や「持ち帰り残業」を行う必要に迫られているというわけです。
残業代が発生する持ち帰り残業
「社員が勝手にやっているのだから残業代は不要だ」と考えていませんか?
会社が指示した場合はもちろんですが、そうでない場合であっても残業代の支払い義務が生じることもあります。
会社や上司から指示された
上司からの指示により社員が持ち帰り残業を行った場合、労働として扱われます。
この場合、労働基準法の第37条に基づき、雇用主はその労働に対して適切な賃金を支払わなければいけません。
支払わなかった場合、労働基準法違反とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
残業時間の上限を超えたら残業代を支払っても違法
法定労働時間の1日8時間より多く働かせる場合、36協定を締結しなくてはなりません。
ただし、36協定を締結していても、残業時間の上限は月45時間・年360時間と定められています。また、特別条項付き36協定の上限は、月100時間未満・年間720時間以内などです。
よって、残業時間の上限を超えて働かせた場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
黙示の指示があった
上司の明確な指示がなくても、自宅での仕事が黙認されている場合には「違法」となる可能性があります。
たとえば、労働者が持ち帰り残業をせざるを得ない状況に陥っており、雇用主が認知しているにもかかわらず黙認していたケースです。
この場合、事実上「黙示の指示」と見なされ、残業代を支払う義務が生じます。
さらに、客観的に見て勤務時間内に処理できない仕事量を指示した場合も、「黙示の指示があった」として時間外労働の扱いとなります。
持ち帰り残業の稼働分も労働時間に含まれるため、残業代を支払わない場合は違法とみなされる可能性があるので注意が必要です。
残業代が発生しない持ち帰り残業
持ち帰り残業が違法とならないケースとして、「社員自らの判断で持ち帰り残業をした場合」や「管理職が持ち帰り残業をした場合」が挙げられます。
自主的な持ち帰り残業
社員が自身の判断で持ち帰り残業を行った場合、会社の指揮命令下にあるとはみなされず、労働時間として計算されません。
ただし、自主的な持ち帰り残業が労働者の健康やワークライフバランスに悪影響を与える可能性もあります。
決して推奨されるものではないため、持ち帰り残業を抑制する対策が求められます。
管理職の持ち帰り残業
管理職(労働基準法上の「管理監督者」に該当する人)が持ち帰り残業を行った場合、残業代は発生しません。
ただし常態化すれば、管理職自身の長時間労働や健康への悪影響など、別の問題を引き起こす可能性があります。
適切な労働環境を確保するための対策が必要です。
「持ち帰り残業」に潜むリスク
未払い賃金による訴訟リスク
持ち帰り残業には「個人の自主性」により行われる場合と、「業務上の必要に迫られて」やむを得ず発生している場合の2つのケースがあります。
後者の場合、明確な指示の有無に関わらず『黙示の業務命令』とみなされます。そのため、会社は持ち帰り残業に伴う労働時間分の賃金を支払わなくてはなりません。
事例
業務時間内には処理しきれない業務量を要求しながら、定刻に強制的に消灯。
※居残りの禁止・持ち帰り残業の強要としてみなされます。
情報漏えいのリスクが高まる
持ち帰り残業は、情報漏えいを引き起こす危険性があります。
持ち帰り残業を行う際、社員は個人のデバイスに企業のデータを転送したり、紙媒体で外に持ち出したりすることになります。
データや機密情報を社外に持ち出せば、デバイスの紛失や盗難、ネットワークウイルス感染などのリスクは高くなるでしょう。
情報漏えいやサーバー攻撃などのセキュリティトラブルが発生すれば、業務に影響が生じるだけでなく、取引先や顧客からの信頼を損ないます。
社員の健康が悪化する恐れがある
社員の心身にもさまざまな悪影響を及ぼします。
持ち帰り残業によって労働時間が長くなると心身への負担が増大し、うつや過労死といった深刻な事態に発展する可能性があるのです。
さらに、作業する環境が整っていない場所で仕事をすると、集中力や業務効率が下がるため、余計に時間がかかるでしょう。
社員のモチベーションが低下する
当然ですが、持ち帰り残業の増加は社員のモチベーション低下につながります。
持ち帰り残業が常態化すると残業前提で働くことになります。「定時までに終わらせよう」という意識が薄くなり、ダラダラと仕事をするようになるため、パフォーマンスの低下にもつながるでしょう。
また、残業代が支払われない場合、社員のモチベーションはさらに低くなり、離職リスクも高まります。
企業イメージが悪化する
持ち帰り残業に不満を抱く社員や家族が、その不満を公表することで企業イメージが悪化する可能性も考えられます。
転職掲示板やSNS、ブラック企業リストを掲載するサイトなどに、企業の実態を投稿する事例もみられます。
インターネット上に広がった情報やデータを、消したり回収したりするのは非常に難しく、会社側が反論する機会はほとんどありません。
悪い情報が広まると、採用活動に支障をきたすだけでなく、取引先の減少などに発展する可能性があります。
近年では、社員の内部告発がきっかけで倒産に至るケースも増えているので、持ち帰り残業が常態化している企業は労働環境の改善に取り組みましょう。
労働問題に発展する可能性がある
残業代を支払わないと労働問題に発展する可能性があります。
持ち帰り残業は社外で行われるものですが、事由によっては労働時間として考慮しなければいけません。
したがって、通常の残業と同様、基本的には残業代を支払う必要があります。
残業代の支払いを怠ると、賃金不払いとして従業員から訴えられる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
持ち帰り残業に関する裁判例
ここでは、2020年に起きた持ち帰り残業による訴訟についてご紹介します。
アルゴグラフィックス事件 東京地裁R2.3.25
アルゴグラフィックス事件は、月85時間を超える時間外労働に従事していた従業員が「くも膜下出血」で死亡した件で、労災民事訴訟を起こしたものです。
労働者の遺族が労災認定を受けた後、亡くなった労働者の勤務先に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償を求めました。
裁判所は、当該労働者の死亡と業務との因果関係を認め、会社の安全配慮義務違反を認めました。
被告側(雇用者)は、従業員の労働時間を把握しておらず、労働者に過重な労働を課す状況であったため、安全配慮義務違反が認定されたのです。
近年、長時間労働に対する懸念が高まり、企業の中には長時間労働の抑制を公言するところが増えています。しかし、実際にはその言葉と実践が一致しないケースも多く存在します。
このような実態に対する警告として、アルゴグラフィックス事件は重要な判例となるでしょう。
持ち帰り残業を防ぐ方法
では、具体的にどうすれば持ち帰り残業を防げるのでしょうか。
仕事量と時間を正確に把握する
持ち帰り残業は、通常の労働時間内に仕事を終えることが難しい場合に発生します。
そのため、社員の業務量と作業ペースを適切に把握することが大切です。
以下のポイントを確認してみましょう。
- 各社員が担当する業務のボリューム
- 各社員の業務スピード
上記の情報をもとに、社員に対して現実的な仕事量を適切に割り振るように心がけましょう。
これにより、通常の労働時間内で業務を遂行できるようになり、持ち帰り残業を防げます。
業務効率化を進める
社員の業務効率が低いと、通常の労働時間内に仕事を終わらせることが難しい場合があります。
したがって、担当する社員に合わせて業務プロセスを見直し、効率化の余地があるかどうかを検討することが肝要です。
業務の効率化を進めることで、社員のモチベーション向上や全体的な生産性の向上にも寄与できます。
持ち帰り残業のルールを決める
持ち帰り残業はできれば避けたい状況ですが、やむを得ない状況もあるでしょう。そのような状況に備えて、以下のようなルールを事前に設定しておくのがおすすめです。
- 持ち帰り残業が許可される条件の明確化
- 上司から許可を得るための手続きや労働時間の申告方法の設定
- 社外に持ち出してもよい資料と持ち出し禁止の資料の区別の明確化
- 使用デバイスやセキュリティ対策に関するルールの確立
これらのルールを策定して社内で共有することで、社員が持ち帰り残業に関して、より慎重な意識を持てます。
コミュニケーションを活性化させる
持ち帰り残業を減らすためには、社内コミュニケーションの活性化も大切です。
たとえば、大量の仕事を抱えたまま誰にも相談できず、持ち帰り残業で対応してしまうといった問題が発生することもあるでしょう。
そうした事態を防ぐには、専用のコミュニケーションツールの活用が有効です。
一般的なツールは以下のようなものが挙げられます。
- ビジネスチャット
- グループウェア
- オンライン会議
- 社内SNS
コミュニケーションツールにはさまざまな種類があり、備わっている機能も多くあります。ツールを有効に活用し、持ち帰り残業をなくしましょう。
持ち帰り残業を依頼する場合の注意点
持ち帰り残業には多くのリスクが伴いますが、繁忙期などには避けられないこともあるでしょう。
会社が社員に対して持ち帰り残業を指示する場合には、以下の点に留意する必要があります。
本人の同意を得る
持ち帰り残業の時間を労働時間として取り扱うことを条件として、社員の同意を得てください。
そのうえで、持ち帰り残業をする際は事前の申請方式で運用し、それに対応する賃金を支払うと良いでしょう。
強制しない
本人が同意しない場合、会社は持ち帰り残業を強制することはできません。
テレワーク(在宅勤務)などの場合を除き、私生活の場(自宅など)での労働提供契約がない限り、社員は持ち帰り残業に従う法的義務がないからです。
社員が持ち帰り残業を拒否しても「業務命令違反」とはみなされず、その拒否を理由に懲戒処分をすることもできません。
情報漏えい対策を講じる
業務上、内部資料などの情報を外部に持ち出す必要がある場合、社外での業務を前提とした適切なルールを設定することが重要です。
情報漏えいだけでなく、持ち運び中の盗難や置き忘れなどのリスクも考慮する必要があります。
具体的な情報漏えい対策の一例は以下の通りです。
- 生体認証や情報保護機能を備えたノートパソコンの利用を検討する
- 内部ファイルを暗号化する
- 情報を持ち出す際にはセキュリティが確保されたデバイスを使用する
これらの対策を実施することで、情報の漏えいや紛失のリスクを最小限に抑えられます。
まとめ
事業主にとって「労働時間の適正な把握」は義務です。
“社員が勝手にやっていることだから…”というスタンスでは、後々大きな問題を生む可能性があることを、強く認識しておく必要があります。
そのうえで、予防策として業務体制や職場環境の整備を行い、「持ち帰り残業」をさせないよう工夫しましょう。
やむを得ないケースに対応するルールを事前に作っておく、勤怠管理システムの導入を検討するなど、具体的な施策を取り入れていくことが不可欠です。