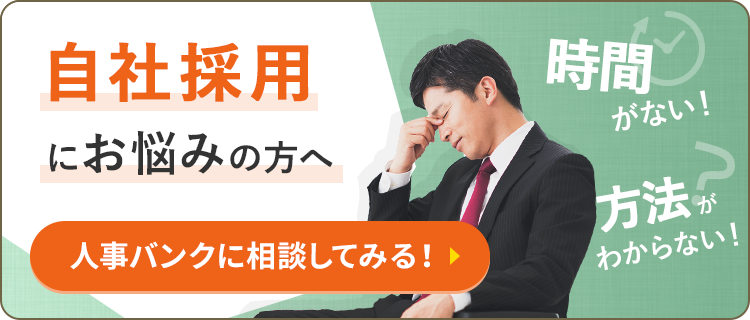「就活がきつい」と感じる学生が増える中、どのようにすれば彼らに響く採用手法を実現できるのでしょうか?
本記事では、学生に安心感を与えるためにできることや、柔軟性をもって採用活動にのぞむための具体策をご紹介します。
自分に合った企業探しや面接対策、エントリー競争などに負担を感じ、「就活がきつい」とストレスを抱える学生は少なくありません。
採用広報や選考設計の工夫、共感を前提としたコミュニケーションなど、人事担当者が知っておきたい実践的なアプローチについて解説します。
あわせて読みたい
はじめに
採用を成功させるには、学生の本音を知ることが大切です。
まずは「就活がつらい」と感じる背景や、学生の意欲を引き出す企業の姿勢をチェックしていきましょう。
学生が「就活がつらい」と感じる背景とは
就職活動に対して「つらい」と感じる学生は少なくありません。
その背景には情報量の多さによる混乱や面接・書類作成へのプレッシャー、スケジュールの過密さ、相談相手の不在など、さまざまな要因が絡んでいます。
これらは個人の問題というより、就活の構造的な負担によるものです。
企業側がその実情を理解し、配慮を示すことで、学生に選ばれる企業になることができるでしょう。
就活に前向きになってもらい、長期的に活躍する人材に
就活を「きつい」と感じる学生の多くは、やり方がわからない不安や、自分らしさが伝わらない焦りの中にいます。
こうした心理的負担を軽減できれば、学生が就活に前向きになります。また、就職に意欲的になってもらうことで、入社後の定着や活躍にもつながります。
だからこそ、採用担当者が学生の立場に立ち、寄り添う姿勢が重要です。
情報の透明化や柔軟な選考、個性を尊重する対話型の面接など、学生が「自分を受け入れてもらえた」と感じる体験は、企業への信頼やエンゲージメントを高め、長期的な活躍の土台にもなるでしょう。
学生が「きつい」と感じる5つの理由と、その対策
学生は、どのような点で「就活がきつい」と感じているのでしょうか。
学生が就活にストレスを感じる主な理由と、その不安を和らげるために企業側ができる配慮についてご紹介します。
情報過多で、就活の進め方がわからない
就活は初めての経験でありながら、企業情報や選考対策、自己分析、ES作成などやるべきことが多く、学生は「何から始めたらよいのか分からない」と迷いがちです。
さらに、ネットやSNS上には多くの情報があふれており、かえって混乱を招くケースもあります。
正解が見えにくい中で、学生は不安や孤独感を抱え、就活に対して前向きになれないことが少なくありません。
人事としてできる配慮
情報の多さに戸惑う学生に対しては、まず「選考フローの可視化」が有効です。
全体の流れや各ステップの目的を明示することで、学生は安心して就活に臨めます。
また、就活を始めたばかりの学生にもわかりやすい「初学者向けコンテンツ」の整備も効果的です。
たとえば、自己PRの考え方や業界研究の進め方を解説する動画や資料、社員からのメッセージ配信などは学生が情報を整理をする助けになります。くわえて、自分に合った企業選びをする際の助けにもなり、学生の信頼感にもつながるでしょう。
スケジュール過密で心身が疲弊する
説明会や面接、ESの提出など、就活中の学生は日々、予定に追われながら過ごすことが多くなりがちです。
特に近年はオンライン開催の機会も増え、気軽に参加できる反面、スケジュールが過密になりやすい傾向があります。
また、学業やアルバイトと並行して就活を進める学生も多く、休息の時間が取りづらくなることで心身ともに疲弊してしまうケースもあるようです。
結果として、就活そのものへのモチベーション低下を招くことがあるでしょう。
人事としてできる配慮
過密なスケジュールで疲弊している学生には、選考や説明会の日程を柔軟に設計することが大切です。
たとえば、夕方や休日にも対応することで、学業やアルバイトと両立しやすくなるでしょう。
また、録画型の会社説明会を提供すれば、自分のペースで視聴できるため負担の軽減につながります。
さらに、選考プロセスそのものも見直し、必要最小限の工程数に絞ることで、学生の心理的・時間的負担を和らげることが可能です。
効率的かつ配慮ある設計が、応募意欲の向上につながります。
ES・履歴書作成の負担が大きい
就活生にとって、エントリーシートや履歴書の作成は大きな負担となっています。
企業ごとに内容を変える必要があり、自己PRや志望動機を毎回見直す作業は消耗しやすいものです。
特に、企業研究や業界分析と並行して複数社へエントリーする学生ほど、作成にかかる時間と労力は膨大です。
手書きを求められる場合はなおさら負担が増し「書類の時点で心が折れそうになる」と感じる学生も少なくありません。
人事としてできる配慮
ESや履歴書の負担を軽減するには、OpenESなどの共通フォーマットに対応することが有効です。
一から書き直す手間が減るため、学生の心理的なハードルも下がるでしょう。
また、書類の完成度でふるいにかけるのではなく、面談や面接を通じて人柄や思考を見極める「対話重視型」の選考へとシフトすることも、学生の安心感につながります。
さらに、ES提出後に簡単なフィードバックを伝えることで、学生が次回に活かせる気づきを得られ、企業側への信頼感やエンゲージメントも高まりやすくなるでしょう。
“自分らしさ”が出せずに迷走する
就活において「自分らしさを出して」と言われても、正解が見えない中で迷い、かえって自信を失う学生は少なくありません。
企業に合わせた自己演出を重ねるうちに、本来の自分がわからなくなってしまうこともあります。
また、「評価されるための答え」を探し続けることに疲れ、就活そのものに疑問を感じるケースも
あるようです。
こうした状況は、学生のエネルギーを削ぎ、応募意欲の低下につながる要因となっています。
人事としてできる配慮
自分らしさを出せずに悩む学生に対しては、選考の中に「正解のない問い」を取り入れると効果的です。
たとえば、「あなたが大切にしている価値観は?」など、一人ひとりの考えを尊重する質問を投げかけることによって、学生が自己開示することを促します。。
また、「評価項目に個性を重視している」と明示的に発信することで、就活生に安心感を与え、主体性を引き出します。
こうした工夫は、形式にとらわれず本来の魅力を引き出す第一歩となるはずです。
キャリアのイメージがわかず、志望動機が作れない
将来の働き方やキャリアパスが具体的に思い描けず、「なぜこの会社を志望するのか」が曖昧になってしまう学生は少なくありません。
特に、初めて社会に出る新卒学生にとっては業界や職種の違いすら掴みにくく、志望動機の作成に行き詰まることがあるようです。
漠然とした不安や積み重なった違和感が、就活そのものへのモチベーション低下を招く要因のひとつとなっています。
人事としてできる配慮
キャリアのイメージが湧かず志望動機を作れない学生には、「働く姿」を具体的に伝える工夫が有効です。
たとえば、若手社員の一日の過ごし方やリアルな声をコンテンツとして可視化することで、入社後の自分を想像しやすくなります。
また、入社から数年後のキャリアステップを示す「キャリアモデル」の紹介や、実際に働く若手社員へのインタビュー記事も効果的です。
こうした情報発信は、学生が将来像を描く手がかりとなり、自発的な志望動機の形成につながるでしょう。
「就活がきつい」と感じている学生を採用するための手法は?
「就活がきつい」と感じている学生を採用するには、以下の手法が有効です。
・採用代行
・内定者フォロー
・カジュアル面談
・OB・OG訪問
・SNS広報
学生との接点を広げ、安心して選考に進める環境を整えましょう。
採用代行
採用代行(RPO)とは、企業の採用業務を外部に委託するサービスです。
学生との初期接点や日程調整、選考連絡などを代行することで、就活に負担を感じる学生にもスムーズな対応が可能になります。
企業は本来注力すべき業務に集中でき、学生一人ひとりに寄り添った柔軟な採用活動ができる点が、大きなメリットです。
内定者フォロー
内定者フォローとは、学生の内定辞退を防ぎ、入社意欲を高めるための重要な施策です。
売り手市場が続く中で、入社の決定権は学生側にあるため企業は積極的な対応が求められます。
定期的な連絡や懇親会、eラーニングの提供、社員との交流機会の創出などが、内定者の不安解消や期待感アップにつながるでしょう。
カジュアル面談
カジュアル面談は、企業と学生が選考前にリラックスして対話し、相互理解を深める場です。
履歴書不要・私服OKで合否に関係しないため、就活に不安を感じる学生も参加しやすいのが特長です。
選考のような雰囲気を避けつつ、企業の魅力や文化を伝えることで応募のきっかけづくりやミスマッチ防止につながります。
人材確保が難しい今、注目されている採用手法のひとつです。
OB・OG訪問
OB・OG訪問は、学生が企業や業界をより具体的に理解するための有効な手段です。
近年では、マイナビの「先輩発見」や「訪問予約」機能を活用し、企業が公式に訪問を受け入れるケースが増加しています。
学生は個人的なつながりに頼らず、安心して先輩社員と交流できることがメリットです。
現場のリアルな声を聞けることで志望動機形成にも役立ち、企業側もミスマッチの防止や採用への関心を高めるチャンスとなります。
SNS広報
XやInstagram、YouTubeなどのSNSを活用することで、企業の雰囲気や社員のリアルな姿を視覚的に伝えることができられます。
就活生の多くが重視する「社風」や「人柄」が伝わりやすいため、安心感を持って応募できるうえ、ミスマッチの防止にも有効です。
また、費用を抑えつつ迅速に情報発信ができる点も魅力で、応募者の増加や定着率の向上に役立つ採用広報手法として注目されています。
人事担当者として意識したい3つの視点
「就活がきつい」と感じる学生に寄り添うには、企業側の視点転換も必要です。
ここでは、人事担当者として意識すべき3つの視点を紹介します。
共感を前提とした応募者コミュニケーション
「就活がきつい」と感じる学生に対しては、共感を前提としたコミュニケーションが重要です。
緊張や不安を抱える学生に対し、一方的な評価姿勢ではなく、まず気持ちに寄り添う姿勢を持つことで信頼関係を築きやすくなります。
質問の意図を伝える、リアクションを丁寧に返すなど、小さな配慮が応募者の安心感につながるでしょう。
“わかりやすさ”と“安心感”のある情報設計
就活に不安を感じる学生にとって、情報の「わかりやすさ」と「安心感」は大きな支えとなります。
採用サイトや説明資料は、専門用語を避け、読みやすい言葉で構成することが大切です。
また、選考フローや面接内容などを具体的に示すことで、応募者が心の準備をしやすくなります。
情報を丁寧に設計すると、学生に安心してもらえる採用環境を整えられるでしょう。
選考ステップの柔軟化と可視化による心理的負担の軽減
「就活がきつい」と感じる学生には、選考過程の見通しの悪さが心理的負担となることがあります。
そこで、選考ステップの流れや日程をあらかじめ明示することが有効です。
また、オンライン面接の導入や、日程変更への柔軟な対応といった工夫も、学生の不安軽減につながります。
可視化と柔軟化の両立が、応募への一歩を後押しするはずです。
トップ人事が注目する話題は「人事バンク」でチェック!
「人事バンク」は、人事のプロのための情報サイトです。
採用や労務、研修などに関する最新ニュースに加え、理系学生の採用戦略や実務に役立つノウハウも網羅しています。
また、都道府県別データなど現場で使える独自コンテンツも充実しており、無料会員登録で限定コンテンツがすぐに利用できます。
業務に役立つ最新情報を効率よくキャッチしたい方は、メルマガ登録がおすすめです。
まとめ
就活への不安やストレスを抱える学生は、企業からの共感や丁寧な情報提供を求めています。
そうした学生に響く採用をおこなう行うには、SNSなどを活用した「人」を軸とした広報、選考プロセスの柔軟化、安心感を与えるコミュニケーション設計が欠かせません。
企業の魅力や価値観を一方的に伝えるのではなく、相手の視点に立ち「この会社でなら自分らしく働けそう」と思ってもらえる関係性づくりが、これからの採用成功の鍵となるでしょう。