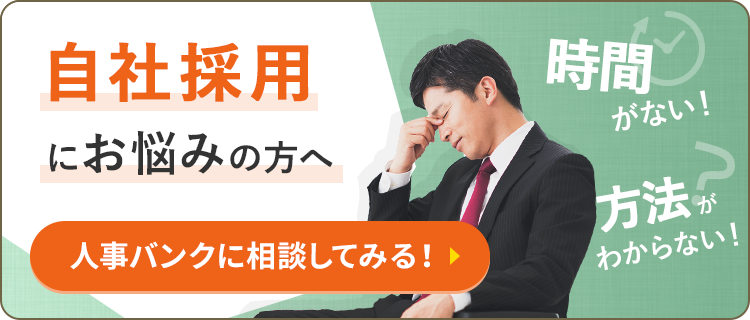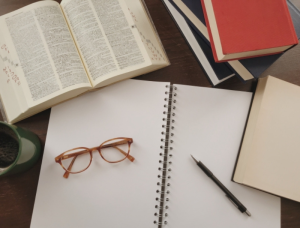
採用業務を始めたばかりの担当者にとって、専門用語の多さは大きなハードルです。
本記事では「採用計画・準備」「応募・選考プロセス」「内定・入社」「最新トレンド」まで、実務に役立つ用語をわかりやすく解説します。
基本を押さえ、効果的な採用活動に活かしましょう。
採用計画・準備
採用計画・準備は、企業の持続的な成長と人材確保の基盤となる重要なプロセスです。
戦略的な採用計画を立て、適切な準備をおこなうことで、優秀な人材を効果的に獲得し、組織の競争力を高めることができます。
採用ブランディング
採用ブランディングとは、求職者に対して「働きたい」と思ってもらえるように企業の魅力を発信する取り組みです。
優秀な人材からの応募を促進し、採用活動全体の効率を高めることを目指します。
具体的には、企業のミッション、ビジョン、バリュー、働きがいのある環境、キャリアパスを、ウェブサイト、SNS、説明会を通じて効果的に伝えます。
採用要件定義
採用要件定義とは、採用する人材に求める能力、経験、スキル、人物像を明確に定義することです。
たとえば、企業が「新しい市場に進出するために、〇〇の経験を持つ営業担当者」を求めている場合、その経験内容、語学力、異文化理解力を詳細に定義します。
職務内容、必要なスキル・経験、求める人物像を整理することで、採用のミスマッチを防げます。
要件があいまいなまま進めると「応募はあるが欲しい人材が来ない」「入社後に不適合が発覚する」といった問題が起こりえます。
そのため、経営戦略や事業計画に基づき、部署やポジションごとに必要な要素を具体的に洗い出すことが重要です。
応募者側も自身のスキルや経験が求める要件に合致するかを判断しやすくなり、結果的に企業側はより質の高い応募者を集めやすくなります。
カルチャーフィット
カルチャーフィットとは、候補者が企業文化や価値観にどの程度適応できるかを指す概念です。
スキルが高くても、価値観が大きくずれると早期離職のリスクが高まります。
そのため面接時にはスキルだけでなく「理念への共感」や「チームとの相性」も見極めることが重要です。
面接やアセスメントを通じて、候補者の価値観や行動特性を深く理解することが求められます。
ジョブディスクリプション(JD)
ジョブディスクリプション(職務記述書)とは、特定の職務における業務内容、責任範囲、必要なスキルや経験などを明確に記載した文書です。
ジョブ型雇用の普及に伴い、採用や人事評価の基準として注目されています。
候補者は自身の経験やスキルが募集要件に合致するかを具体的に判断することに利用でき、企業側は求める人物像とのマッチ度が高い候補者を集めやすくなります。
母集団形成
母集団形成とは、採用したい人材層の中から、自社に興味を持ち、応募してくる可能性のある候補者群(母集団)を、採用活動を通じて意図的に作り出すプロセスです。
採用成功のためには、まず十分な数の候補者を集めることが不可欠です。
具体的には、求人広告や人材紹介、SNSに加え、リファラル採用など複数チャネルを組み合わせ、幅広い候補者を集めることがポイントです。
質の高い母集団を形成できれば、優秀な人材の確保につながります。
労働市場(人材市場)
労働市場(人材市場)とは、求職者と求人企業が労働力を取引する市場のことです。
労働市場の動向を理解することは、採用戦略を立てるうえで非常に重要です。
求職者の需要と供給のバランス、特定の職種におけるスキル保有者の数、給与水準を把握することで、より現実的で効果的な採用計画を立案することができます。
労働市場は、景気や業界動向によって採用難易度は大きく変動します。
たとえばエンジニア職は慢性的に人材不足が続いており、採用競争が激しいのが特徴です。市場動向を理解することで、現実的な採用戦略を立てられるようになります。
ペルソナ
ペルソナとは、採用活動において、自社が求める理想的な人材像を具体的に設定した架空の人物像のことです。
「30代男性」といった属性だけでなく、氏名、年齢、性別、現職の職種や役職、年収、家族構成、さらには価値観、仕事に対する考え方、キャリア志向、趣味・嗜好といった、詳細なプロフィールを設定します。
ペルソナを決めることでターゲットとなる求職者像が明確になり、より効果的な採用メッセージやチャネル選定ができます。
トライアル雇用
トライアル雇用は、採用前に一定期間、候補者に実際に就業してもらうことで、お互いの適性を見極める雇用形態です。
未経験人材や異業種からの転職者の採用で活用されます。
通年採用やポテンシャル採用と並び、長期的な採用戦略を考えるうえで有効な選択肢です。
「採用リスクを下げつつ、候補者にも実際の職場を体験してもらえる」点で双方にメリットがあります。
通年採用
通年採用とは、従来の決まった時期(新卒採用における春など)だけでなく、年間を通して継続的に採用活動をおこなうことです。
人材が求めるタイミングや、近年では企業の募集ニーズが多様化しているため、通年採用は長期的な採用計画を立てるうえで有効な手段でしょう。
たとえば、欠員補充や急な事業拡大に対応しやすくなるほか、特定のスキルを持つ即戦力人材を、時期を問わず獲得できるチャンスが広がります。
また、新卒採用においても、早期選考や秋採用を実施することで、優秀な学生を逃さず採用できる可能性があります。
ポテンシャル採用
ポテンシャル採用とは、現時点でのスキルや経験よりも、将来性や成長可能性(ポテンシャル)を重視した採用手法です。
専門的なスキルや経験がまだ十分でない若手社員や第二新卒、未経験者を対象とする場合に有効です。
ポテンシャル採用では、候補者の学習意欲、適応力、課題解決能力、コミュニケーション能力に加え、自社で活躍したいという意欲を、面接や適性検査を通じて見極めます。
この採用手法は、長期的な視点で組織を強化したい場合や、将来の幹部候補を育成したい場合に適しています。
若者雇用促進法
若者雇用促進法(正式名称:青少年の雇用の促進等に関する法律)は、若者の職業生活における活躍を促進し、雇用の安定を図ることを目的に2016年に制定された法律です。
この法律では、企業に対して、若者の採用・育成に積極的な企業を「ユースエール認定企業」として認定する制度や、ハローワークにおける若者向けの職業相談・職業紹介の強化が定められています。
企業側は、自社が若者の採用・育成にどのように取り組むべきか、どのような支援制度が利用できるのかを理解しておくことが重要です。
たとえば、職場体験の機会提供、インターンシップの実施、キャリアコンサルティングの導入、ハラスメントのない働きやすい職場環境の整備が挙げられます。
採用手法
採用手法とは、企業が求める人材を獲得するために用いるさまざまなアプローチや手段のことです。
手法は多岐にわたり、ターゲットとする人材層や採用したいポジション、予算、時期に応じて、複数の手法を組み合わせることが一般的です。
求人広告(オーガニック求人/有料求人広告)
求人広告は、候補者に自社の採用情報を届ける代表的な手段です。
オーガニック求人は、自社HPや無料求人サイト、SNSを活用して自然流入を狙う方法で、費用を抑えながら企業独自の魅力を発信できます。
一方、有料求人広告は求人媒体や検索連動広告に出稿し、短期間で多くの応募を集めやすいのが特徴です。
採用計画に応じて両者を組み合わせることで、効率的に母集団形成ができます。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、求人広告に応募が来るのを待つのではなく、企業側から積極的に候補者へアプローチする採用手法です。
具体的には、転職サイトやSNS、スカウトサービスを活用して、登録者の経歴やスキルを確認したうえでスカウトメールを送ったり、LinkedInで直接コンタクトを取ります。
メリットは「欲しい人材」にピンポイントでアプローチできる点です。
一方、候補者へのアプローチ文面や対応スピードによって成果が大きく変わるため、人事担当者には営業的なコミュニケーションスキルが求められます。
タレントプール
タレントプールとは、自社に興味を示した人材や過去に応募・選考した人材、将来的に採用したいと考えられる人材の情報を蓄積しておくデータベースのことです。
「今回は採用に至らなかったが、将来的にマッチしそうな人」「イベントやSNSで接点を持った人」を記録しておくことで、次回以降の採用活動に活かせます。
ダイレクトリクルーティングをおこなう際には、このタレントプールを“送り先”にすることができます。
そのため、今すぐダイレクトリクルーティングを実施していなくても、将来を見据えてタレントプールを作成しておくことが重要です。
タレントプールを作成しておくことで、欠員補充や新規事業立ち上げの際にも、ゼロから候補者を探す手間が省けます。
また、候補者との継続的な関係構築(コミュニケーション)をおこなうことで、企業へのエンゲージメントを高め、採用確率も向上させることができるでしょう。
リファラル採用
リファラル採用とは、自社の従業員からの紹介を通じて人材を採用する手法です。
既存社員が推薦するため、企業文化や仕事内容にマッチする人材を獲得しやすく、定着率も高い傾向があります。
採用コストを抑えつつ、信頼性のある人材に出会えるのもメリットです。
一方、紹介に偏りが生じやすいため、他の採用手法と併用して活用することが効果的です。
アルムナイ採用
アルムナイ採用とは、過去に自社を退職した元従業員(アルムナイ)に、再び入社を促す採用手法です。
かつて在籍していた経験があるため、企業文化や業務内容を理解しており、再入社後もスムーズに即戦力になるのが大きな特徴です。
また、外部で培った新たな知識や人脈を持ち帰ってくれることで、組織に新しい風をもたらす効果も期待できます。
アルムナイ採用のために、退職後も元従業員と定期的に情報交換をおこなったり、イベントを開催したりすることで、退職した従業員と良好な関係を築くことができます。
いざという時に「戻りたい」と思ってもらえるような企業ブランドを維持することが大切です。
エージェント(人材紹介会社)
エージェントとは、求人企業と転職希望者をつなぐ人材紹介会社のことです。
企業側が、求める人物像や条件をエージェントに伝えると、登録者の中から適した候補者を紹介してもらえます。
一般的には採用が決定した場合に成功報酬を支払う仕組みで、短期間で即戦力人材を確保できるのがメリットです。
人材紹介会社は、独自のデータベースや広範なネットワークを持っているため、自社だけではリーチしにくい優秀な人材や、特定のスキルを持つ専門職人材を発掘できるのが強みです。
RPO(採用代行)
RPO(Recruitment Process Outsourcing/採用代行)とは、企業の採用活動を外部の専門業者に委託する仕組みです。
求人広告の作成・掲載、候補者のスクリーニング(書類選考)、面接日程の調整、面接の実施、入社手続きのサポートなどさまざまな業務をアウトソースできます。
RPOのメリットは、採用業務の効率化と質向上です。
専門知識を持ったRPOにより、採用担当者の負担を大幅に軽減し、コア業務である戦略立案や最終的な意思決定に集中できるようになります。
また、採用ノウハウや最新の採用手法を活用することで、より質の高い候補者を見つけ、採用ミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
採用業務が煩雑でリソースが不足している企業、採用プロセスを標準化・効率化したい企業にとって、有効な選択肢でしょう。
スクラム採用
スクラム採用とは、人事部に加え現場社員や経営陣らが協力し合い、チーム全体で進める採用手法です。
従来の「人事が主導して現場に引き渡す」という流れではなく、求人要件の策定から候補者との面接、入社後のオンボーディングまでを関係者全員で担うのが特徴です。
メリットは、現場のリアルな声を反映した採用ができることです。
また、社員全員が「採用は自分ごと」という意識を持つことで、組織全体の採用力を高める効果も期待できます。特にスタートアップや成長企業で導入が進んでいます。
Instagram採用
Instagram採用とは、Instagramを活用して候補者との接点をつくり、自社の魅力を発信して採用につなげる手法です。
写真や動画を通じて職場の雰囲気や社員の働き方をリアルに伝えられるため、求人広告だけでは伝わりにくいカルチャーや価値観を効果的にアピールできます。
Instagramでは、ハッシュタグ検索やストーリーズの活用により、潜在的な求職者や若年層へのリーチができます。
Z世代やミレニアル世代はInstagramで企業情報を収集する傾向が強いため、採用広報の一環として取り組む企業が増えています。
インフルエンサー採用
インフルエンサー採用とは、SNSで影響力を持つインフルエンサーを通じて自社の魅力を発信し、採用活動に活かす手法です。
企業アカウントだけでは届きにくい層にもリーチでき、候補者にリアルで親近感のある情報を届けられるのが特徴です。
求人広告では伝わりにくいカルチャーや雰囲気を自然に伝えられます。
オウンドメディアリクルーティング
オウンドメディアリクルーティングとは、自社が運営するオウンドメディア(採用サイト、コーポレートサイト、noteやブログ)を通じて、候補者に向けて魅力を発信し、採用につなげる手法です。
求人票だけでは伝えきれない「社員の声」「働き方」「企業カルチャー」を記事や動画で発信することで、応募前から候補者の理解や共感を得られる点が大きな特徴です。
検索エンジンからの流入も見込めるため、求人広告に依存せず中長期的に母集団を形成できるメリットもあります。
さらに、自社コンテンツはストック資産となり、発信を続けるほど採用広報の効果が高まります。企業の採用ブランディングとしても強化しながら、自社にマッチする人材の獲得につなげられるでしょう。
採用マーケティング
採用マーケティングとは、求職者に「選ばれる企業」として認知され、応募につなげるための一連の取り組みを指します。
求人広告や人材紹介に依存した採用活動とは異なり、企業ブランディング・情報発信・広告運用・データ分析を組み合わせておこなうのが特徴です。
エンプロイヤーブランディング(採用ブランディング)
エンプロイヤーブランディング(採用ブランディング)とは、企業が「どのような人材に、どのようにアプローチしたいか」を明確にし、求職者に対して自社の魅力を効果的に伝えるための戦略です。
求人情報を掲載するだけでなく、企業の独自価値、文化、働く環境を、一貫性のあるメッセージで発信し、ターゲットの認知度と好意度を高めていく活動全般を指します。
具体的には、企業の理念やビジョン、社会的なミッション、働く環境の魅力、キャリアパスをWebサイトやSNS、説明会を通じて発信します。
エンプロイヤーブランディングは採用活動に限らず、既存社員のエンゲージメント向上にも寄与します。社員が「自分の会社を誇れる」と感じることで、自然に外部へポジティブな情報が拡散され、採用力の強化につながるでしょう。
Indeed
Indeedは、世界最大級の求人検索エンジンであり、求人広告の定番媒体として日本国内でも幅広く活用されています。
従来の求人媒体が、応募課金型・掲載枠課金型であるのに対し、Indeedは検索エンジン型の仕組みを採用しています。
そのため、求職者はキーワードや勤務地を自由に検索し、自分に合った求人を効率的に探すことができます。
企業にとっては、潜在的な候補者を含む幅広い層にリーチできるのが大きなメリットです。
Indeedの利用方法は大きく2つに分けられます。
1つ目は、無料で自社採用ページや求人情報を掲載できる「オーガニック枠」、2つ目は、広告費を投下して露出を強化する「スポンサー枠(有料広告)」です。
スポンサー枠ではクリック課金型(CPC)が採用されており、予算やターゲティングを調整しながら効率的に応募者を集めることが可能です。
そのため、少ない予算でも工夫次第で成果を出せる点が特徴です。
また、Indeedは応募数だけでなく、応募単価(CPA)やクリック単価(CPC)といった数値を可視化できるため、採用マーケティングの改善サイクルを回しやすいのも強みです。
CPC(クリック単価)
CPC(Cost Per Click/クリック単価)とは、求人広告がクリックされるごとに発生する広告費用のことをいいます。
Indeedや求人検索エンジン、SNS広告で採用マーケティングをおこなう際に用いられる重要な指標です。
従来の掲載課金型の求人広告では、期間中にどれだけクリックされても固定費用がかかる仕組みでしたが、CPC型はクリックされなければ課金されないため、無駄なコストを抑えつつ効率的に応募者へリーチできるのが特徴です。
CPCは、適切にコントロールすることで、採用コストの最適化が図れます。
たとえば、人気職種や都市部ではクリック単価が高騰しやすく、逆にニッチ職種や地方では低めに設定できます。
そのため、ターゲットとなる候補者層に合わせて入札額を調整したり、広告文やキーワードを改善することが重要です。
CPA(応募単価)
CPA(Cost Per Application/応募単価)とは、1件の応募を獲得するためにかかった広告費用を指す指標です。
たとえば、求人広告に10万円を投じて20件の応募があった場合、CPAは5,000円となります。
採用マーケティングにおいては、CPC(クリック単価)の次に重視すべき指標であり、実際の応募獲得効率を測る目安になります。
応募・選考プロセス
応募から内定までの流れを設計するのが「選考プロセス」です。選考では、公正性・一貫性を保ちながら、候補者の適性やスキルを多面的に見極めることが重要です。
書類選考
書類選考とは、応募者が提出した履歴書や職務経歴書を基に、採用要件に合致しているかを判断する最初のステップを指します。
評価ポイントは、経験やスキル、応募動機です。
書類だけでは人物像を正確に把握できないため、あくまで「面接に進む候補者を見極めるためのフィルター」として位置づけることが重要です。
構造化面接
構造化面接とは、事前に決められた質問内容と評価基準に基づいておこなう面接手法のことです。
従来の面接では、面接官ごとの経験や主観に左右されやすく、評価のばらつきが課題とされてきました。これに対して構造化面接では、すべての候補者に同じ質問を投げかけ、あらかじめ用意した基準で採点するため、公平性と客観性を確保しやすいのが特徴です。
構造化面接を導入することで、候補者の能力や行動特性を比較しやすくなり、採用のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。
さらに、複数の面接官が同じ評価基準を用いることで、組織として一貫した判断が可能になり、採用の透明性向上にもつながります。
適性検査(アセスメント)
適性検査(アセスメント)とは、候補者の能力や性格、価値観を客観的に測定する評価手法です。
代表的なものには、言語・数的処理の基礎学力を測る能力検査に加え、論理的思考や判断力を確認する問題解決テスト、性格特性や行動傾向を把握する性格診断があります。
これらを組み合わせることで、応募書類や面接だけでは見抜きにくい候補者の強みや課題を多面的に把握することができ、長期的に活躍できる人材を見極めやすくなります。
ただし、適性検査は「合否」に直結するものではありません。
面接や職務経歴と組み合わせて総合的に判断することが重要です。
内定・入社
内定・入社は、採用活動のゴールとなる最終フェーズです。候補者に内定を提示し、条件や入社後のイメージを共有することで、入社意欲を高め定着につなげます。
オファー面談をはじめとした丁寧なコミュニケーションが欠かせず、入社までの不安を取り除くサポートが重要です。
オファー面談
オファー面談とは、候補者に対して内定の条件や待遇を正式に提示し、入社への最終的な意思確認をおこなう場のことで、給与や勤務条件だけでなく、入社後のキャリアパスや働き方の具体像を共有することで、候補者の不安を解消し、納得感を高める役割もあります。
面談の進め方次第で、内定辞退率を大きく左右するため、企業にとって重要なプロセスです。
オファー面談では、一方的に条件を伝えるだけでなく、候補者の希望や不安を丁寧にヒアリングし、相互理解を深めることが成功のポイントです。
教育・研修
教育・研修は、新入社員が早期に組織へ適応し、力を発揮できるように支援するためのプロセスです。
オンボーディングやOJT、メンター制度があり、業務知識やスキルの習得を促すだけでなく、職場文化や価値観への理解を深める役割もあります。
オンボーディング
オンボーディングとは、新入社員が入社後スムーズに組織へと適応し、早期に活躍できるよう支援するプロセスを指します。
初期研修やオリエンテーションにとどまらず、業務知識の習得、社内制度の理解、チームメンバーとの関係構築までを含む包括的な取り組みです。
オンボーディングをおこなうことで、早期離職の防止や定着率の向上、社員のエンゲージメント強化につながります。
近年では、マニュアルや研修プログラムの整備に加え、オンラインツールやメンター制度と組み合わせるケースも増えており、企業文化を浸透させる重要な手段として注目されています。
OJT
OJT(On the Job Training)とは、実際の業務を通じて上司や先輩社員が新入社員に指導をおこなう育成方法です。
座学研修とは異なり、現場での実務を経験しながら知識やスキルを身につけられるため、即戦力化につながりやすいのが特徴です。
OJTでは、業務を任せるだけでなく、進め方の説明やフィードバックもおこないます。
目標を設定し、段階的に業務範囲を広げるため、着実に成長できます。
メンター制度
メンター制度とは、新入社員や若手社員にメンターと呼ばれる先輩社員がつき、日常的なサポートをおこなう制度です。
仕事の進め方やキャリア形成に関するアドバイスはもちろん、職場での人間関係や悩みごとを相談できる存在として、新入社員をサポートします。
OJTが業務遂行に直結した指導であるのに対し、メンター制度は心理的支援やキャリア支援の側面が強い点が特徴です。
労務関連
労務関連の知識は、人事担当者が採用から入社後の雇用管理まで適切に対応するために欠かせません。
勤務形態や労働時間制度、雇用契約に関する基本事項を理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、社員が安心して働ける環境を整えることができます。
フレックスタイム
フレックスタイムとは、社員が一定の範囲内で始業・終業時刻を自由に選べる働き方の制度です。
1日の中で必ず勤務すべき「コアタイム」と、自由に出退勤を決められる「フレキシブルタイム」を組み合わせるのが一般的です。
これにより、通勤ラッシュの回避や家庭の事情に合わせた柔軟な働き方が可能となり、ワークライフバランスの改善や生産性向上につながります。
裁量労働制
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。
業務の進め方や時間配分を社員の裁量に委ねることができるため、研究開発職や企画職など、成果に至るプロセスを一律に管理しにくい職種で多く採用されています。
社員にとっては自分のリズムで働ける自由度が高い一方、企業側は長時間労働の温床とならないよう、労使協定の締結や労働基準監督署への届出といった法的手続きを適切におこない、労務管理を徹底することが不可欠です。
試用期間
試用期間とは、新しく採用した社員に対して、本採用前に一定期間設けた試し雇用期間のことです。
一般的には3〜6か月程度が多く、業務への適性や勤務態度、社風への適応力などを見極めます。
企業にとっては採用のミスマッチを防ぐ手段となり、社員にとっても実際の仕事内容や職場環境を理解する機会です。
有効求人倍率
有効求人倍率とは、求職者1人に対してどれだけの求人があるかを示す指標で、厚生労働省が毎月発表しています。
計算方法は「有効求人数 ÷ 有効求職者数」で、数値が1を上回れば求人数の方が多く、人材不足の状況を意味します。
逆に1を下回れば、求職者が多く就職が難しい状況といえます。業種や地域ごとによって差はあり、特に医療・福祉や建設、ITエンジニア職は常に高い傾向です。
その他
採用や人事に関わる用語は、時代の変化に応じて新しく生まれた概念やシステムも数多く存在します。
ジョブ型雇用やリスキリングのように働き方や人材育成の潮流を示す言葉から、ATS(採用代行システム)やHRテックのようにテクノロジーを活用した仕組みが近年では注目されています。
ジョブ型雇用
ジョブ型雇用とは、あらかじめ明確に定義された「職務(ジョブ)」に基づいて人材を採用・配置する雇用形態のことをいいます。
従来の日本型雇用である「メンバーシップ型雇用」が、職務を限定せず長期的な育成や配置転換を前提としているのに対し、ジョブ型は職務内容・責任範囲・成果基準が明確に決められているのが特徴です。
この仕組みでは、募集時にジョブディスクリプション(職務記述書)を提示し、候補者は自らのスキルや経験が要件に合致しているかを確認したうえで応募します。
そのため、採用の透明性が高まり、即戦力人材を確保しやすいのが特徴です。また、国際的には一般的な雇用形態であり、グローバル企業との競争や人材流動化が進む中で、日本でも導入を検討する企業が増えています。
ATS
ATS(Applicant Tracking System)とは、採用管理システムのことです。
求人の公開から応募者管理、選考プロセスの進捗確認まで一元化できるツールで、人事担当者の業務効率を大幅に改善する役割を果たします。
従来はExcelやメールで個別に管理していた応募者情報を一括で扱えるため、重複や漏れを防ぎ、選考のスピードと精度を高められるのが特徴です。
ATSは、求人媒体や自社採用サイトと連携できるものも多く、複数チャネルからの応募を一括管理できる点も強みです。
さらに、レポート機能により応募数・通過率・内定率のデータを可視化し、採用マーケティングの改善に役立てられます。
近年はクラウド型サービスが主流となり、中小企業でも導入しやすくなっています。
HRテック
HRテックとは、「Human Resources(人事)× Technology(技術)」の略語で、人事業務にテクノロジーを活用する仕組みやサービスを指します。
採用管理、勤怠管理、人事評価、タレントマネジメントといった幅広い領域で利用されており、AIやクラウド、データ分析を取り入れることで、従来は属人的だった人事業務を効率化・高度化できるのが特徴です。
ATS(採用管理システム)や適性検査ツール、スカウトサービスがHRテックの代表例です。
AI採用
AI採用とは、人工知能(AI)を活用して採用活動を効率化・高度化する手法を指します。
具体的には、応募者の書類スクリーニング、適性検査の自動分析、面接での表情や発話内容の解析など、幅広い領域で導入が進んでいます。
AIを用いることで、人事担当者の負担を軽減し、短時間で多くの候補者を公平に評価できる点が大きなメリットです。
しかし、AI採用はあくまで「人の判断を支援するツール」として活用することが重要で、データと人間の目を組み合わせることで、より質の高い採用活動を実現できます。
DX人材
DX人材とは、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するために必要な知識やスキルを持つ人材を指します。
ITスキルに長けているだけでなく、データ活用やシステム導入を通じて業務プロセスを変革し、ビジネスモデルの進化を実現できる点が特徴です。
代表的なDX人材には、エンジニアやデータサイエンティストに加え、プロジェクト全体をマネジメントできる人材も含まれます。
近年は多くの企業でDX推進が経営課題となっているため、DX人材の獲得競争が激化しています。
リスキリング
リスキリングとは、技術革新や市場環境の変化に対応するために、社員がスキルを学び直すことを指します。
AIやDXの普及により、従来の業務が自動化・効率化される一方で、新しい業務や役割が求められるようになったため、その需要が高まってきました。
代表的なリスキリングでは、データ分析やプログラミング、デジタルマーケティングが挙げられます。
社員にとってはキャリアの可能性を広げる機会となり、企業側にとっては競争力強化や人材不足解消につながります。
ジョブカフェ
ジョブカフェとは、若年層の就職支援を目的に各都道府県が設置している無料の就業支援施設です。
15歳から概ね39歳までの求職者を対象に、キャリアカウンセリング、職業適性診断、求人紹介、セミナー開催など幅広いサービスを提供しています。
ハローワークや教育機関、企業と連携し、若者が安心してキャリアを築けるよう支援するのが特徴です。
利用者は就職活動のノウハウを学べるだけでなく、企業とのマッチングイベントやインターンシップを通じて実際の働き方を体験する機会もあります。
HRBP
HRBP(Human Resources Business Partner)とは、人事が単なる管理部門ではなく、経営や事業部門の戦略パートナーとして機能する役割を指します。
従来の人事が担ってきた労務管理や採用・研修の運用業務に加え、事業目標を達成するために必要な人材戦略を立案・推進する点が特徴です。
具体的には、事業部門の課題を理解したうえで、人員配置、組織開発、評価制度の設計をおこない、経営と現場の橋渡し役を担います。
HRBPによって、事業は部門の垣根を越えた実効性の高いものになります。
近年ではグローバル企業を中心に普及が進んでおり、日本でも「戦略人事」を実現する重要な役割として注目されています。
嫁ブロック・夫ブロック
嫁ブロック・夫ブロックとは、本人が内定を得ても、配偶者の反対によって入社を断念してしまう現象のことを指します。
家庭を持つ求職者の場合、転職は収入や勤務時間、勤務地の変化を伴うため、家族の理解が欠かせません。
配偶者から「安定性に不安がある」「労働条件が合わない」の理由で反対され、結果として内定辞退につながるケースが少なくありません。
企業にとっては貴重な人材を逃す要因となるため、候補者本人だけでなく家族にも安心感を与える工夫が必要です。
具体的には、福利厚生や働き方の柔軟性、キャリアパスの展望を丁寧に説明し、候補者が配偶者へ説明しやすい情報を提供することが効果的です。
まとめ
本記事では、採用担当者が押さえておくべき人事用語を幅広く解説しました。
人材獲得競争が激化する中で、用語の意味を理解し、自社の採用戦略にどう活かすかを考えることが重要です。本記事を参考に、自社に合った採用体制を整え、長期的に活躍できる人材の確保と育成につなげてみてはいかがでしょうか。