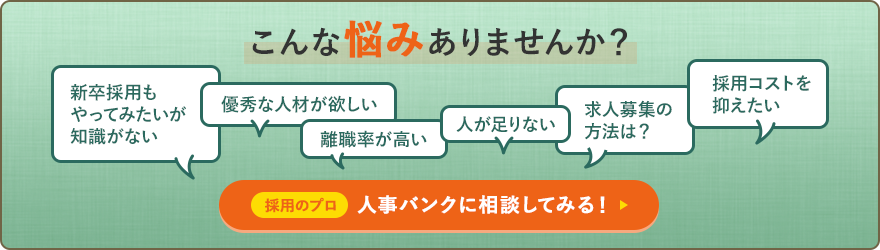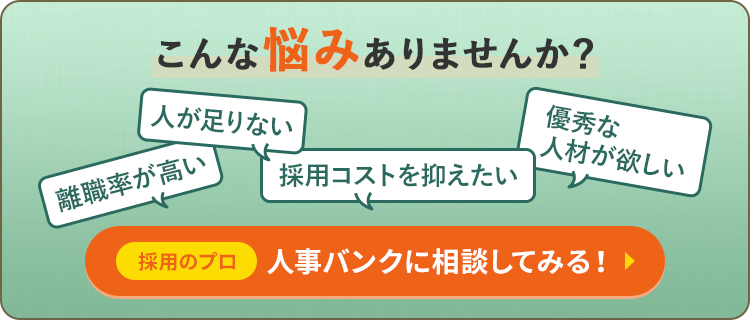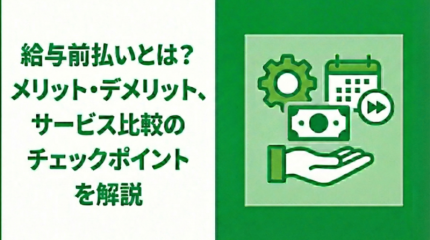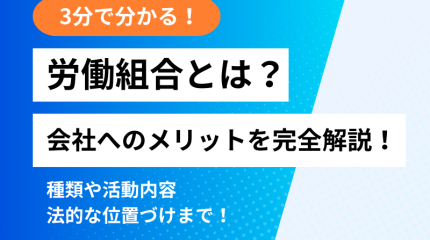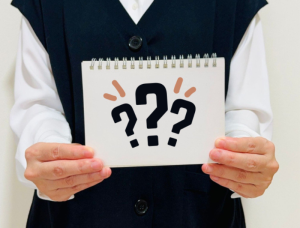
2025年10月より、従業員のリスキリング(学び直し)を推進する新たな公的支援制度「教育訓練休暇給付金」がスタートしました。
この制度は、従業員がスキルアップのために長期の無給休暇を取得する際、その間の生活費を国が一部支援するものです。
企業の人事・労務担当者の皆様にとって、本制度は従業員の能力開発を促進し、企業の持続的な成長を実現するための重要なツールとなるでしょう。
本記事では、この教育訓練休暇給付金の目的、対象となる従業員や休暇の条件、支給される給付金の金額と期間、さらには対象となる教育訓練の範囲まで、制度の全貌をわかりやすく解説します。
また、企業が制度を導入・活用するうえで不可欠な就業規則の改定ポイントや、従業員への効果的な周知方法、そして人材戦略への組み込み方についても深掘りします。
人事担当者の皆様が、本制度を深く理解し、自社の人材戦略に戦略的に活かすための具体的なガイドとして、活用の一助となりますと幸いです。
受け取れる給付金を調べるなら
【2025年10月新設】教育訓練休暇給付金とは?
教育訓練休暇給付金は、2025年10月から新たに始まった制度で、労働者が自身のキャリアアップやスキル習得のために、会社を30日以上休職して教育訓練を受ける際、その間の生活を支援するために給付金が支給されるものです。
これは単なる福利厚生としての休暇制度ではなく、政府が推進する「リスキリング(学び直し)」を推進するための重要な施策として位置づけられています。
労働者にとっては、経済的な不安を軽減しながら、主体的に学び、自身の市場価値を高める機会となるでしょう。
この制度は、変化の激しい現代において、従業員が新たな知識やスキルを習得し、キャリアを自律的に築いていくことを支援するものです。
企業側から見ても、従業員の自発的な学びを促進することで、組織全体の生産性向上や競争力強化につながり、持続的な成長を実現するための重要な投資と捉えることができます。
まさに、個人のキャリア形成と企業の成長戦略が結びつく、現代の人材育成に不可欠な制度といえるでしょう。
制度の概要を3つのポイントにしてご紹介
教育訓練休暇給付金制度の概要を、特に重要な3つのポイントに絞ってご紹介します。
まず1つ目のポイントは、この制度が「30日以上の無給休暇」を対象としている点です。
従業員が長期の教育訓練を受ける際、会社から給与が支払われない無給の状態が続くと、生活費の心配から学びを諦めてしまうケースも少なくありません。
この制度は、そうした経済的な懸念を解消し、安心して訓練に集中できる環境を提供することを目的としています。
2つ目のポイントは、休暇中の賃金の基本手当相当額(失業給付の算定方式に準ずる額)が支給されるという点です。
これは、教育訓練給付金のように訓練費用の一部が支給されるものとは異なり、長期休暇中の生活費を直接的に保障するものです。
これにより、従業員は訓練期間中の生活費を確保することができ、より長期で専門的な学びにも挑戦しやすくなります。
そして3つ目のポイントは、この制度を利用するためには、企業側に「教育訓練休暇制度が就業規則等で整備されていること」が前提となる点です。
従業員が「教育訓練休暇給付金」を申請する前に、企業は労働者が無給の長期休暇を取得できる教育訓練休暇制度を、就業規則に明確に規定しておく必要があります。
この制度が社内に存在しない場合、従業員は給付金を利用することができませんので、人事担当者の皆様は早急に社内規定の見直しや整備に着手することが求められます。
なぜ今?創設の背景にある「リスキリング推進」と企業の人材育成
教育訓練休暇給付金がこのタイミングで創設される背景には、日本の社会と経済が直面している喫緊の課題があります。
特に「2025年問題」に象徴される少子高齢化による労働人口の減少や、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)に代表されるDX(デジタルトランスフォーメーション)の急速な進展は、産業構造そのものを大きく変えつつあります。
このような変化に対応するためには、既存の知識やスキルだけでは不十分であり、国全体として「リスキリング(学び直し)」を推進し、新たな時代に適応できる人材を育成することが不可欠となっています。
従業員のリスキリングは、個人の成長だけでなく、企業にとっても大きなメリットがあります。
新しい技術やビジネスモデルに適応できなければ、企業の競争力は低下し、持続的な成長は望めません。
従業員一人ひとりが自発的にスキルアップを図り、変化に対応できる能力を身につけることが、企業の未来を左右するといえるでしょう。
しかし、従業員が長期の教育訓練を受けるには、経済的な負担やキャリアの中断といったハードルが存在していました。
この教育訓練休暇給付金制度は、そうした従業員の学びのハードルを下げ、企業の教育投資コストを軽減しながらも、従業員のリスキリングを強力に支援する戦略的意義を持っています。
従業員のスキルアップは、企業の生産性向上やイノベーション創出に直結し、結果として人材の定着率向上や新たな人材確保にもつながります。
この制度を積極的に活用することで、企業は変化に強い組織を作り上げ、持続的な成長を実現することが期待されます。
誰が対象?人事担当者が知るべき受給要件
教育訓練休暇給付金を受給するには、従業員本人、取得する休暇、そしてそのほかの条件がそれぞれ定められています。
ここでは、それらの具体的な要件を詳しく掘り下げて解説していきます。
対象となる従業員の条件(雇用保険の加入期間など)
教育訓練休暇給付金の対象となる従業員には、いくつかの具体的な条件があります。
最も重要なのは雇用保険の加入期間です。
原則として休暇開始前2年間に被保険者期間が 12か月以上あることが必要です。
また、休暇開始前に5年以上、 雇用保険に加入していた期間があることも必須の条件となります。
この要件は、従業員個人の受給資格の根幹をなす部分ですので、人事担当者様は従業員からの問い合わせに対し、この具体的な数値を交えて的確に説明できるよう、しっかりと把握しておくことが重要です。
対象となる休暇の条件(有給 or 無給?必要な日数は?)
給付の対象となる「休暇」についても、明確な条件が設定されています。
まず、この休暇は、企業が賃金を支払わない「無給」の休暇でなければなりません。
有給休暇として賃金が支払われる期間は、給付金の対象外となりますので注意が必要です。
休暇は無給で、かつ30日以上である必要があります。
また、この休暇は従業員が自由に取得できるものではなく、企業の就業規則などに基づき、正式な手続きを経て付与された「教育訓練休暇」である必要があります。
人事担当者様には、この点が従業員に誤解されないよう、制度設計時や説明時に明確に伝えることを強くお勧めします。
いくら、何日間もらえる?給付額の計算方法と支給上限
ここでは、教育訓練休暇給付金を利用した際に、従業員が「一体いくら、どのくらいの期間給付金を受け取れるのか」という具体的な疑問にお答えします。
給付金の正確な計算方法や、支給される期間には上限があるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。
給付額の算定方法(離職時の基本手当が基準)
教育訓練休暇給付金の支給額は、離職時に支払われる「基本手当日額(失業給付)」を基準に算定されます。
この基本手当日額は、原則として休暇を開始する直前6ヶ月間の賃金総額(賞与等は除く)を180日で割った金額を基に一定の割合(50~80%とされる)で算定されます。
具体的な割合は、受給される方の年齢や直前の賃金水準によって変動します。
たとえば、額面月収が30万円の従業員の場合、直近6ヶ月間の賃金総額は180万円となり、これを180日で割ると日額1万円が基本手当の基準となります。
この1万円に対し、年齢や賃金に応じた割合(仮に60%とします)が適用されれば、1日あたり6,000円が給付されることになります。
このように、従業員の月収や年齢によって給付額は異なるため、個別の状況に応じて概算してみると良いでしょう。
最大150日!訓練期間に応じた給付日数
教育訓練休暇給付金が支給される期間には上限が設けられています。
これは、雇用保険の加入期間に応じて決定され、最大で「90日、120日、150日」のいずれかとなります。
具体的には、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満の場合は最大90日、10年以上20年未満の場合は最大120日、20年以上になると最大150日間が給付の対象日数となります。
これらの日数を上限とし、休暇取得日数分が支払われます。
この上限日数は、従業員が教育訓練の計画を立てるうえで非常に重要な要素です。
たとえば、1年間にわたる長期の訓練を計画している場合でも、給付金が支給されるのは最大150日間となるため、残りの期間の生活費についてはご自身で計画を立てる必要があります。
人事担当者は、この上限日数を正確に伝え、従業員が無理のない訓練計画を立てられるよう支援することが求められます。
どのような講座が対象?認められる教育訓練の範囲
教育訓練休暇給付金は、労働者の学びを支援する制度ですが、どのような教育訓練でも対象となるわけではありません。
この給付金を受給するためには、受講する講座も一定の要件を満たす必要があります。ここからは、教育訓練休暇給付金の対象として認められる教育訓練の種類やその範囲について、具体的な事例を交えながら詳しくご説明します。
大学院、専門学校などで実施される講座
教育訓練休暇給付金の対象となる教育訓練の範囲は幅広く、特に大学や大学院、専門学校などの正規の教育機関で実施される講座は、その多くが対象として認められます。
これらの教育機関では、専門性の高い知識や技術を体系的に学ぶことができ、従業員のキャリアアップや専門分野での深化に大きく寄与します。
たとえば、特定の学術分野における学位取得を目指す長期のプログラムや、専門職としての資格取得に直結する専門学校の課程などが該当します。
このような学びの機会は、従業員が自身の専門性を高め、将来のキャリアパスを広げるための重要なステップとなり、企業にとっても高度な専門知識を持つ人材の育成につながるでしょう。
【具体例】DX、語学、医療・福祉系の資格講座
現代のビジネス環境や労働市場のニーズに対応した講座も、教育訓練休暇給付金の対象となります。
企業の競争力強化に直結するDX(デジタルトランスフォーメーション)関連講座、たとえばAIプログラミング、データサイエンス、クラウド技術などは、デジタル化が進む現代において非常に価値の高いスキルです。
また、グローバル化に対応するためのビジネス英語や中国語などの語学講座も対象です。
さらに、少子高齢化社会において需要が高まる医療・福祉系の資格取得講座も含まれます。
これらの具体例から、教育訓練休暇給付金が、個人のキャリアアップだけでなく、社会や企業の変革に対応できる人材育成を推進する制度であることがわかります。
厚生労働省の指定講座リストと確認方法
従業員や人事担当者の方が、受講を検討している講座が教育訓練休暇給付金の対象になるかどうかを確認するには、厚生労働省の指定講座リストを参照するのが最も確実です。
基本的に、既存の「教育訓練給付金」の指定講座であれば、教育訓練休暇給付金の対象にも含まれると考えてよいでしょう。
具体的な確認方法としては、厚生労働省やハローワークのウェブサイトに設置されている「教育訓練給付制度検索システム」を利用するのが便利です。
このシステムでは、講座名、実施機関名、訓練分野などのキーワードで検索することで、対象となる講座を見つけることができます。
申請をスムーズに進めるためにも、事前に受講希望の講座が指定対象であることを必ず確認するようにしてください。
申請の流れは?従業員・企業それぞれの手続きと必要書類
教育訓練休暇給付金の申請プロセスは、従業員本人と企業(人事担当者)の双方にそれぞれ役割があります。
制度を円滑に利用するためには、それぞれの立場がどのような手続きを進め、どのような書類を準備する必要があるのかを把握しておくことが重要です。
ここでは、煩雑に感じられる申請手続きを、従業員と企業の立場からステップ・バイ・ステップで解説しますので、ぜひ参考にしてください。
【従業員向け】申請手続きの4ステップと必要書類一覧
教育訓練休暇給付金の申請は、主に以下の4つのステップで進められます。従業員の方は、計画的に準備を進めることが大切です。
まず、ステップ1として「事前相談」が挙げられます。教育訓練休暇の取得を検討する場合、まずは会社の就業規則を確認し、人事担当者へ相談します。
企業が教育訓練休暇制度を導入しているか、また取得の条件や手続きについて確認し、合意形成を図ることが何よりも重要です。
次に、ステップ2「書類準備」では、受講を希望する教育機関から、入学許可証や受講案内などの書類を取得します。
同時に、管轄のハローワークへ赴き、教育訓練休暇給付金の申請書一式を受け取り、必要事項を記入します。
ステップ3は「申請」です。教育訓練休暇の開始日(受講開始日)の1ヶ月前までに、必要書類をすべて揃えて管轄のハローワークに提出します。
この際、会社の教育訓練休暇証明書など、企業側から発行される書類も必要になるため、早めに準備を進めてもらいましょう。
最後に、ステップ4「受講後報告」として、訓練終了後、定められた期間内に受講証明書や成績証明書などをハローワークに提出することで、給付金が支給されます。
申請に必要な主な書類としては、教育訓練休暇給付金支給申請書、本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーカード(または通知カードと身元確認書類)、受講する教育訓練施設の入学許可証や受講証明書、受講料に関する領収書、そして企業が発行する教育訓練休暇証明書などがあります。
これらの書類は、漏れがないように事前に確認し、準備しておくことがスムーズな申請につながります。
【人事・企業向け】企業が協力すべき手続きと提出書類
人事・労務担当者として、従業員が教育訓練休暇給付金を申請する際には、いくつかの重要な協力と手続きが求められます。
特に重要なのが「教育訓練休暇証明書」の作成と交付です。
これは、従業員が会社の制度に基づいて教育訓練休暇を取得していることを公的に証明するものであり、この書類がなければ従業員は給付金を申請できません。
証明書には、休暇期間、訓練内容、企業が定める教育訓練休暇制度に基づいていることなどが明記されます。
また、企業は従業員の休暇期間中の賃金支払い状況を、ハローワークへ報告する義務があります。
これは、給付金が無給休暇中の生活保障を目的としているため、本当に賃金が支払われていないかを確認するための手続きです。
ハローワークからの照会に応じて、正確な情報を提供できるよう、賃金台帳などの関連書類を整理しておく必要があります。
企業側の協力体制が整っていなければ、従業員は制度を利用することができず、従業員のモチベーション低下や人材流出につながる可能性も否定できません。
これらの手続きを通じて、企業は従業員のリスキリングを積極的に支援する姿勢を示すことができます。
従業員が安心して学びに取り組める環境を整備することは、結果として企業の競争力強化にもつながるため、人事・労務担当者はこれらの手続きを迅速かつ正確に進めるよう心がけましょう。
申請前に確認!制度利用における6つの注意点
教育訓練休暇給付金は、従業員のリスキリングを力強く後押しする魅力的な制度ですが、利用する際にはいくつか注意しておくべき点があります。
知らずに手続きを進めてしまうと、後々トラブルにつながったり、想定外の不利益を被ったりする可能性も考えられます。
そこで、人事担当者が従業員に説明する際にぜひ押さえておきたい、特に重要な6つのポイントを解説していきます。
自社に「教育訓練休暇制度」がなければ利用不可
教育訓練休暇給付金を利用するうえで、まず最も重要な大前提となるのが、企業側が「教育訓練休暇制度」を就業規則などで明確に規定している必要があるという点です。
この制度が社内に存在しない場合、たとえ従業員が教育訓練の受講を希望し、ハローワークで申請しようとしても、給付金を受け取ることはできません。
単に「無給で長期休暇を認める」という口約束や内規だけでは不十分です。
労働基準監督署に届け出た正式な就業規則や、労働協約、労使協定などに基づき、法的に有効な教育訓練休暇制度が整備されていることが、給付金利用の絶対条件となります。
人事担当者様は、まず自社の就業規則を確認し、必要であれば制度の新設や改定に早急に取り組む必要があります。
給付には上限日数が設けられている
教育訓練休暇給付金には、支給される期間に上限が設けられています。
具体的には、雇用保険の加入期間に応じて、最大90日、120日、150日のいずれかとなります。
これは、従業員が長期の教育訓練を計画する際に、特に注意が必要な点です。
たとえば、従業員が1年間の海外大学院留学を計画していたとしても、給付金が支給されるのはそのうちの最大150日間(約5ヶ月間)のみとなります。
残りの期間は給付金が出ないため、従業員は自身の貯蓄や他の収入源で生計を立てる必要があります。
人事担当者様は、この上限について従業員に正確に伝え、休暇期間中の資金計画を現実的に立てるよう促すことが重要です。
失業時の基本手当(失業保険)との関係性
教育訓練休暇給付金の受給は、将来従業員が離職した場合に受け取る可能性のある失業手当(基本手当)に影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、この給付金の算定基礎として使われた雇用保険の被保険者期間は、将来、失業給付を受ける際の計算対象から除外されます。
このため、教育訓練休暇の直後などに離職した場合、失業給付の受給に必要な被保険者期間が不足したり、給付日数が減ったりする可能性があります。
従業員のライフプランに大きく関わる情報であるため、人事担当者様は、この重要な影響について従業員に事前にしっかりと説明し、納得したうえで制度を利用してもらうよう促す必要があります。
休暇中の副業・アルバイト収入に関する注意
教育訓練休暇給付金は、教育訓練に専念するために収入が途絶える労働者を支援する目的で設計されています。
そのため、休暇中に副業やアルバイトで収入を得た場合には、その日の給付金が支給対象外となるため注意が必要です。
たとえば、教育訓練休暇中に週に数日アルバイトをした場合、そのアルバイトで収入を得た日は給付金が支給されません。
従業員が安易な考えで副業をしてしまい、後から給付金の返還を求められるといったトラブルを防ぐためにも、このルールについては事前に明確に周知しておくことが非常に重要です。
不正受給とみなされるケースとは
教育訓練休暇給付金の制度を悪用し、不正に給付金を受け取ろうとする行為は厳しく罰せられます。
不正受給とみなされる具体的なケースとしては、実際には教育訓練に出席していないにもかかわらず申請する、休暇を取得していないのに申請する、副業による収入があるにもかかわらずそれを隠して申告する、などが挙げられます。
不正受給が発覚した場合、受け取った給付金の全額返還を求められるだけでなく、さらに最大でその2倍に相当する金額(つまり合計で受け取った額の3倍)の納付を命じられることがあります。
また、詐欺罪として刑事罰の対象となる可能性もありますので、制度の利用にあたっては、従業員に対してコンプライアンスの遵守を徹底するよう、人事担当者様から強く訴えかける必要があります。
【人事担当者必見】給付金を活用した人材戦略と導入準備
ここまで教育訓練休暇給付金の制度概要や対象者、注意点などについて詳しく見てきましたが、ここでは、人事担当者の皆様が本制度をどのように自社の人材戦略に組み込み、具体的な導入準備を進めるべきかという実践的な側面に焦点を当てて解説します。
就業規則の改定から従業員への効果的な周知方法、そして単なる福利厚生に留まらない戦略的な活用法まで、すぐにアクションに移せる具体的なノウハウをご紹介していきます。
就業規則はどう変える?規定例と変更手続きのポイント
教育訓練休暇給付金を従業員が利用するためには、企業が教育訓練休暇制度を就業規則に明記していることが必須条件となります。
この制度の導入にあたり、まず労働組合がある場合は労働組合の意見を、労働組合がない場合は労働者代表の意見を聞く必要があります。
その後、変更した就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出ることで、法的な手続きが完了します。
就業規則に新たに教育訓練休暇を規定する際の例として、「第〇条(教育訓練休暇)勤続5年以上の従業員が、業務命令または自発的な能力開発のために厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講する場合、90〜150日を上限として教育訓練休暇を申請できるものとする。ただし、具体的な適用条件、申請手続き、期間中の賃金については別途定める細則による。」といった条文が考えられます。
この規定例を参考に、各企業は自社の業種、企業文化、従業員のキャリアパスに合わせて、休暇の取得要件、対象となる訓練の種類、期間の上限、そして復職後のキャリアサポートなど、具体的な細則を定めていくことが重要です。
従業員への効果的な周知方法とエンゲージメント向上へのつなげ方
新設される教育訓練休暇制度と給付金を従業員に効果的に周知し、積極的な利用を促すためには、多角的なコミュニケーション戦略が不可欠です。
社内イントラネットや社内報での情報掲載はもちろんのこと、全社的な説明会や部署ごとのブリーフィングを実施し、質疑応答の時間を設けることで、従業員の疑問や不安を解消することが有効です。
また、人事部内にキャリア相談窓口を設置し、従業員一人ひとりのキャリアプランに合わせた制度活用のアドバイスを提供することも推奨されます。
制度を単なる事務的な情報として伝えるのではなく、「会社はあなたの成長を全力で支援します」という前向きなメッセージと共に発信することで、従業員のエンゲージメントを大きく向上させることができます。
従業員が自身のスキルアップを通じて会社に貢献できる機会が広がることを具体的に示すことで、自己啓発へのモチベーションを高め、結果として従業員の定着率向上や生産性向上にもつながります。
単なる福利厚生で終わらせない!戦略的なリスキリングへの活用法
教育訓練休暇給付金制度を、単なる福利厚生の一環としてではなく、企業の持続的な成長を支える「戦略的リスキリング」のツールとして活用することが、人事担当者に求められます。
そのためには、まず企業として将来的に必要となるスキルや人材像を明確に定義し、それに合致するリスキリングの機会を提供することが重要です。
たとえば、AI活用、データ分析、GX(グリーントランスフォーメーション)関連技術など、自社の事業戦略上不可欠なスキルを習得できる講座を「推奨講座リスト」として提示し、従業員に積極的に受講を促すアプローチが有効でしょう。
さらに、休暇取得を希望する従業員に対しては、事前にキャリアカウンセリングを実施し、学習計画と復職後のキャリアパスを共に検討する場を設けることをお勧めします。
休暇期間中も定期的な面談を通じて進捗を確認し、学習内容を実際の業務にどう活かすかを具体的に話し合うことで、個人の成長と組織の目標を密接に連動させることができます。
このような取り組みを通じて、従業員個々のスキルアップが企業の競争力強化に直結する、戦略的な人材育成サイクルを構築していくことが可能になります。
まとめ
2025年10月に施行される「教育訓練休暇給付金」は、従業員の主体的な学び直しを支援し、キャリアアップを促進するための重要な制度です。
この制度は、無給で30日以上の教育訓練休暇を取得する労働者に対し、国が給付金を支給する制度であり、日本全体のリスキリング推進を後押しする役割を担っています。
企業側にとっては、従業員の能力向上を通じて生産性や企業競争力を高める絶好の機会となります。
ただし、給付金を利用するためには、まず企業が就業規則等で「教育訓練休暇制度」を整備することが大前提となります。
給付額や支給日数には上限が設けられており、従業員への丁寧な説明が必要です。
休暇中の副業による収入がある場合は、給付の対象外となる日があることや、不正受給とみなされる行為には厳しい罰則があることなど、人事担当者はこれらの注意点を正確に理解し、従業員に周知徹底することが求められます。
この教育訓練休暇給付金を単なる福利厚生としてではなく、企業の成長戦略に不可欠な人材育成の柱として位置づけることが重要です。
就業規則の適切な改定、従業員への効果的な情報提供、そして会社の未来に必要なスキル習得を促す戦略的なリスキリングプログラムの推進を通じて、従業員の自律的な学びを最大限に引き出し、企業の持続的な成長へとつなげていきましょう。