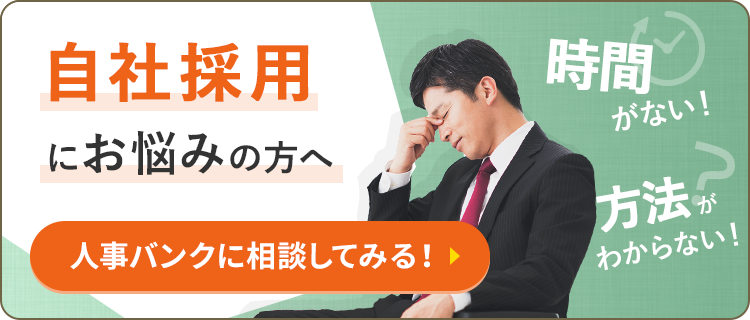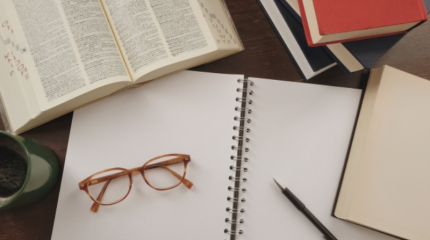近年、職場のハラスメントに対する意識がかつてないほど高まっています。
これは、従業員が安心して働ける環境を整備する上で非常に重要な進展ですが、その一方で「ハラスメント・ハラスメント(ハラハラ)」という新たな問題が顕在化し、人事担当者の皆様を悩ませるケースが増えています。
この記事では、「ハラハラ」が何を意味するのか、なぜ現代の職場で注目されるようになったのか、そして企業にどのようなリスクをもたらすのかを深く掘り下げて解説します。
「ハラハラ(ハラスメント・ハラスメント)」とは?
最近耳にする「ハラハラ」という言葉は、ハラスメントに関連する新しい概念です。
ここでは、職場における「ハラスメント・ハラスメント」の定義を明確にしていきます。
職場で問題視される「ハラハラ」の定義
「ハラスメント・ハラスメント」、略して「ハラハラ」とは、業務上で必要かつ適切な指導や注意に対し、それをハラスメントであると過剰に主張する行為を指します。
これは、本来であれば業務の適正な遂行や部下の成長を促すためのコミュニケーションが、ハラスメントという名目で否定されてしまうことで発生します。
この問題は、特に職場環境において顕著であり、多くの場合、上司が被害者となり、部下が加害者となる構図が見られます。
たとえば、部下の業務ミスを指摘したり、進捗状況を確認したりといった、上司として当然果たすべき役割が、ハラスメントだと主張されるケースがそれに該当します。
「ハラハラ」は、単なる個人間の感情的な対立に留まらず、組織全体の健全な運営を阻害する深刻な問題です。
管理職が適切な指導を躊躇するようになり、結果として業務の停滞や生産性の低下を招き、組織全体の士気を低下させる新たなリスク要因として、人事担当者はその実態を正確に把握しておく必要があります。
なぜ今「ハラハラ」が注目されるのか?その背景を解説
ハラハラの増加は、単一の原因ではなく、法改正や職場環境の変化など、複数の要因が複雑に絡み合って生じています。
ここでは、なぜ現代の職場で「ハラハラ」が注目されるようになったのか、その背景にある要因を深掘りして解説します。
パワハラ防止法によるハラスメント意識の高まり
2020年6月に施行されたパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)は、職場におけるハラスメント対策を企業に義務付けました。
この法律の施行は、ハラスメントに対する従業員の権利意識を高め、ハラスメント行為の撲滅に向けて社会全体が前向きに動き出すきっかけとなりました。
しかし、その一方で、ハラスメントという言葉が過度に広く解釈され、本来は業務上正当な範囲内でおこなわれる指導や注意までもが、安易に「パワハラ」として主張されるケースが増加しました。
これは、法律の意図するところとは異なる負の側面であり、現場での解釈のずれが「ハラスメント・ハラスメント(ハラハラ)」を生む一因となっています。
結果として、企業はハラスメント防止策を強化しつつも、正当な業務運営が阻害されないよう、新たな課題に直面しています。
指導とハラスメントの境界線の曖昧さ
多くの管理職が直面しているのが、「適切な指導」と「パワハラ」の境界線が曖昧であるという問題です。
業務遂行に必要な指示や、部下の成長を促すためのフィードバックが、どこからハラスメントと見なされるのかについて、明確な基準が確立されていないため、管理職は常に判断に迷いが生じています。
これにより、部下からのハラスメント主張を過度に恐れ、必要な指導をためらってしまう管理職が増えています。
この曖昧さは、部下側にも混乱を生じさせ、「これはハラスメントではないか」という疑念を抱かせやすくなります。
結果として、本来であれば建設的なコミュニケーションであるはずのやり取りが、ハラスメント問題へと発展する土壌を作り出しているのです。
管理職が指導を躊躇することは、部下の成長機会を奪うだけでなく、チーム全体のパフォーマンス低下にもつながりかねません。
コミュニケーション不足が招く信頼関係の欠如
職場におけるコミュニケーション不足は、上司と部下の間に信頼関係が築かれにくく、結果として「ハラハラ」を誘発する核心的な要因となります。
日頃から対話が不足している職場では、上司からの業務指示やフィードバックが、その意図とは異なり、部下にとっては攻撃や非難として受け取られてしまうことがあります。
たとえば、日頃から業務の進捗状況や課題についてオープンに話し合う機会がない場合、上司が業績不振を指摘しても、部下は「なぜ今になって言われるのか」「自分だけがターゲットにされている」と感じるかもしれません。
このような信頼関係の欠如は、上司の正当な指導であっても「ハラスメント」のラベルを貼られかねない状況を生み出します。
相互理解を深めるコミュニケーションが不足していると、ちょっとした言動も誤解を生みやすくなり、ハラスメントの主張へと発展しやすくなるのです。
「ハラハラ」が企業にもたらす3つの重大なリスク
ハラハラを放置すると、単なる個人間のトラブルにとどまらず、企業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
管理職の萎縮、生産性の低下、そして職場全体の人間関係の悪化という、3つの重大なリスクにつながることを深く理解しておく必要があります。
このセクションでは、それぞれのリスクがどのように組織を蝕んでいくのかを具体的に解説します。
リスク1:管理職の萎縮と適切な指導の停滞
ハラハラが企業にもたらす最も直接的なリスクの一つは、管理職の萎縮と適切な指導の停滞です。
部下から「ハラスメントである」と訴えられることを恐れた管理職は、たとえ業務上必要不可欠な指導やフィードバックであっても、それを避けるようになります。
これは「回避型コミュニケーション」と呼ばれ、結果として部下の成長機会を奪い、チーム全体のスキルアップや業務改善が進まなくなってしまうのです。
管理職が本来果たすべき役割を全うできなくなるこの状態は、組織全体の業務遂行能力や生産性の低下に直結します。
新たなプロジェクトへの挑戦や困難な課題への対処において、適切な指導がないために社員が自律的に動けなくなり、結果的に企業の競争力までもが損なわれる可能性も少なくありません。
リスク2:職場全体の生産性と士気の低下
ハラハラ問題は、個別のトラブルに留まらず、職場全体の生産性と士気にも悪影響を及ぼします。
ハラスメントの訴えがあった場合、人事部門や管理職は事実確認や関係者からのヒアリング、調停といった対応に多くの時間と労力を割かなければなりません。
これにより、本来集中すべき業務が滞り、組織全体の業務効率が著しく低下します。
さらに、職場内に「次は自分が訴えられるかもしれない」「誰かの不満によって問題が引き起こされるかもしれない」という不信感や緊張感が蔓延します。
このような環境下では、従業員は自分の意見を自由に発言することを躊躇し、建設的な議論や情報共有が阻害されます。
結果として、組織全体の士気は低下し、社員のモチベーションやエンゲージメントも損なわれてしまうのです。
リスク3:人間関係の悪化と無用なトラブルの増加
ハラハラは、職場における人間関係を著しく悪化させ、無用なトラブルを増加させる原因となります。
ハラスメントの主張があった場合、たとえその内容が事実無根であったとしても、指摘された側の上司と主張した側の部下との間の信頼関係は、一度損なわれると修復が極めて困難になります。
これは、周囲の従業員にも波及し、チーム内に「あの人は信用できない」といった不信感が広がったり、場合によっては派閥が生まれたりする危険性も孕んでいます。
このような状況では、業務を円滑に進めるための報連相が滞ったり、協力体制が崩れたりすることが避けられません。
結果として、業務とは直接関係のない人間関係のトラブルが頻繁に発生し、問題解決に貴重なリソースを浪費することになります。
組織の安定が脅かされ、健全な職場環境の維持が困難になることは、企業にとって大きな損失です。
これは「ハラハラ」?具体的な事例と判断基準
実際の現場では、どのような言動が「ハラハラ」と見なされる可能性があるのでしょうか。
ここでは具体的なケーススタディを基に、その判断基準と、正当な訴えとの違いを明らかにします。
「ハラハラ」と判断されうる言動の具体例
ここでは、「ハラハラ」と判断される可能性のある代表的な言動を、2つのケースに分けて見ていきます。
業務上の正当な指示を「パワハラ」と主張するケース
たとえば、部下が作成した資料に具体的な不備があったため、上司がその点を明確に指摘し、再提出を求めたとします。
この指示に対し、部下から「精神的に追い詰めるパワハラだ」と主張された場合、これが「ハラハラ」と判断される典型的なケースです。
この上司の指示は、業務上の必要性があり、かつ資料の品質向上という目的のためにおこなわれたものであり、その指摘内容も適切かつ相当な範囲内であったと考えられます。
このような状況では、上司の言動は業務命令として正当であり、パワハラには該当しません。
業務上の指導やフィードバックは、組織の目標達成や個人の成長にとって不可欠なものであり、不備の指摘は管理職の役割に含まれます。
部下の成長を促すための建設的な指導が、感情的にパワハラと受け取られることは、「ハラハラ」の典型例と言えるでしょう。
注意や指導に対して過剰に「被害者」として振る舞うケース
もう一つの例として、部下の勤怠不良が続いており、上司が個別に改善を促す注意をしたとします。
この注意に対し、部下が涙ながらに「いじめられている」と周囲の同僚や別部署の社員に訴え、同情を引こうとするケースも「ハラハラ」に該当する可能性があります。
本来、上司の注意は、業務規則に基づいた正当なものであり、部下の問題行動を改善するためのものです。
しかし、部下はこの状況で自身の問題点と向き合うことを避け、自らを「被害者」として演じることで、上司からの正当な指導を無効化しようとしているといえます。
この行動は、問題の本質である自身の勤怠不良から目を逸らし、周囲の感情に訴えかけることで、責任転嫁を図ろうとするものです。
指導方法に問題がなかった場合、このような過剰な反応は「ハラハラ」と判断されることがあります。
正当なハラスメントの訴えとの違いはどこにあるか
「ハラハラ」と「正当なハラスメントの訴え」を区別するためには、いくつかの判断基準を総合的に評価することが重要です。
まず、最も重要なのは「言動の客観性」です。
訴えの内容が、客観的な事実に基づいているか、証拠となるものがあるかを確認します。
次に、「業務上の必要性と相当性」です。
上司の言動が、業務遂行上必要不可欠なものであり、その方法や程度が社会通念上相当な範囲内であったかを見極めます。
たとえば、叱責があったとしても、それが人格否定ではなく、具体的な改善点を示すものであれば、指導の範囲内と判断されます。
さらに、「言動の継続性や意図」も重要な判断材料です。
単発的な出来事ではなく、嫌がらせや苦痛を与える意図が継続的にあったかどうかも検討します。
一方、「主張者の言動のパターン」も考慮に入れるべきです。
過去にも同様の過剰な主張を繰り返す傾向があるか、あるいは自分の責任を回避するためにハラスメントを盾にする傾向がないかなど、複合的に判断します。
ただし、これらの判断は非常にデリケートであり、安易に「ハラハラ」だと決めつけることは絶対に避けるべきです。
すべてのハラスメントの訴えに対しては、公平かつ慎重な事実確認が不可欠です。
感情的な側面だけでなく、客観的な証拠や状況証拠を丹念に収集し、複数人からのヒアリングを通じて事実関係を正確に把握することが、公正な判断を下す上で最も重要となります。
人事担当者が実践すべき「ハラハラ」対策【予防と対応】
ハラハラ問題に効果的に対処するためには、問題発生を未然に防ぐ「予防策」と、発生してしまった際に適切に対応する「対応策」の両輪が不可欠です。
本セクションでは、それぞれについて具体的なアクションプランを解説します。
【予防策】ハラハラを未然に防ぐための組織的なアプローチ
ハラハラを未然に防ぐためには、個人の意識に頼るだけでなく、組織全体で取り組む仕組み作りが重要です。ここでは、特に効果的な3つのアプローチを紹介します。
ハラスメントの定義・基準を就業規則で明確化する
ハラスメントの定義や基準を就業規則で明確にすることは、ハラハラを未然に防ぐための強力な第一歩です。
就業規則にパワハラやセクハラなどの具体例を明記するだけでなく、「業務遂行上必要かつ適正な範囲で行われる指導は、ハラスメントに該当しない」という旨を併記することが重要です。
これにより、従業員はハラスメントの具体的なラインを理解し、管理職は正当な指導をおこなう上での心理的な障壁を取り除くことができます。
結果として、安易なハラスメント主張の抑制にもつながり、組織全体の共通認識が醸成されることで、より健全な職場環境が構築されます。
全従業員を対象としたハラスメント研修を定期的に実施する
ハラスメント防止教育は、全従業員が対象となるべきです。
研修では、何がハラスメントに当たるのかというネガティブな側面だけでなく、何がハラスメントに当たらないのか、すなわち正当な指導の範囲とはどのようなものかというポジティブな側面も、具体的なケーススタディを交えて詳しく説明することが求められます。
特に「ハラハラ」という概念そのもの、それが組織に与える悪影響についても研修内容に含めることで、従業員一人ひとりがこの問題に対する意識を深めることができます。
管理職向けには、適切な指導方法や部下との信頼関係構築の重要性に焦点を当て、一般社員向けには、ハラスメントの正しい理解と相談窓口の活用方法を伝えることで、組織全体の意識改革を促し、ハラハラを発生させにくい職場文化の醸成を目指します。
心理的安全性を高め、健全なコミュニケーションを促進する
職場の心理的安全性を高め、健全なコミュニケーションを促進することは、ハラハラの根本的な予防につながります。
心理的安全性が確保された職場では、従業員は自分の意見や懸念を率直に表明でき、上司からの指導やフィードバックも前向きに受け止めやすくなります。
これにより、誤解や対立が生じにくくなり、ハラスメントと受け取られかねない状況を未然に防ぐことができます。
人事担当者が推進できる具体的な施策としては、管理職向けのコーチング研修を実施し、部下との対話スキル向上を支援することが挙げられます。
また、定期的な1on1ミーティングの制度化、風通しの良い職場文化を醸成するための社内イベントや交流機会の企画なども有効です。
このような取り組みを通じて相互理解と信頼関係を深めることで、ハラハラが生じにくい基盤を作り上げることが期待されます。
【対応策】万が一ハラハラが発生した際の適切な対処法
予防策を講じていても、ハラハラ事案が発生する可能性はゼロではありません。
ここでは、問題が起きてしまった際に、人事担当者が取るべき冷静かつ適切な対処法を3つのステップで解説します。
公平な立場での迅速な事実確認とヒアリング
ハラスメントの訴えがあった場合、人事担当者はまず、公平かつ中立な立場で迅速な事実確認をおこなうことが不可欠です。
予断を持たず、主張者と被主張者の双方、そして可能であれば関係者からも個別にヒアリングを実施します。
感情的な訴えに流されることなく、「いつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたか」という客観的な事実を時系列に沿って詳細に聴取し、整理することが重要です。
この初期段階での丁寧かつ公平な対応は、その後の問題解決プロセスにおける信頼性を担保する上で極めて重要です。
正確な事実関係を把握することで、それが正当なハラスメント事案なのか、あるいはハラハラに該当するのかを適切に判断するための基盤が作られます。
相談窓口や第三者機関の活用
社内にハラスメント相談窓口を設置し、従業員が安心して相談できる体制を整えることは、ハラハラを含む職場トラブルの早期発見と解決につながります。
相談窓口の存在を周知し、プライバシー保護を徹底することで、従業員は気軽に問題を打ち明けることができるようになります。
また、当事者間の感情的な対立が激しく、社内での解決が困難な場合や、公平性の確保が難しいと感じられる場合には、弁護士や社会保険労務士などの外部専門家、あるいはEAP(従業員支援プログラム)などの第三者機関を介入させることも有効な手段です。
第三者の客観的な視点と専門知識を取り入れることで、より公正かつ円滑な解決が期待でき、企業としての信頼性も高まります。
再発防止に向けたフィードバックと職場環境の改善
ハラハラ事案への対応が完了した後も、それで終わりではありません。
再発防止に向けたフィードバックと職場環境の改善は、持続可能な健全な職場を作る上で不可欠なプロセスです。
事実調査の結果、訴えが「ハラハラ」であったと判断された場合、主張した従業員に対しては、その行為が組織や周囲の従業員に与える影響を丁寧に説明し、自身の行動を振り返り、理解を促すフィードバックをおこなう必要があります。
一方で、仮に管理職の指導方法に改善の余地があった場合には、その点についても適切なコーチングや研修をおこない、指導スキルの向上をサポートします。
このように、個別の事案対応で終止符を打つのではなく、そこから得られた教訓を活かすことが重要です。
社内規定の見直しやコミュニケーション改善策の導入など、職場環境全体の改善につなげる視点を持つことが、将来的なハラハラの発生を抑制し、より良い組織を築くための鍵となります。
まとめ:適切な指導を恐れない、健全な職場環境を目指して
本記事では、近年職場で問題視される「ハラスメント・ハラスメント(ハラハラ)」について、定義・背景・リスク・対策を簡潔に解説しました。
ハラハラとは、正当な業務指導を「ハラスメント」と過剰に受け取る行為です。パワハラ防止法の施行やハラスメントへの過敏な反応、指導との線引きの曖昧さ、信頼関係の欠如が背景にあります。
この問題は、管理職の萎縮、生産性の低下、人間関係の悪化といったリスクを企業にもたらします。
しかし、就業規則での定義の明確化や研修の実施、心理的安全性の確保などにより、予防は可能です。
問題が発生した場合は、公平・迅速な対応と事実確認、外部機関の活用、再発防止策の実施が重要です。指導をためらうことが、かえって大きなリスクとなり得ます。
人事担当者を中心に、正しい知識と信頼に基づいた職場づくりを進め、健全なコミュニケーションと相互尊重の文化を育むことが求められます。