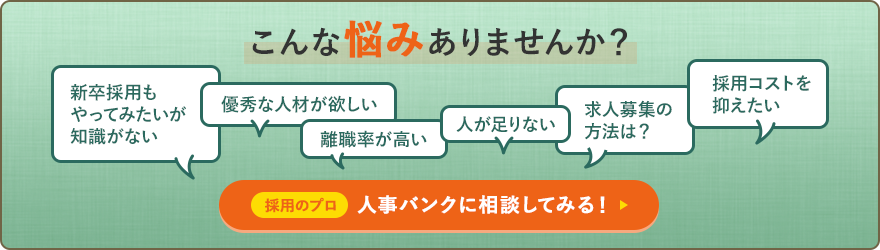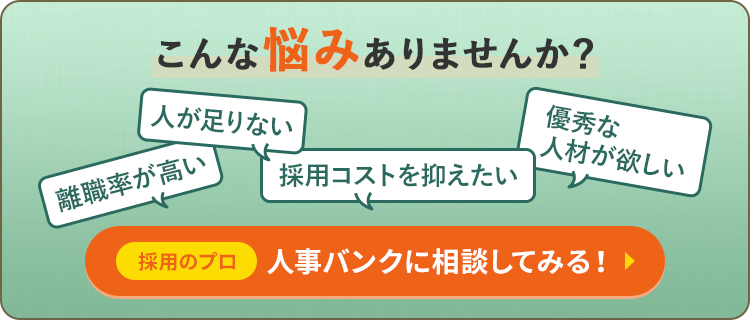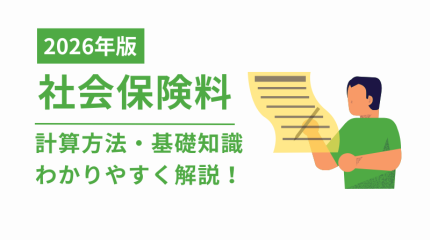年末が近づき、人事・労務ご担当者様にとっては、年末調整と並行して賞与(ボーナス)の計算準備に追われる季節ではないでしょうか。
賞与計算は、社会保険料や所得税など控除額の計算が複雑で、従業員ごとに状況も異なるため、ミスが起こりやすい業務のひとつです。
万が一ミスが発生すると、従業員からの信頼を損なうだけでなく、訂正や差額調整といった煩雑な手続きに追われることになりかねません。
そこで本記事では、年末の賞与計算を控えたご担当者様に向けて、賞与計算の正しい手順から、ミスを未然に防ぐための具体的なチェックポイント、そして万が一間違えてしまった場合の対処法まで、網羅的に解説します。
賞与計算でよくあるミスとその原因
まずは、多くの企業で起こりがちな賞与計算のミスを確認し、どこに注意すべきかを把握しましょう。
最も注意が必要なのが、社会保険料・所得税の計算間違いです。
法改正などで更新された最新の保険料率や税率を適用していなかったり、社会保険料計算の基礎となる標準賞与額(1,000円未満切り捨て)の処理を忘れていたりするケースが散見されます。
また、所得税計算の基準となる「前月の給与」の金額を間違えて参照することも、ミスにつながりやすいポイントです。
次に、対象者の判定ミスも挙げられます。
たとえば、賞与支給月の末日以前に退職した従業員(社会保険料の控除が不要)から控除してしまったり、逆に産休・育休中で社会保険料が免除される従業員から誤って控除してしまったりするケースです。
このほか、賞与の基礎額(総支給額)の算定ミスも起こりがちです。
人事評価や在籍期間の反映を間違え、支給額そのものが違っていたり、欠勤・遅刻早退の控除計算を誤ったりするパターンです。
こうした計算や判定のミスの前段階として、Excelや給与計算ソフトへの手入力時に金額や従業員情報を打ち間違えるといった、単純な入力・転記ミスも後を絶ちません。
これらのミスは、手順の誤解や確認不足、特定の担当者しか手順を知らないといった属人化された業務プロセスが原因で起こります。
一つひとつ丁寧な確認作業をおこなうことが不可欠です。
ここからは、具体的にどういった点に注意して確認を進めるべきかを解説します。
ゼロから確認!正しい賞与計算の5ステップ
それでは、基本となる賞与計算の流れを5つのステップで見ていきましょう。
STEP1:賞与支払対象者の確定
まず、自社の賃金規程や就業規則に基づき、「誰に」賞与を支払うのかを確定させます。
一般的には「賞与の支給日に在籍している従業員」を対象としますが、算定期間中の在籍状況などを加味する企業もあります。
特に、支給を待たずに退職する従業員や、産休・育休中の従業員など、イレギュラーな対象者がいないかを確認することが最初の重要なポイントです。
健康保険法・厚生年金保険法において「賞与」とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの」と定義されています。
したがって、「決算賞与」や「インセンティブ(報奨金)」といった名称であっても、年3回以下の支給であれば社会保険料・所得税の計算対象となる「賞与」として扱う必要があります。
STEP2:総支給額の決定
次に、従業員一人ひとりの賞与の総支給額を決定します。
基本給連動型、業績評価連動型など、企業の制度にしたがって算出します。この金額がすべての計算の基礎となります。
STEP3:控除額の計算①(社会保険料)
総支給額から控除する社会保険料を計算します。賞与から控除される社会保険料は以下の4つです。
- ・健康保険料
- ・介護保険料(40歳~64歳の従業員が対象)
- ・厚生年金保険料
- ・雇用保険料
【健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の計算】
計算式:標準賞与額 × 各保険料率
ポイントは「標準賞与額」です。
これは、賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた金額を指します。
また、健康保険料と厚生年金保険料には上限額があるため注意が必要です。
(健康保険は年度(毎年4月1日~翌年3月31日)で累計573万円、厚生年金は1ヶ月あたり150万円)
【雇用保険料の計算】
計算式:賞与総支給額 × 雇用保険料率
雇用保険料は、1,000円未満の切り捨てをおこなわず、総支給額に直接料率を掛けて計算します。
STEP4:控除額の計算②(所得税)
次に、所得税(源泉徴収税額)を計算します。
計算式:(賞与総支給額 – 社会保険料の合計額)× 賞与に対する源泉徴収税率
この「源泉徴収税率」は、国税庁が公開している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めます。
税率を調べるには、以下の2つの情報が必要です。
- ・前月の給与の課税対象額(総支給額から社会保険料と非課税交通費を引いた額)
- ・扶養親族などの数
前月の給与データと扶養情報を正確に参照することが、正しい所得税計算の鍵となります。
前月の給与がない、または賞与額が前月の社会保険料等控除後給与の10倍を超えるなどの場合は計算方法が異なりますので、詳細は国税庁のWebサイトなどでご確認ください。
賞与計算では社会保険料と所得税を控除しますが、住民税は控除(天引き)しません。
住民税は前年の所得に基づいて計算され、毎月の給与から特別徴収されるため、賞与支給時の計算は不要です。
STEP5:差引支給額(手取り額)の確定
最後に、総支給額からすべての控除額を差し引き、最終的な従業員の手取り額を確定します。
計算式:賞与総支給額 -(社会保険料合計 + 所得税) = 差引支給額(手取り額)
賞与計算のミスを確実に防ぐ!5つのチェックポイント
正しい手順を理解したうえで、ミスを防ぐための具体的なチェックポイントを5つご紹介します。
ぜひ実務でお役立てください。
チェック1:最新の保険料率・税率を公式サイトで確認する
社会保険料率や雇用保険料率は、法改正などにより年度の途中で変更されることがあります。
計算を始める前に、思い込みで作業せず、必ず協会けんぽ(または健康保険組合)や厚生労働省の公式サイトで最新の料率を確認する習慣をつけましょう。
チェック2:特殊なケースの対象者を事前にリストアップする
計算ミスが起こりやすいのは、通常とは異なる対応が必要な従業員です。
以下のケースに該当する従業員がいないか事前に洗い出し、対応方法を個別に確認しておきましょう。
- ・賞与支給月の末日より前に退職する従業員
社会保険料(健康保険・厚生年金)の控除は不要です。
資格喪失月の賞与からは控除しない、というルールのためです。
ただし、雇用保険料は控除対象となりますのでご注意ください。 - ・産休・育休中の従業員
社会保険料の免除期間中であれば、本人負担分・会社負担分ともに控除は不要です。 - ・介護保険の対象になる(40歳)/外れる(65歳)従業員
誕生日に応じて介護保険料の控除対象が変わるため、見落とさないように注意が必要です。
チェック3:ダブルチェック・トリプルチェックの体制を構築する
ヒューマンエラーをゼロにすることは困難です。
だからこそ、担当者一人に任せず、必ず複数人で確認する体制を整えましょう。
「計算担当者」と「確認者」を分けたり、責任者が最終承認をおこなったりすることで、ミスの発見率が格段に向上します。
セルフチェック用の確認リストを作成し、チェック項目をひとつずつ確認していくのも有効です。
チェック4:計算プロセスを可視化・標準化する
「あの人しかわからない」という業務の属人化は、ミスの温床です。
誰が作業しても同じ結果になるよう、計算プロセスを標準化しましょう。
たとえば、Excelの計算シートのフォーマットを統一し、計算式や参照するセルを固定化するだけでも効果があります。
また、なぜその計算になったのか、根拠となる数値を必ず残しておくルールを作ることで、検算や後からの問い合わせ対応もスムーズになります。
チェック5:給与計算システムを最大限活用する
手計算や複雑なExcel管理には限界があります。
根本的なミス防止と業務効率化を目指すなら、給与計算システムの導入・活用が最も効果的です。
多くの給与計算システムは、最新の保険料率や税率が自動でアップデートされ、社会保険料や所得税も自動計算してくれます。
産休・育休などの設定も簡単におこなえるため、担当者の負担を大幅に軽減し、劇的に計算ミスを減らすことができます。
計算後は「賞与支払届」の提出を忘れずに
賞与を支払った後は、支払日から5日以内に管轄の年金事務所(または健康保険組合)へ「被保険者賞与支払届」を提出する義務があります。
この届出に基づき、従業員一人ひとりの標準賞与額が登録され、将来の年金額の計算などに反映されます。
提出漏れは従業員の不利益につながるため、計算・支払業務とセットで必ず期限内に対応しましょう。
もし賞与計算を間違えてしまったら?正しい訂正・対応方法
万全を期していても、ミスが発覚する可能性はあります。
その際は、慌てず誠実に対応することが重要です。
まずおこなうべきは、従業員への説明と謝罪です。
何よりも先に、対象の従業員に計算ミスがあった事実を速やかに伝え、誠心誠意謝罪します。
原因と今後の対応について丁寧に説明し、信頼関係を損なわないよう努めます。
次に、差額の精算をおこないます。
不足分があった場合は、速やかに追加で支給します。
過払いがあった場合は、原則として次回の給与や賞与で相殺するか、直接返還してもらうことになります。
ただし、一方的な天引きはトラブルの元になるため、必ず従業員の同意を得てから進めましょう。
同時に、行政機関への修正手続きも必要です。
控除額に誤りがあった場合、年金事務所やハローワーク、税務署への修正手続き(「賞与支払届」の訂正届や、年末調整での再計算など)をおこない、正しい内容に訂正しましょう。
賞与計算に関するFAQ(よくある質問)
Q. 算定期間中に途中入社した従業員の賞与はどう計算しますか?
A.多くの企業では、就業規則や賃金規程に基づき、算定期間中の在籍日数に応じて日割り(あるいは月割り)で計算します。
計算方法(日割りか、算定基準日に在籍しているか否かなど)は企業のルールによって異なるため、自社の規程をまずご確認ください。
Q. パートやアルバイトにも賞与計算は必要ですか?
A.パートやアルバイトであっても、賞与を支給し、かつ社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の被保険者であれば、正社員と同様に社会保険料や所得税の計算・控除が必要です。
Q. 賞与支払届の提出が遅れたり、忘れたりするとどうなりますか?
A.提出が遅れた場合でも、速やかに提出してください。意図的に届出をおこなわない場合、健康保険法などに基づき罰則(懲役または罰金)が科される可能性もあります。
また、従業員の将来の年金額に影響するため、必ず期限内に提出しましょう。
まとめ
賞与計算は、正確性が第一に求められる重要な業務です。 ご紹介した内容を着実に実行し、「最新料率の確認」「特殊ケースのリストアップ」「ダブルチェック体制」といった5つのチェックポイントを徹底することで、ミスを限りなくゼロに近づけることができます。
さらに、計算後の「賞与支払届」の提出までを確実におこない、業務を完了させましょう。
年末の繁忙期、正確かつ効率的に業務を進めるためにも、本記事の内容をぜひお役立てください。
そして、ミスの不安から解放される根本的な解決策として、給与計算システムの活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。