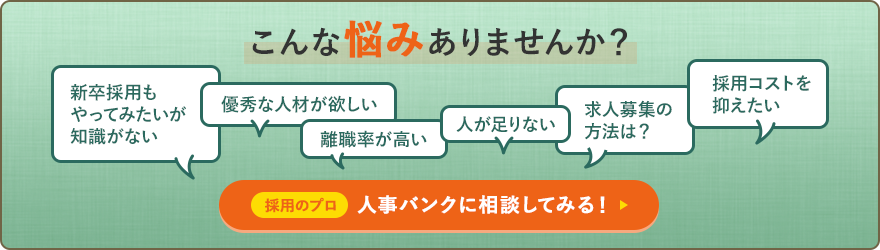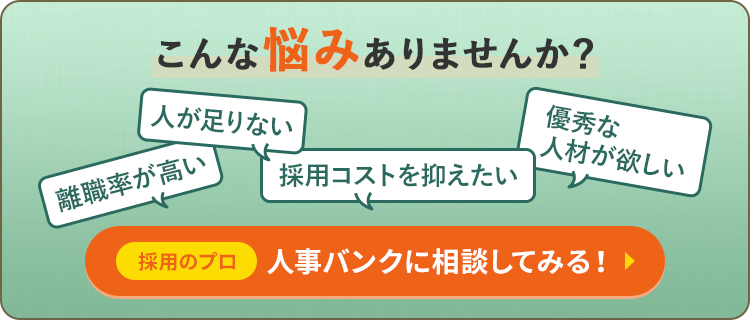近年、企業の人事担当者や経営層の間で「リベンジ退職」という言葉が深刻な課題として認識され始めています。
手塩にかけて採用し、これからの活躍を期待していた新入社員や若手社員が次々と離職していく現実は、採用コストや育成コストの損失に留まらず、残された社員の士気低下や組織全体の生産性悪化にもつながりかねない、看過できない問題です。
本記事では、「リベンジ退職」がなぜ発生するのか、その背景にある構造的な原因を深掘りし、従来の早期離職との違いを明確にしたうえで、人事担当者が今すぐにでも取り組むべき、本質的かつ具体的な防止策について、網羅的に解説していきます。
「リベンジ退職」とは何か?
まず、この新しい現象を正確に理解するために、「リベンジ退職」の定義とその背景、そして従来の早期離職とは何が違うのかを明確に区別しておく必要があります。
リベンジ退職の定義
リベンジ退職とは、学術的な定義はないものの、主にメディアや人材業界で用いられている言葉です。
一般的には、職場や上司への強い不満や失望を背景に、引継ぎをおこなわずに退職する、繁忙期を狙って辞めるなど、組織に不利益が生じる可能性のある「報復的な退職行動」を指します。
ここでの「リベンジ(復讐)」は、単なる転職やキャリアの立て直しではなく、職場への不満が退職という形で表面化した状態を示す言葉として扱われるのが一般的です。
従来の早期離職との本質的な違い
若手社員の早期離職は、従来から企業が抱える普遍的な課題でした。
従来型の早期離職は、入社後の環境不適合が主因で、「提示された労働条件と実態が異なる」「配属先の人間関係に馴染めなかった」「業務内容が自分に合わなかった」といった問題が中心でした。
一方、報道で使われる「リベンジ退職」は、入社前後の環境だけではなく、職場や上司への強い不満・怒りを背景に、引継ぎをおこなわず退職する、繁忙期を狙って辞めるなど、組織に損害を与える可能性のある退職行動を指す点で異なります。
学術的定義はなく、主に報道や人事領域の調査で用いられる概念です。
つまり、問題の起点は入社後における職場への不満であり、単なるキャリア志向の転職とは区別されます。
リベンジ退職を理解するには、動機が従来の早期離職とは根本的に異なることを押さえる必要があります。
なぜリベンジ退職は起こるのか?構造的な3つの原因を深掘りする
リベンジ退職は、個人の資質や忍耐力の問題として片付けられるものではありません。
その背景には、社会環境の変化がもたらした構造的な原因が存在します。
ここでは、人事担当者が把握しておくべき3つの主要な原因を深掘りして解説します。
原因1:採用プロセスのオンライン化がもたらした「相互理解の歪み」
リベンジ退職の最大の引き金となったのは、採用活動の急速なオンライン化です。
パンデミックに対応するため、多くの企業が説明会から面接までの全プロセスをオンラインに移行しました。
これにより、地理的な制約なく多くの学生にアプローチできるという効率化が実現した一方で、深刻な副作用も生み出しました。
それが、企業と学生の「相互理解の歪み」です。
対面でのコミュニケーションでは、言葉の内容だけでなく、オフィスの雰囲気、社員同士の何気ない会話、すれ違う社員の表情、面接官の佇まいといった、数多くの非言語的な情報から、その企業の「空気感」や「カルチャー」を感じ取ることができます。
しかし、オンラインではこれらの情報が著しく欠落します。
学生は、企業側が編集し、最適化した情報しか受け取ることができず、その企業のリアルな姿を想像するしかありません。
逆に企業側も、画面越しの限られた情報だけでは、候補者の本質的な人柄や潜在的な価値観、自社のカルチャーとの親和性を正確に見抜くことが困難になりました。
この情報格差が、入社後に「聞いていた話と違う」「思っていた雰囲気と違う」というリアリティショックを、これまで以上に深刻なものにしているのです。
原因2:リモートワーク環境下での「オンボーディング不全」
就職活動の歪みという「入口」の問題に加え、入社後の受け入れ体制、すなわち「オンボーディング」の不全がリベンジ退職を加速させています。
特に、入社直後からリモートワークが主体となった環境は、新入社員の組織への適応を著しく困難にしました。
本来であれば、職場での先輩や上司との何気ない雑談、ランチタイムの交流、隣の席の先輩の電話応対を聞いて仕事を覚えるといった、偶発的な学びや関係構築の機会が豊富にあります。
しかし、リモートワーク下では、こうした機会が失われます。
業務上の疑問があっても「こんなことでチャットを送っていいのだろうか」と躊躇してしまい、結果として一人で問題を抱え込んでしまいます。
同期入社の仲間との連帯感も希薄になりがちで、社会人として最も不安な時期に強い孤独感や疎外感を味わうことになります。
これは単なる「寂しさ」の問題ではありません。
組織の一員として認められていないという感覚や、周囲からスキル習得のサポートを十分に受けられず成長が実感できないという焦りは、企業への帰属意識(エンゲージメント)の低下に直結します。
「この会社にいても成長できないかもしれない」「自分はここで必要とされているのだろうか」という疑念が、離職という決断を後押しする強力な動機となってしまうのです。
原因3:Z世代特有のキャリア観と「健全な転職市場」の存在
リベンジ退職の対象となるZ世代、あるいは若手世代全般のキャリアに対する価値観の変化も、この現象を理解するうえで欠かせない要素です。
彼らの多くは、終身雇用が過去のものとなった時代に育ち、会社にキャリアを委ねるのではなく、自らの手でキャリアを切り拓いていく「キャリアオーナーシップ」という意識を強く持っています。
そのため、ひとつの企業に勤め上げることへのこだわりは薄く、自身の成長につながらない、あるいは価値観に合わないと感じれば、より良い環境を求めて転職することに心理的な抵抗がほとんどありません。
彼らにとって転職は、キャリアの失敗を意味するネガティブなものではなく、自己実現のためのポジティブで合理的な選択肢のひとつです。
さらに、SNSや口コミサイトを通じて、他社の労働環境や企業文化、給与水準といった情報を容易に入手できるため、自社を客観的に評価し、比較検討することが日常的におこなわれています。
こうした価値観に加え、現在の日本市場が人手不足を背景に第二新卒や若手人材の採用に積極的であり、転職しやすい環境が整っているという外部要因も大きく影響しています。
現職への多少の不満や将来への不安が、「転職すればもっと良い環境があるはずだ」という期待と結びつき、リベンジ退職という具体的な行動を後押ししているのです。
リベンジ退職を防ぐために人事が取り組むべき本質的な対策
では、企業はこのリベンジ退職という潮流にどう立ち向かえばよいのでしょうか。
小手先のテクニックではなく、組織の在り方そのものを見直す、本質的な3つの対策が求められます。
対策1:採用広報・選考プロセスにおける「透明性」の徹底
入社後のギャップを最小化するためには、採用活動の段階で「正直さ」と「透明性」を徹底することが最も重要です。
これは、企業の魅力をアピールすることをやめるという意味ではありません。
魅力的な側面と同時に、仕事の厳しさ、地道な業務内容、組織が抱える課題といったリアルな情報も包み隠さず開示する「RJP(Realistic Job Preview/現実的な仕事情報の事前開示)」を実践することが不可欠です。
たとえば、キラキラした成功事例だけでなく、「入社後、最も苦労したこと」を若手社員に語ってもらう動画コンテンツを制作したり、説明会で「当社の弱み」について敢えて言及したりすることで、学生は入社後の働き方を現実的にイメージでき、覚悟を持って入社を決めることができます。
選考プロセスにおいても、企業が一方的に候補者を評価する場ではなく、候補者が企業を深く理解し、自身のキャリアと照らし合わせる「双方向の対話の場」と位置づけるべきです。
面接時間の半分を候補者からの質疑応答の時間にあてる、あるいは現場社員とのカジュアルな面談を複数回設定するなどして、候補者の不安や疑問を徹底的に解消する姿勢が求められます。
さらに、内定を出してから入社するまでの期間も重要です。
定期的な連絡や内定者向けのイベント、メンターとなる先輩社員との事前の顔合わせなどを通じて、内定者のエンゲージメントを維持し、入社日を万全の状態で迎えられるようサポートすることが、入社直後の離職を防ぐ上で極めて効果的です。
対策2:入社後の定着と活躍を促す「戦略的オンボーディング」の構築
採用のミスマッチをゼロにすることは不可能です。
だからこそ、入社した社員が組織にスムーズに適応し、早期に活躍できるよう支援する「戦略的なオンボーディング」プログラムの構築が決定的に重要になります。
特に、最初の90日間は社員の定着を左右する極めて重要な期間と捉え、体系的なサポート体制を設計する必要があります。
具体的には、業務の指導役とは別に、年齢の近い先輩社員を「メンター」としてアサインし、業務上の悩みからプライベートな相談まで気軽にできる関係性を築くことが有効です。
ただし、この制度を成功させる鍵は、メンターの選定と教育にあります。
メンター自身が制度の目的を深く理解し、新入社員の話を真摯に聴く傾聴力や、適切なフィードバックをおこなうスキルを身につけられるよう、企業側が研修などの支援をおこなうべきです。
また、上司との定期的な1on1ミーティングも欠かせません。これを単なる業務の進捗確認の場とするのではなく、本人のキャリアプランや価値観、現在のコンディションなどを共有する「キャリア面談」として機能させることが重要です。
上司が部下の成長と幸福にコミットしているという姿勢を示すことが、信頼関係の基盤となり、エンゲージメントを高めます。
くわえて、同期同士の連帯感を醸成する研修や、他部署の社員と交流できるランチ会などを意図的に企画し、社内に公私にわたる「タテ・ヨコ・ナナメ」のつながりを構築することも、孤独感を和らげ、組織への定着を促します。
対策3:キャリアの自律性を尊重し、成長機会を提供する仕組みづくり
「この会社で働き続けたい」と社員に思ってもらうためには、目の前の業務だけでなく、その先にある未来、つまりキャリアへの希望を示すことが不可欠です。
まず、自社内におけるキャリアパスを「見える化」することが求められます。
どのようなスキルや経験を積めば、どの役職に就けるのか、そのための評価基準は何なのかを明確に示し、社員が自身の5年後、10年後の姿を具体的に描けるように支援します。
優れたキャリアを歩んでいる社員をロールモデルとして紹介することも有効でしょう。
さらに重要なのは、会社が一方的にキャリアパスを提示するだけでなく、社員自身がキャリアを選択できる「自律性」を尊重する仕組みです。
たとえば、希望する部署へ自ら手を挙げて異動できる「社内公募制度」や、新規事業を提案できる「ビジネスコンテスト」などを導入することで、社員の挑戦意欲を刺激し、マンネリ化を防ぐことができます。
「成長実感」は若手社員にとって極めて重要なモチベーションです。
現在のスキルレベルよりも少し難易度の高い業務を意図的に任せる「ストレッチアサインメント」も有効な手段となります。
くわえて、資格取得支援制度や外部研修への参加費補助など、社員の自律的な学習(リスキリング)に会社が投資する姿勢を示すことは、「会社は自分の成長を応援してくれている」という強いメッセージとなり、エンゲージメント向上に大きく貢献します。
まとめ
本記事では、社会問題化しつつある「リベンジ退職」について、その定義、構造的な原因、そして企業が講じるべき具体的な対策を多角的に解説しました。
リベンジ退職を、単に「最近の若者は我慢が足りない」といった世代論で片付けてしまうと、企業は本質的な問題解決の機会を永遠に失ってしまいます。
むしろ、リベンジ退職は、退職していく社員が身をもって示してくれた、自社の組織課題を浮き彫りにする貴重なフィードバック、いわば「組織の健康診断」の結果と捉えるべきです。
今回ご紹介した対策は、一見すると手間やコストがかかるように思えるかもしれません。
しかし、これらに真摯に取り組むことは、リベンジ退職の防止に留まらず、すべての社員のエンゲージメントと生産性を向上させ、優秀な人材が「ここで働き続けたい」と心から思える、魅力的な組織文化を醸成することにつながります。
それは、変化の激しい時代を生き抜くための、最も確実で価値ある未来への投資といえるでしょう。