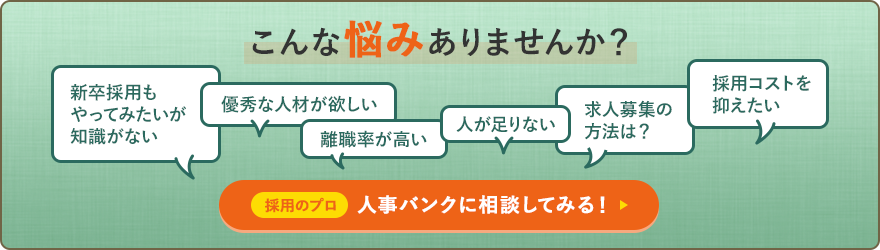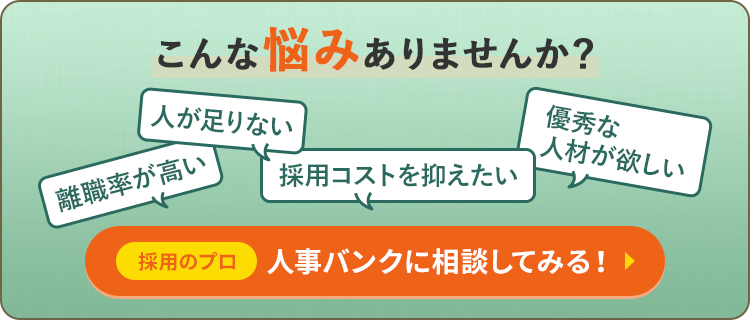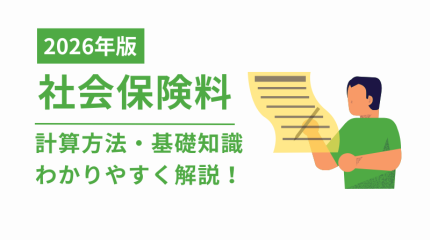近年、「ウェルビーイング」という言葉を耳にする機会が増えました。
これは単に病気ではない状態や一時的な幸福を指すのではなく、肉体的、精神的、社会的にすべてが満たされた「良い状態」を意味する包括的な概念です。
現代社会において、経済的な豊かさだけでは測れない個人の生活の質や幸福が重視されるようになり、特にビジネスの文脈では、従業員のエンゲージメント向上や企業の持続的成長の鍵として、ウェルビーイングへの注目が高まっています。
本記事では、このウェルビーイングという概念を多角的に掘り下げていきます。
その歴史的背景や現代社会で注目される理由、そして個人や企業がウェルビーイングを実現するためにどのような取り組みがなされているのかについて解説します。
また、その状態をどのように測定するのかについて、具体的な事例や測定方法を交えながらご紹介しますので、少しでもお役に立てば幸いです。
主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイング
ウェルビーイングをより深く理解するためには、「主観的ウェルビーイング」と「客観的ウェルビーイング」という二つの側面を知ることが重要です。
これらはウェルビーイングを構成する基本的な要素であり、それぞれ異なる意味合いを持っています。
主観的ウェルビーイングとは、個人が自身の幸福感や人生に対する満足度、生きがいなどをどのように感じているか、という内面的な評価を指します。
これは個人の心の状態や感情に焦点を当てたもので、たとえば「毎日が充実していると感じるか」「仕事にやりがいを感じるか」といった質問を通じて測定されます。
数値化が難しい側面もありますが、個人の実感に基づいているため、真の幸福を測るうえで欠かせない要素といえるでしょう。
一方、客観的ウェルビーイングは、個人の外部環境や具体的な状況に基づいて測定される指標です。
たとえば、所得水準、健康状態、労働時間、教育レベル、居住環境の安全性などがこれに当たります。
これらは客観的に比較・評価が可能であり、国や企業の施策の効果を測る際によく用いられます。
企業が従業員のウェルビーイング向上を考える際には、この主観的・客観的両方の側面をバランス良く捉え、施策に反映させることが非常に重要になります。
たとえば、健康診断の受診率向上(客観的)だけでなく、従業員が「体調が良い」と感じているか(主観的)を把握し、どちらの視点からもウェルビーイングを向上させるよう取り組むことで、よりよい企業経営を実現できます。
「ウェルビーイング」 は100年かけて議論が進む重要な概念
ウェルビーイングという言葉は、一見すると最近注目され始めた新しい概念のように思えるかもしれません。
しかし、実はこの概念は、人々の幸福や社会のあり方について、100年以上にわたり学術的、社会的に深く議論されてきた、非常に重要なテーマなのです。
単なる流行語ではなく、長きにわたる研究と社会の変化の中でその意味合いを深めてきました。
ウェルビーイングの言葉の起源や歴史的な背景を紐解きながら、この概念がいかに奥深く、現代社会にとって重要なものかを解説します。
ウェルビーイングの語源
「ウェルビーイング(Well-being)」という言葉は、「well(良い)」と「being(状態)」という二つの英語が組み合わさってできています。
文字通り「良い状態」を意味し、健康で幸せな状態や、満たされた生活を送っている状態を指します。
この「良い状態」は、単に身体的な健康だけでなく、精神的な安定、社会との良好なつながり、そして人生全体の満足度といった、さまざまな側面を含んだ広い概念として使われるようになりました。
ウェルビーイングの歴史
ウェルビーイングの概念は、時代とともにその解釈を広げてきました。
元々、ウェルビーイングという言葉が広く認知されるようになったきっかけのひとつは、1946年に世界保健機関(WHO)が発表した憲章の健康の定義にあります。
ここでは、「健康とは、病気ではないとか、虚弱ではないということではなく、肉体的、精神的、社会的に完全に満たされた状態である」と明記され、単に病気がないことにとどまらない、より包括的な健康観が示されました。
この定義は、ウェルビーイングの多面的な性質を示唆するものでしたが、さらに2021年には、WHOがウェルビーイングを「個人や社会が経験するポジティブな状態」と再定義しました。
この再定義の背景には、新型コロナウイルス感染症の世界的流行があります。
パンデミックは、人々の生活様式や働き方を大きく変化させ、心身の健康や、社会とのつながりの重要性を改めて浮き彫りにしました。
不安や孤立感が増大する中で、単なる健康維持だけでなく、個人が精神的にも社会的にも満たされた「良い状態」であることへの意識が急速に高まり、ウェルビーイングが現代社会における喫緊の課題として改めて注目されるようになったのです。
なぜウェルビーイングが注目されているか
ウェルビーイングがなぜこれほどまでに注目を集めているのか、その多角的な理由を掘り下げ、経済成長の先に、私たちが「実感できる豊かさ」や、地球全体での持続可能な幸福をどのように追求していくか、その背景にある価値観の変化を探り、今後の社会や企業活動の方向性を考えていきましょう。
経済的な豊かさが幸せとは限らない社会で、生活の実態が大切にされている
かつて国の豊かさを示す主要な指標とされてきたGDP(国内総生産)は、経済活動の規模を測るうえで重要な役割を果たしてきました。
しかし、GDPがどれだけ高くても、そこに暮らす人々の幸福度が低いという現実が浮き彫りになるにつれ、経済的な豊かさだけでは真の幸せを測れないという認識が世界的に広まっています。
たとえば、日本の経済規模は世界有数ですが、国連が発表する世界幸福度ランキングでは上位に位置することは稀で、主観的な幸福感や生活の満足度において、他の先進国に遅れをとる傾向が見られます。
このような状況から、人々が実際に「実感できる」生活の質や、個人の主観的な満足度が、国の豊かさを測るうえでより重要視されるようになりました。
これは、物質的な充足だけでなく、精神的な健康、良好な人間関係、自由な選択ができる環境、そして未来への希望といった、多岐にわたる要素が幸福を構成するという考え方に基づいています。
経済的な数字だけを追い求めるのではなく、人々の暮らしの「実態」を深く理解し、それに寄り添う政策や企業活動が求められる時代へと変化しているといえるでしょう。
成熟社会では、「実感できる豊かさ」 が求められる
社会が物質的な豊かさを達成し、いわゆる「成熟社会」へと移行する中で、人々が求める価値観は大きく変化しています。
以前はモノを所有することや経済的な成功が重視されていましたが、現代では心の充足感や自己実現、良好な人間関係、そして自分らしい生き方といった「実感できる豊かさ」へと価値の軸がシフトしているのです。
特に、デジタルネイティブであるZ世代は、情報過多な社会の中で育ち、画一的な価値観に縛られることなく、自分らしい生き方を重視する傾向が非常に強いです。
彼らにとって、個人のウェルビーイングはまさに自己実現の基盤であり、企業が従業員のウェルビーイングを尊重し、それをサポートする環境を提供することは、優秀な人材を確保し、定着させるうえで不可欠な要素となっています。
働きがいのある職場環境や柔軟な働き方、精神的なサポート体制など、ウェルビーイング経営は、現代の人材戦略において欠かせない考え方といえるでしょう。
SDGs 17の目標の先にある 「地球全体のウェルビーイング」 へ
国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)は、貧困、飢餓、気候変動など、地球規模の課題解決を目指す17の目標から構成されています。
これらの個別の目標達成は、最終的には「地球全体のウェルビーイング」という、より大きなゴールへとつながっています。
たとえば、気候変動対策や生態系の保全は、人類だけでなく地球上のあらゆる生命が持続可能で幸福な状態を享受するための基盤となります。
SDGsが示す17の目標は、単に問題を解決するだけでなく、人間と自然が調和し、未来世代も豊かに暮らせる状態、すなわち地球全体のウェルビーイングを実現するためのロードマップと捉えることができます。
この視点を持つことで、私たちは個々の活動がどのように全体に貢献するのかを理解し、より意識的に行動できるようになります。
教育現場でもウェルビーイングが重要とされ、注目が高まる
ウェルビーイングへの注目は、企業や社会全体に留まらず、教育現場においても急速に高まっています。
単に学力や知識を詰め込む教育から、子どもたちの心の健康や社会性、自己肯定感を育む教育へと重点がシフトしているのです。
文部科学省も、子どもたちの「非認知能力」の育成や、主体性を尊重した学びの重要性を提唱しており、これらはすべて子どもたちのウェルビーイングの向上に直結します。
このような教育を受けて育った世代が社会に出てくるということは、彼らにとってウェルビーイングが当たり前の価値観となることを意味します。
企業が今のうちからウェルビーイング経営に取り組むことは、将来的に価値観を共有できる優秀な人材を引きつけ、企業の成長を長期的に支えるうえで不可欠な戦略となるでしょう。
みんなどんな取り組みをしているの?
ウェルビーイングという言葉は、個人の健康や幸福だけでなく、組織や社会全体のあり方にも深く関わってきます。
それでは、ウェルビーイングの向上に向けて、国や企業、そして研究機関ではどのような具体的な取り組みが進められているのでしょうか。
ここからはさまざまなレベルでのウェルビーイングへのアプローチや具体的な事例をご紹介します。
これらの事例は、自社でウェルビーイング施策を検討する際のヒントとなるはずです。
国を挙げてウェルビーイングに取り組む
近年、多くの国々が国民の幸福度や生活の質を向上させることを国家戦略の中心に据え始めています。
たとえば、ブータンは「国民総幸福量(GNH)」という独自の指標を掲げ、経済成長だけでなく、精神的な幸福や環境保護、文化の継承といった多角的な視点から国づくりを進めています。
GNHは、持続可能な開発、文化の保護と促進、良い統治、環境保護の4つの柱に基づいており、国民のウェルビーイングを総合的に高めることを目指しています。
また、ニュージーランドも国民のウェルビーイングを重視する政策を積極的に推進しています。
2019年には、GDP(国内総生産)といった経済指標だけでなく、生活水準、保健、社会関係、環境、文化など、国民のウェルビーイングを多角的に評価する「ウェルビーイング予算」を導入しました。
これにより、政府は経済的な豊かさだけでなく、国民一人ひとりが心身ともに満たされた状態を実現することを国家運営の重要な目標としています。
これらの国の取り組みは、ウェルビーイングが単なる個人の問題ではなく、国家レベルで取り組むべき重要な課題であることを明確に示しています。
日本における主観的ウェルビーイング拡大に向けた取り組み
日本政府もまた、国民の主観的ウェルビーイング、つまり生活満足度の向上に力を入れています。
内閣府では、国民の生活実態や幸福感を把握するため、「満足度・生活の質に関する調査」を定期的に実施しています。
この調査では、所得や健康状態といった客観的な指標だけでなく、「現在の生活にどの程度満足していますか」といった個人の主観的な満足度や、将来への期待感なども尋ねています。
このような調査を通じて得られたデータは、政府が政策を立案する際の重要な根拠となります。
たとえば、日本は経済的には豊かな国であるにもかかわらず、世界幸福度ランキングでは比較的低い順位に位置しています。
これは、経済的な豊かさだけでは測れない、人々の心の充足や社会とのつながりといった側面が不足している可能性を示唆しています。
この課題を背景に、政府は官民一体となって、国民一人ひとりがより満足度の高い生活を送れるよう、具体的な施策を模索し、実行していくことが求められています。
国民の生活の満足度 (ウェルビーイング) を計測
ウェルビーイングを測定する際には、単一の指標だけでなく、多様な側面からアプローチすることが重要です。
国レベルの取り組みでは、内閣府の「満足度・生活の質に関する調査」がその代表例です。
この調査では、個人の生活全般に対する満足度や、所得、仕事、家族関係、健康、社会とのつながりといった具体的な領域ごとの満足度を質問しています。
また、国際的な基準に合わせた客観的な指標、たとえば平均寿命や教育水準、所得なども同時に収集されます。
これにより、個人の感じ方である「主観的ウェルビーイング」と、外部から測定可能な「客観的ウェルビーイング」の両方を組み合わせて分析することで、国民の生活の質をより多角的に把握しようとしています。
このような多面的な計測を通じて、政策の効果を検証し、国民が真に望む豊かな社会の実現に向けた改善点を見つけ出すことができるのです。
従業員のほか、お客さまや地域住民などのウェルビーイングに取り組み始める
近年、企業のウェルビーイングへの取り組みは、自社の従業員に限定されることなく、より広範なステークホルダーへと拡大する傾向にあります。
これは、企業の社会的責任(CSR)や、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資といった考え方が浸透し、企業活動が社会全体に与える影響が重視されるようになったためです。
顧客、取引先、そして事業拠点のある地域住民など、企業が関わるすべての人々のウェルビーイングに貢献することが、長期的な企業価値の向上につながるという認識が広がっています。
たとえば、ある食品メーカーは、安全で健康的な製品を提供することで顧客のウェルビーイングに貢献するとともに、サプライチェーン全体の労働環境改善にも積極的に関わっています。また、地域の清掃活動や子供向けの教育プログラムに協力することで、地域住民の生活の質の向上にも寄与しています。
このような取り組みは、企業のブランドイメージ向上だけでなく、顧客ロイヤルティの確立や優秀な人材の確保にもつながり、結果として企業の持続的な成長を支える基盤となります。
このように、ウェルビーイング経営は、従業員の幸福度向上に留まらず、顧客満足度の向上、サプライヤーとの強固な関係構築、地域社会との共生など、多岐にわたる側面から企業のレジリエンスを高める戦略的なアプローチとして注目されています。
独自にウェルビーイングの指標や制度を開発する
多くの先進的な企業は、自社の企業文化や従業員の特性に合わせて、独自のウェルビーイング指標や制度を開発し、積極的に導入しています。
たとえば、Googleは「Search Inside Yourself」というマインドフルネスプログラムを通じて従業員の心の健康を支援したり、従業員の満足度を測る独自のサーベイ「Googlegeist」を実施しています。
コマツでは、健康経営の一環として、従業員の健康診断結果や生活習慣に関するデータを分析し、個別の健康増進プログラムを推奨することで、心身両面からのウェルビーイング向上を図っています。
キリンホールディングスは、従業員のエンゲージメントとウェルビーイングの向上を目指し、「キリンのウェルビーイング」という独自のビジョンを掲げています。
具体的には、柔軟な働き方を促進する制度の導入や、メンタルヘルスケアの専門家による相談窓口の設置、さらには従業員同士のコミュニケーションを活性化するイベントの企画など、多角的なアプローチでウェルビーイングを推進しています。
このように、企業が自社に最適化された形でウェルビーイングを追求することは、従業員のエンゲージメントを高め、結果として企業全体の生産性向上や持続的な成長に寄与すると考えられています。
ウェルビーイングの研究や学びが活発に
ウェルビーイングは、単なる漠然とした「幸せ」の追求にとどまらず、心理学、社会学、経済学、医学など、多様な学術分野で活発な研究対象となっています。
世界各地の大学や研究機関では、ウェルビーイングの定義、測定方法、そして向上させるための介入策について、科学的根拠に基づいた検証が進められています。
たとえば、ポジティブ心理学の分野では、個人の幸福や強みに焦点を当てた研究が進められ、具体的な実践方法が提唱されています。
また、多くの大学でウェルビーイングに関連する専門コースや学位プログラムが新設され、企業や自治体の担当者向けのセミナーや研修も活発におこなわれるようになりました。
これにより、ウェルビーイングは感覚的なものではなく、データや理論に基づいたアプローチが可能な分野であることが広く認識されています。
企業が従業員のウェルビーイング向上施策を導入する際にも、これらの学術的な知見や研究成果を参考にすることで、より効果的で信頼性の高い施策の実施につながるでしょう。
ウェルビーイングであるか、どうやってわかるの?
ウェルビーイングという言葉はよく耳にするけれど、実際に「私たちのウェルビーイングはどのくらいなのか」「どうすれば測れるのか」といった疑問を持つ経営者や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。
個人や組織のウェルビーイングを具体的にどのように測定できるのか、世界で広く用いられている代表的な方法をご紹介し、
それぞれの測定方法の特徴と、どのように活用できるかを解説します。
ぜひ自社での施策検討の参考にしてください。
人生をハシゴに見立てて測る「キャントリルの梯子(ハシゴ)」 法
ウェルビーイングの測定方法として、最もシンプルでありながら、個人の総合的な人生評価を把握できるのが「キャントリルの梯子(Cantril Ladder)」です。
この方法は、世界幸福度報告書をはじめとする多くの国際的な調査で活用されています。
具体的には、「あなたの人生を0から10の11段階の梯子に見立ててください。一番上が最高の人生、一番下が最悪の人生だとします。今、あなたはこの梯子のどの段にいると感じますか?」という質問を投げかけます。
さらに、「5年後にはどの段にいると思いますか?」と尋ねることで、現在の幸福度だけでなく、将来への希望や期待感も測ることができます。
この手法は、個人の主観的なウェルビーイングを直感的に捉えることができる点が大きな特徴です。
たとえば、従業員サーベイに組み込むことで、組織全体の幸福度やエンゲージメントの状態を大まかに把握できます。
また、部署ごとの平均値を比較することで、特定の部署でウェルビーイングが低い傾向にあるといった示唆を得ることも可能です。
数値が低い場合には、働き方や人間関係、キャリアパスなど、何らかの改善が必要である可能性を示唆していると考えられます。
5つの質問に答えると幸福度が測れる「人生満足度尺度」
心理学者のエド・ディーナー博士が開発した「人生満足度尺度(Satisfaction with Life Scale、略称SWLS)」も、ウェルビーイングを測るうえで広く利用されているツールです。
これは、わずか5つの質問に「全くそう思わない(1点)」から「強くそう思う(7点)」までの7段階で回答するだけで、個人の主観的な人生満足度を測定できる簡便さが特徴です。
質問はたとえば「私の人生はほとんどの点で理想的である」「私の人生の状況は優れている」「私は人生に満足している」といった内容で構成されています。
合計点数によって満足度が高いか低いかを判断できるため、職場調査や研究で応用されることも多く、この尺度を用い、特定の研修プログラム導入前後での従業員の満足度の変化を測定するといった活用が考えられます。
また、部署間の満足度を比較して、より具体的な組織課題の特定につなげたりすることも可能です。
高い満足度は、生産性の向上や離職率の低下にもつながると考えられていますので、組織の健康状態を測るひとつの指標としても有効です。
オンラインで幸せが測れる「幸福度診断(Well-Being-Circle)」
近年では、オンラインで手軽に個人の幸福度を測定できるツールも登場しています。
そのひとつが「幸福度診断(Well-Being Circle)」です。この診断は、ポジティブ心理学の理論に基づき、個人のウェルビーイングを多角的に分析することを目的としています。
たとえば、セリグマン博士の提唱するPERMAモデル(ポジティブ感情、エンゲージメント、人間関係、意味合い、達成感)など、複数のウェルビーイング理論を背景に質問が設計されていることが多いです。
診断結果は、それぞれの要素についてバランスチャートや具体的なアドバイスとして提示されるため、自己理解を深めるのに役立ちます。
企業がこれを導入すれば、従業員一人ひとりが自身のウェルビーイングの状態を客観的に把握し、改善のきっかけとすることができます。
また、組織全体の傾向を匿名で集計・分析することで、どのようなウェルビーイングの側面が特に課題となっているのか、あるいは強みとなっているのかを把握し、より効果的なウェルビーイング施策の立案に役立てることが期待できます。
世界幸福度ランキング
国連が毎年発表する「世界幸福度ランキング」も、ウェルビーイングを測る重要な指標のひとつです。
このランキングは、一人当たりの国内総生産(GDP)、社会的支援の有無、健康寿命、人生の選択の自由度、寛容さ、そして腐敗の認識という6つの主要な要素に基づいて各国の幸福度を数値化しています。これらの要素は、客観的な経済指標や健康指標と、個人の主観的な感覚や社会の質に関わる要素を組み合わせている点が特徴です。
残念ながら、日本の幸福度ランキングは先進国の中でも低い位置にあり、経済的な豊かさとは裏腹に、人生の選択の自由度や寛容さといった主観的な満足度が低い傾向にあると分析されています。
これは、企業や個人がウェルビーイングを考えるうえで、単に経済的な豊かさだけでなく、働きがいや人間関係、社会とのつながりといった非経済的な要素の重要性を示唆しています。
このランキングは、グローバルな視点から自社のウェルビーイング経営の立ち位置を考えるきっかけとなり、社会全体の課題としてウェルビーイングに取り組む必要性を再認識させてくれるでしょう。
ウェルビーイングでいられるためには?
個人や組織がウェルビーイングな状態を実現し、それを維持していくための具体的な方法について、心理学などの研究によって提唱されている代表的なフレームワークをいくつかご紹介し、ウェルビーイングを高めるための実践的なヒントをお伝えします。
これらの知見は、日々の生活や職場の環境をより良くするための具体的なステップとなるでしょう。
セリグマン博士の「PERMA(パーマ)」モデル
ポジティブ心理学の創始者であるマーティン・セリグマン博士は、持続的な幸福、つまりウェルビーイングを構成する5つの主要な要素として「PERMA(パーマ)モデル」を提唱しました。
PERMAは、Positive Emotion(ポジティブな感情)、Engagement(没頭)、Relationships(人間関係)、Meaning(意義)、Accomplishment(達成)の頭文字から取られています。
「ポジティブな感情」とは、喜びや感謝、希望といった前向きな気持ちを指します。
「没頭」は、時間の経過を忘れるほど何かに集中している状態のことで、いわゆる「フロー状態」もこれに当たります。
仕事や趣味に夢中になることで得られる充実感は、ウェルビーイングにとって非常に重要です。
「人間関係」は、他者との良好なつながりや支え合いを意味します。人は社会的な生き物であり、家族、友人、同僚との温かい関係は、精神的な安定と幸福感に不可欠です。
「意義」とは、自分自身よりも大きなもの、たとえば社会貢献や倫理観、信念のために生きることで得られる目的意識を指します。
仕事に意義を見出すことで、働くことへのモチベーションが高まります。
そして「達成」は、目標を設定し、それを乗り越えることで得られる成功体験や自尊心を意味します。
小さな目標達成の積み重ねが、自信と前向きな気持ちを育みます。
企業では、従業員のパフォーマンスレビューにPERMAの要素を取り入れたり、チームビルディング研修で人間関係を強化したり、キャリアパスを明確にして意義や達成感を高めるなど、さまざまな形でこのモデルを応用することで、従業員のウェルビーイングと生産性の向上を両立させることができます。
ウェルビーイング研究~“SPIRE”アプローチ
ポジティブ心理学の専門家であるタル・ベン・シャハー博士は、ウェルビーイングをより包括的に捉えるためのフレームワークとして「SPIRE(スパイア)モデル」を提唱しました。
SPIREは、Spiritual(精神性)、Physical(身体性)、Intellectual(知性)、Relational(関係性)、Emotional(感情)の5つの側面の頭文字を取ったものです。
「精神性」は、人生の目的や意味を見出すこと、あるいは日々の生活の中に感謝や崇高なものを見出すことを指します。
「身体性」は、健康的な食生活、十分な睡眠、適度な運動など、心身の健康を保つための要素です。
「知性」は、好奇心を持ち、学び続け、新たな知識やスキルを習得することによる知的成長を意味します。
「関係性」は、他者との良好なつながり、社会的な交流、支え合いのネットワークを指します。
これはPERMAモデルの「人間関係」とも共通する重要な要素です。
そして「感情」は、ポジティブな感情を育み、ネガティブな感情とも適切に向き合うことを含みます。
PERMAモデルが主に個人の内面的な幸福感に焦点を当てるのに対し、SPIREモデルは、精神的な充足感から身体的な健康、知的な成長、他者とのつながり、感情の豊かさまで、より広範な側面からウェルビーイングを捉えています。
これらの要素がバランス良く満たされることで、人はより豊かなウェルビーイングの状態を築くことができると考えられています。
企業が従業員のウェルビーイングを考える際にも、単なるストレス軽減だけでなく、これらの多角的な側面から施策を検討することが有効です。
前野隆司先生の「幸せの4つの因子」
慶應義塾大学の前野隆司教授は、日本人の幸福感を研究し、「幸せの4つの因子」という独自のモデルを提唱しています。
これは、幸せを「持続的な幸福」と定義し、それを構成する4つの要素から説明するものです。
それぞれの因子は「やってみよう!」「ありがとう!」「なんとかなる!」「ありのままに!」という親しみやすい言葉で表現されています。
「やってみよう!(自己実現と成長の因子)」は、目標に向かって努力したり、自分の可能性を信じて挑戦したりする中で得られる達成感や成長を意味します。
新しいスキルを習得したり、困難な課題を克服したりする経験が、この因子を育みます。
「ありがとう!(つながりと感謝の因子)」は、人とのつながりを大切にし、感謝の気持ちを持つことで得られる幸福感です。
家族や友人、同僚との良好な関係性や、助け合いの中で生まれる温かい感情が重要になります。
「なんとかなる!(前向きと楽観の因子)」は、失敗を恐れずに前向きに物事を捉え、楽観的に困難を乗り越えようとする姿勢を指します。
完璧主義を手放し、不確実な状況でも希望を見出すことが、心の平穏につながります。
そして「ありのままに!(独立と自分らしさの因子)」は、他者との比較ではなく、自分自身の価値観や個性を尊重し、ありのままの自分を受け入れることを意味します。
この因子は、自己肯定感を高め、自分らしい生き方を追求することにつながります。
これらの4つの因子は、どれかひとつがあれば幸せになれるというものではなく、相互に関連しながら、バランス良く満たされることで持続的な幸福感が生まれると考えられています。
日本人に馴染みやすい表現であるため、企業研修や個人でのウェルビーイング向上のための取り組みにも取り入れやすいでしょう。
たとえば、社内コミュニケーションの活性化で「ありがとう!」の機会を増やしたり、チャレンジできる環境を提供することで「やってみよう!」の機会を生み出すなど、多角的なアプローチが可能です。
自分らしく、ウェルビーイングでいられる方法を探してみよう
ここまで、ウェルビーイングという概念の奥深さや、それを高めるためのさまざまな理論やアプローチをご紹介してきました。
PERMAモデルやSPIREモデル、幸せの4つの因子など、それぞれに異なる視点がありますが、共通しているのは「ウェルビーイングが多面的な要素から成り立っている」という点です。
一方で、これらのモデルが示すのはあくまでも普遍的な要素であり、一人ひとりのウェルビーイングの形は異なります。
大切なのは、画一的な「こうすれば幸せになれる」という正解を求めるのではなく、ご紹介した知識を参考にしながら、ご自身や皆さんの組織にとって「自分らしい」ウェルビーイングのあり方を探求していくことです。
日々の行動を振り返り、何が自分をポジティブな気持ちにするのか、どんな時に充実感を得られるのかを内省してみましょう。
また、同僚やチームメンバーとウェルビーイングについて対話する機会を設けることも有効です。
それぞれの価値観やニーズを共有し、お互いにとってより良い環境を共に創りあげていくプロセスそのものが、ウェルビーイングを高めることにつながります。
ウェルビーイングは一度達成したら終わりではなく、常に変化し続けるものです。
今日から少しずつでも、ご自身や周囲のウェルビーイングを高めるための行動を始めてみませんか。
まとめ
これまでウェルビーイングという概念が、単なる健康や幸福にとどまらず、肉体的、精神的、社会的に満たされた「良い状態」を指す包括的なものであることをご紹介してきました。
WHOによる定義の変遷や、SDGsとの関連性からもわかるように、ウェルビーイングは現代社会において、個人だけでなく企業や国家レベルでも重視される不可欠な概念となっています。
経済的な豊かさだけでは真の幸福は測れないという価値観の変化、そして成熟社会において「実感できる豊かさ」が求められるようになったことが、ウェルビーイングへの注目度を高めています。
特に、自分らしい生き方を重視するZ世代が社会の中心を担うようになる中で、企業がウェルビーイング経営に取り組むことは、従業員のエンゲージメント向上、優秀な人材の確保、離職率の低下、さらには生産性向上といった多岐にわたるメリットをもたらし、企業の持続的な成長に直結する戦略的な投資であるといえるでしょう。
ウェルビーイングの状態を測定する「キャントリルの梯子」や「人生満足度尺度」といったツール、そしてPERMAモデルやSPIREモデル、日本の前野隆司先生が提唱する「幸せの4つの因子」など、ウェルビーイングを高めるための実践的なフレームワークも多数存在します。
これらの知識を活用し、自社の文化や従業員のニーズに合わせて、良好なコミュニケーション環境の構築、健康増進プログラムの導入、柔軟な働き方の推進といった具体的な施策を実行していくことが重要です。
ウェルビーイング経営は、従業員の幸福度向上に貢献するだけでなく、結果として企業のブランドイメージ向上や社会的評価の獲得にもつながります。
ぜひこのウェルビーイングという視点を取り入れ、従業員一人ひとりが活き活きと働ける環境を整え、持続可能な企業成長への具体的な第一歩を踏み出してみてください。