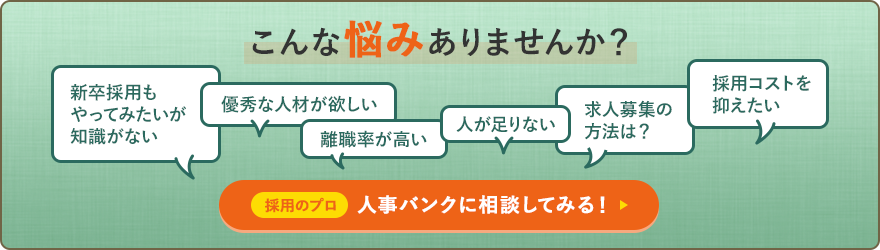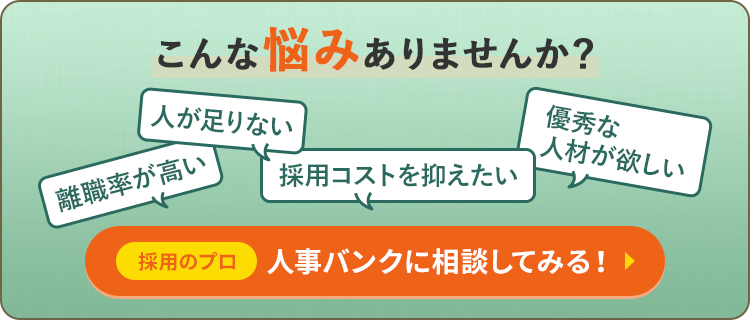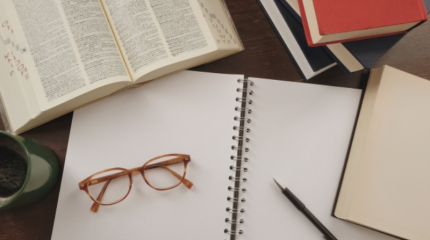電話取次ぎは新人研修の定番テーマ。
基本対応の流れやよくあるNG例を押さえることで、社内の印象や業務効率が大きく変わります。
本記事では、人事担当者が新人教育に活用できる電話取次ぎマニュアルを、言い回しや指導ポイントとともに詳しく解説します。
新人研修で使える電話取次ぎマニュアルの基本
新しい部署で電話対応を任されることになり、電話の取り方や取り次ぎ方に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
電話対応は、単に電話を繋ぐだけの業務ではありません。会社の「顔」としてお客様と最初に接する重要な役割であり、その対応ひとつで会社の第一印象が決まってしまいます。
本記事では、電話取次ぎの基本的なマナーから、実践で役立つ具体的なフレーズ、さらには新人研修でも活用できる社内マニュアルの作成方法まで、電話取次ぎの全てを網羅的に解説します。
会社の代表としての意識を持つ
電話応対は、会社の規模や業種に関わらず、すべての社員が会社の「代表」としてお客様と接する最初の窓口となりがちです。
お客様は電話口の社員の声を通して、その会社の雰囲気やサービス品質、さらには企業文化までを想像します。
そのため、電話応対者がどのような心構えで臨むかが、お客様が会社全体に対して抱く印象を大きく左右するのです。
たとえば、不機嫌そうな声や、ぞんざいな言葉遣いをしてしまうと、お客様は「この会社は社員教育が行き届いていない」「お客様を大切にしない会社だ」といったネガティブな印象を抱いてしまう可能性があります。
逆に、明るく丁寧な声のトーンと適切な言葉遣いで対応すれば、「しっかりとした会社だ」「安心して取引できそうだ」という好印象を与えることができるでしょう。
このように、一つひとつの電話応対が会社の信頼を築き、維持していくための重要なプロセスとなります。
自分が会社の顔であるという責任感を常に持ち、お客様一人ひとりに誠実に対応する意識を持つことが、お客様からの信頼を獲得する第一歩となるのです。
社名・部署・氏名を明確に伝える
電話に出る際の最初のマナーとして、自身の会社名、部署名、そして氏名をはっきりと伝えることが不可欠です。
相手に聞き取りやすいよう、ゆっくりと明確に発音することを心がけてください。
丁寧な名乗り方は、お客様に安心感を与えるだけでなく、間違い電話を未然に防ぐ効果も期待できます。
電話をかけたお客様は、きちんと会社と担当者が確認できたことで、安心して用件を話し始めることができます。
また、もしも間違い電話だった場合でも、早期に判明し、お互いの時間の無駄を省くことにもつながります。
自分の所属と名前を明確に伝えることは、プロフェッショナルとしての第一歩であり、その後の円滑なコミュニケーションの基礎を築く重要なビジネスマナーであることを意識しましょう。
相手の話を復唱して確認する
電話対応において、聞き間違いや勘違いは重大なトラブルに発展する可能性があります。
これを未然に防ぐために非常に重要なのが「復唱確認」です。
お客様の会社名、お名前、電話番号、ご用件、日時などの重要な情報は、必ず相手の言葉を繰り返して確認する習慣を身につけましょう。
たとえば、相手に「〇〇株式会社の△△です」と名乗られたら、「〇〇株式会社の△△様でいらっしゃいますね。いつもお世話になっております」と繰り返すことで、確認の意を示します。
伝言を承る際も、「〇月〇日の〇時に、〇〇の件で折り返しお電話差し上げればよろしいでしょうか」のように、具体的に内容を復唱して間違いがないかを確認してください。
この復唱確認は、お客様に「自分の話をしっかり聞いてくれている」という安心感と丁寧な印象を与えるだけでなく、情報伝達の正確性を格段に高めるうえで不可欠なプロセスです。
聞き取った内容を曖昧なまま進めるのではなく、必ず復唱して確認する徹底した姿勢が、業務の正確性と顧客満足度の向上につながります。
聞き取れない場合は丁寧に聞き返す
お客様の声が小さかったり、電波状況が悪かったりして、お話の内容が聞き取れないことは往々にして起こりえます。
このような場合でも、曖昧なまま話を進めてしまうのは絶対に避けるべきです。
内容を誤解したまま対応してしまうと、お客様にご迷惑をおかけしたり、重大なミスにつながったりするリスクがあるためです。
聞き取れなかった場合は、決して臆することなく、丁寧に聞き返すことが大切です。
「申し訳ございません、お電話が少々遠いようですので、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか」や、「恐れ入ります、お声が聞き取りにくかったのですが、改めてお聞かせいただけますでしょうか」といった具体的なフレーズを使うと良いでしょう。
聞き返すことは、決して失礼にあたる行為ではありません。
むしろ、正確な情報を得るために誠実に対応しようとする姿勢の表れであり、結果としてお客様からの信頼を得ることにもつながります。
不明な点は臆さずに確認し、常に正確な情報に基づいた対応を心がけましょう。
保留操作は一言添えてからおこなう
電話の取り次ぎで担当者を探す際や、お客様からの質問に答えるために何かを確認する際など、一時的に電話の音声を遮断する「保留」機能は頻繁に使われます。
しかし、この保留操作も、マナーを守っておこなわなければお客様に不快感を与えてしまうことがあります。
最も重要なのは、保留ボタンを押す前に必ずお客様に「一言」添えることです。
たとえば、「〇〇に代わりますので、少々お待ちいただけますでしょうか」や、「お調べいたしますので、恐れ入りますが少々お待ちください」のように伝えてから保留にしてください。
何の断りもなく突然保留にすると、お客様は電話が切れてしまったのではないかと不安になったり、不親切な印象を抱いたりする可能性があります。
また、保留時間の目安は一般的に30秒以内とされています。
それ以上長くなる場合は、一度電話に戻り、「大変お待たせしており申し訳ございません。もう少々お時間を頂戴できますでしょうか。それとも、改めてこちらからお電話差し上げましょうか」と、状況を説明したうえで、お客様の意向を確認するようにしましょう。
お客様の時間を無駄にしない配慮が大切です。
受話器は静かに置いて印象を損ねないように
お客様との電話応対がどんなに丁寧で完璧だったとしても、最後に受話器を「ガチャ」と乱暴に置いてしまうと、それまでの努力が台無しになってしまうことがあります。
不快な音は、お客様に非常に悪い印象を与え、「ぞんざいに扱われた」と感じさせてしまう可能性があるためです。
通話が終了し、お客様が電話を切られたことを確認したら、受話器のフックを指でそっと押すか、受話器を静かに台に置くように心がけましょう。
最後の瞬間まで丁寧な所作を意識することで、お客様は最後まで気持ちの良い印象を抱き、貴社に対する信頼感は一層深まります。
受電時のマナーと対応フロー
本セクションでは、実際に会社にかかってきた電話を受ける際の具体的な流れと、それに伴うマナーを時系列に沿って詳しく解説していきます。
素早い応答から始まり、自社の名乗り方、電話をかけてきた相手の方の確認、そして担当者への取り次ぎや不在時の適切な対応に至るまで、一連のフローを学ぶことで、誰でもスムーズかつ好印象を与える電話応対ができるようになるでしょう。
「もしもし」は使わず会社名で応答
ビジネスシーンにおいて、電話に出る際に「もしもし」という言葉は使いません。
これは、あくまで私的な会話で用いられる表現であり、会社の代表として電話応対をする際には不適切とされています。
正しい第一声は、「お電話ありがとうございます。株式会社〇〇でございます」のように、まず相手の方へ感謝の気持ちを伝え、続けて自社の会社名をはっきりと告げることです。
この丁寧な名乗り方は、相手の方にプロフェッショナルな印象を与え、安心して用件を話し始めてもらうための大切な第一歩となります。
自分の名前をはっきり伝える
会社名を名乗った後には、続けて自分の名前もはっきりと伝えることが重要です。
「わたくし、△△が承ります」や「△△でございます」のように名乗ることで、相手の方は誰が対応しているのかを明確に認識できます。
これにより、その後の会話がスムーズに進むだけでなく、対応に責任を持つという姿勢を示すことにもつながります。
自分の名前を伝えることは、相手の方に安心感を与えるとともに、万が一の問い合わせの際にも「△△さんに対応してもらった」と明確に伝えられるため、コミュニケーションの質の向上にも貢献します。
相手の会社名・氏名を復唱して確認
電話をかけてきた相手の方が名乗られたら、その会社名と氏名を必ず復唱して確認する手順を踏みましょう。
これは、聞き間違いや誤解を防ぎ、正確な情報を把握するために不可欠なプロセスです。
たとえば、「〇〇株式会社の△△様でいらっしゃいますね。いつもお世話になっております」のように、確認の言葉とともに日頃の感謝を伝えることで、より丁寧な印象を与えることができます。
名前の間違いは、相手の方に大変失礼にあたりますので、この復唱確認の作業は、ビジネスにおける信頼関係を築くうえで非常に重要となります。
取り次ぎ先の情報を正確に聞き取る
電話を取り次ぐことを依頼された際は、誰宛ての電話なのかを正確に聞き取ることに集中しましょう。
同じ姓の社員が複数いる可能性も考慮し、フルネームだけでなく、部署名や役職なども合わせてしっかりと確認することが大切です。
聞き取った情報は、すぐにメモを取る習慣をつけましょう。
これにより、聞き間違いを防ぎ、正確な情報に基づいたスムーズな取り次ぎが可能になります。
この正確な情報把握は、結果として業務効率の向上にも直結します。
不在時は連絡先と要件を丁寧に伺う
取り次ぎ先の担当者が不在だった場合、まずは相手の方にその旨を丁寧にお伝えします。
たとえば、「申し訳ございません。あいにく〇〇はただいま席を外しております」といった具体的な状況を簡潔に伝えます。
この際、不在の理由を詳しく説明する必要はありません。
次に、相手の方へ今後の対応について選択肢を提示し、能動的な姿勢を示すことが重要です。
「よろしければ、ご伝言を承りましょうか」や「戻り次第、こちらから折り返しお電話いたしましょうか」のように提案し、相手の方の希望を伺います。
もし折り返しを希望された場合は、連絡先(電話番号)と、つながりやすい時間帯を丁寧に伺い、最後に復唱して確認をします。
この一連の対応により、相手の方に親切で丁寧な印象を与えることができます。
電話をかけるときのマナーと準備
ビジネスにおいて、自分から電話をかける「架電」の際にも、電話を受ける場合と同様に、守るべき大切なマナーがあります。
特に重要なのは、相手の貴重な時間を尊重するための「準備」です。
電話をかける前に、何を伝えたいのかを整理し、相手にとって最適な時間帯を考慮し、そして丁寧な名乗り方を習得することで、手際良く、かつ相手に失礼のない電話をかけることができるようになります。
このセクションでは、これらのポイントを具体的に解説していきます。
事前に要件を整理しておく
電話をかける前に、何を伝えるべきか、その目的は何なのかを明確に整理しておくことは、非常に重要です。
話したい内容を事前に箇条書きでメモにまとめておくだけでも、通話中に話が脱線することなく、伝えたい要件を簡潔かつ的確に相手に伝えることができます。
これにより、相手の時間を無駄にすることなく、効率的なコミュニケーションが可能になります。
要件を整理しておくことで、自分自身の伝え忘れを防ぎ、通話の目的を確実に達成できるという大きなメリットがあります。
たとえば、質問事項であればその内容と、相手にどのような回答を求めているのかを具体的にしておくこと、
あるいは依頼事項であれば、期日や必要な情報などを明確にしておくことで、スムーズなやり取りにつながります。
時間帯に配慮して架電する
相手の都合を考慮し、電話をかける時間帯に配慮することも、ビジネスにおける大切なマナーのひとつです。
一般的に、始業直後の忙しい時間帯や、昼休み、そして終業間際などは、相手が最も多忙である可能性が高いため、できる限り避けるのが基本です。
相手の業務サイクルを推測し、忙しくないタイミングを選ぶことで、良好な関係を築き、スムーズに用件を進めることができるでしょう。
名乗りはゆっくり、聞き取りやすく
電話をかける際の第一声である名乗りは、相手に与える第一印象を決定づける重要な要素です。
相手はあなたが誰であるかを予期していないため、ゆっくりと、そしてはっきりと、自分が誰であるかを伝える必要があります。
早口になったり、声が小さかったりすると、相手は聞き取りにくく、不信感を与えてしまうことにもつながりかねません。
「お世話になっております。私、株式会社〇〇の△△と申します」のように、まず丁寧な挨拶に続けて、所属している会社名と自身の氏名を正確に伝えるのが基本です。
取り次がれたら再度名乗ってから本題に入る
電話を取り次いでもらい、目的の担当者が出られた際も、改めて自分の名前を伝えることがマナーです。
これは、担当者が電話を受けた際に、誰からの電話なのかを再確認できるようにするためです。
「株式会社〇〇の△△でございます。先ほどお電話いたしました」のように、一度取り次ぎを経てきたことを付け加えると、相手も状況を把握しやすくなります。
そのうえで、「ただいま、〇分ほどお時間よろしいでしょうか」と、相手の都合を伺う一言を必ず添えましょう。
この一言があるかないかで、相手への配慮の度合いが大きく変わります。相手の都合を一方的に無視して本題に入ってしまうと、失礼な印象を与えかねません。
相手が今、電話対応できる状況にあるかを確認することで、スムーズでストレスのない通話へとつながります。
通話終了時は静かに切るのが基本
電話での用件がすべて終わり、お礼の言葉を述べた後は、「失礼いたします」という挨拶で通話を締めくくるのが一般的です。
かけた側から先に電話を切るのがビジネスにおける基本的なマナーとされています。挨拶が終わったら、慌てずに、静かに受話器を置くように心がけましょう。
この際、受話器を乱暴に置く、いわゆる「ガチャ切り」は、せっかく丁寧なやり取りができていたとしても、最後に相手に不快な印象を与えてしまう可能性があります。
最後まで気を抜かず、受話器をそっと置く、あるいはフックを指で押してから切るなどの所作を徹底することで、最後の瞬間まで相手に良い印象を残すことができます。
電話取次ぎで使える定番フレーズ集
電話取次ぎの業務では、さまざまな状況に対応できる柔軟性と、相手に失礼のない丁寧な言葉遣いが求められます。
しかし、とっさに適切なフレーズを思いつくのは難しいことも少なくありません。
本セクションでは、受電から取り次ぎ、そして終話に至るまで、電話取次ぎのあらゆる場面で役立つ「定番フレーズ」をまとめました。
これらのフレーズを覚えて活用することで、どのような電話にも自信を持ってスムーズに対応できるようになり、あなたの業務を実践的にサポートいたします。
受電・取り次ぎ時の言い回し
電話を受ける際は、まず感謝の気持ちと会社名をはっきりと伝えることが大切です。
たとえば、「お電話ありがとうございます。株式会社〇〇でございます」と明るく名乗ることで、相手は安心して用件を話し始めることができます。
相手が名乗った場合、聞き間違いがないように「恐れ入りますが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」と確認し、その後「〇〇様でいらっしゃいますね」と復唱すると確実です。
そして、取り次ぎが必要な場合は、「かしこまりました。担当の〇〇に代わりますので、少々お待ちください」と伝え、必ず一言添えてから保留にすることが、相手への配慮を示す重要なマナーとなります。
担当者不在時の伝言対応
担当者が不在の場合、まずはその旨を丁寧に伝えることが重要です。
単に「いません」と伝えるのではなく、「申し訳ございません。あいにく〇〇は席を外しております」や、「〇〇は本日、終日外出しております」など、具体的な状況を簡潔に伝えると、相手も理解しやすくなります。
この際、「申し訳ございません」といったクッション言葉を最初に使うことで、相手への配慮が伝わります。
次に、相手の意向を伺い、次のステップをこちらから提案することが大切です。
「よろしければ、戻り次第こちらから折り返しお電話いたしましょうか」と、折り返しの提案をするか、「よろしければ、ご伝言を承りますが、いかがでしょうか」と、伝言を申し出るのが一般的です。
もし折り返しを希望された場合は、「念のため、ご連絡先のお電話番号を頂戴できますでしょうか」と、必ず連絡先を確認し、復唱することで、連絡ミスを防ぎ、確実な対応につながります。
通話終了時の締めくくり表現
通話の締めくくりは、相手への感謝と丁寧な姿勢を示す大切な瞬間です。
一般的な締め方としては、「承知いたしました。失礼いたします」と簡潔に伝えることで、スムーズに終話へと移行できます。
もし相手が時間を割いてくれた場合は、「お忙しいところ、ありがとうございました。失礼いたします」と一言添えることで、より丁寧な印象を与えることができます。
また、担当者への伝言を預かった場合には、「〇〇が戻りましたら、申し伝えます。お電話ありがとうございました」と伝えることで、相手に安心感を与え、感謝の気持ちを示すことができます。
これらのフレーズを状況に応じて使い分けることで、最後の瞬間まで相手に良い印象を与え、円滑なコミュニケーションを築くことができるでしょう。
新人がやりがちな電話取次ぎのNG例と改善ポイント
本セクションでは、新入社員の方が電話取次ぎの際に陥りがちな失敗例、いわゆるNG例と、それらをどのように改善すれば良いのか具体的なポイントをセットでご紹介します。
事前に失敗例とその改善策を知っておくことで、ご自身の電話応対を客観的に見直すことができ、未然にミスを防ぐことにもつながります。
実践的なトラブルシューティングガイドとしてご活用いただき、より質の高い電話応対を目指しましょう。
社名や名前を名乗らずに電話に出る
新入社員の方が電話対応で陥りがちなNG例のひとつとして、電話に出る際に会社名や自分の名前を名乗らず、「はい」や「もしもし」といった言葉だけで応答してしまうケースが挙げられます。
これは一見些細なことに思えるかもしれませんが、ビジネスにおいては相手に大きな不安感を与えてしまう可能性があります。
なぜなら、相手はどこの会社の誰に電話がつながったのかわからず、本当に用件を話して良いのか迷ってしまうからです。
会社名を名乗らない電話応対は、ビジネスマナーを知らないという印象を与え、会社の信頼性にも関わってきます。
お客様からの重要な電話であった場合、最初の対応で会社の顔としての意識が低いと思われてしまうと、その後の取引にも影響を及ぼしかねません。
電話は会社の第一印象を決定づける大切なツールですから、最初の名乗り方ひとつで相手に与える印象は大きく変わることを理解しておく必要があります。
改善策:必ず「○○株式会社の△△です」と名乗ることで信頼感を与える
社名や名前を名乗らずに電話に出てしまうというNG例にたいしては、電話に出る際の最初の挨拶を徹底することで改善できます。
具体的には、「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社の△△でございます」のように、感謝の言葉と会社名、そして自分の氏名をはっきりと、聞き取りやすい声で伝えることを習慣づけましょう。
この一連の挨拶は、電話応対における基本中の基本であり、非常に重要です。
この丁寧な名乗り方は、相手に「どこの会社の誰に電話がつながったのか」を明確に伝え、安心感を与えます。
相手は誰が応対しているのかを認識できるため、安心して用件を話し始めることができるのです。
結果として、最初から信頼関係を築き、スムーズなコミュニケーションへとつながります。
新入社員の方々には、この基本を繰り返し練習し、自然と口から出るようになるまで徹底することをおすすめします。
「もしもし」やカジュアルな言葉遣いを使う
新入社員の方が電話応対でついつい使ってしまいがちなNG例として、「もしもし」という言葉のほかに、「了解です」や「〜っす」といったカジュアルな言葉遣いが挙げられます。
これらの言葉は友人や親しい間柄での会話では問題ありませんが、ビジネスシーンでは不適切とされます。
特に電話応対は会社の代表としてお客様と話す機会であり、このような言葉遣いは、会社の品位を損ないかねません。
会社の代表としてお客様と接する際、電話応対の担当者は「会社の顔」となります。
そのため、ひとつひとつの言葉遣いが、会社の信頼性やプロフェッショナルなイメージに直結します。
カジュアルな言葉遣いは、相手に不快感を与えたり、真剣さに欠ける印象を与えたりする可能性があるため、十分な注意が必要です。
改善策:「お電話ありがとうございます」など、ビジネスに適した言葉を使う
前述のようなNG例を改善するためには、ビジネスシーンにふさわしい言葉遣いを意識的に身につけることが大切です。
「もしもし」の代わりに「お電話ありがとうございます」や「お世話になっております」と第一声を発することで、丁寧な印象を与えることができます。
ほかにも、「了解です」は、尊敬語の「承知いたしました」や「かしこまりました」に言い換えるのが適切です。
これらの言葉遣いは、相手への敬意を示す基本となります。
ビジネスで使える定番フレーズ集などを活用し、日頃から意識的に正しい言葉遣いを練習することが重要です。
最初は慣れないかもしれませんが、繰り返し使うことで自然と身につき、電話応対がスムーズになります。
正しい言葉遣いは、相手に安心感を与え、円滑なコミュニケーションを築くための第一歩となるでしょう。
新入社員の方は、特にこれらのポイントを意識して、日々の業務に取り組んでみてください。
相手の話を聞き流してしまう
電話対応において、相手が話している内容をメモも取らずに聞き流してしまうことは、新人の方が陥りがちなNG行動のひとつです。
これは、相手の会社名や名前、電話番号、伝言内容といった重要な情報を誤って認識したり、最悪の場合忘れてしまったりする原因となります。
その結果、担当者への取り次ぎ時に何度も相手に聞き返してしまったり、誤った相手に電話を取り次いでしまったりといったトラブルを引き起こす可能性があります。
このような対応は、相手に「話を聞いてもらえていない」という不信感を与え、会社の信頼性まで損ねてしまうことにつながりかねません。
改善策:復唱やメモを活用し、正確に情報を受け取る
相手の話を聞き流してしまう状況を改善するためには、必ずメモを取りながら聞く「アクティブリスニング」を実践することが重要です。
電話機のそばには常にメモ帳と筆記具を用意しておき、相手が名乗った会社名や氏名、連絡先、そして用件といった重要な情報を、聞きながらすぐに書き留める習慣をつけましょう。
さらに、書き留めた情報は必ず相手に復唱して確認する癖をつけることで、聞き間違いや伝達ミスを劇的に減らすことができます。
「〇〇株式会社の△△様でいらっしゃいますね」「承知いたしました。〇〇の件でございますね」といったように、確認の言葉を添えることで、相手は「きちんと話を聞いてくれている」と安心感を抱き、より丁寧な印象を与えることにもつながります。
取り次ぎ時に無言で保留にする
電話の取り次ぎをおこなう際、何の断りもなく、いきなり保留ボタンを押してしまうのは避けるべき行動です。
これは新入社員が陥りやすいNG例のひとつです。
突然プツッと音が途切れると、電話の相手は「もしや電話が切れてしまったのではないか」と驚き、不安を感じてしまいます。
相手に不必要な心配をかけるだけでなく、会社全体の印象を悪くしてしまう可能性もあります。
丁寧な対応を心がけていても、このような無言の保留によってそれまでの努力が台無しになってしまうことがあります。
改善策:「少々お待ちください」と一言添えてから保留にする
無言の保留というNG例を改善するためには、必ず保留にする前に一言添えることが重要です。
具体的には、「〇〇に代わりますので、少々お待ちください」といったフレーズを相手に伝えてから、保留ボタンを押すように徹底しましょう。
この一言があるだけで、相手は「今、担当者に取り次いでくれているのだな」「待っていてほしいのだな」と状況を理解し、安心して待つことができます。
この短い一言の有無が、相手に与える印象を大きく左右します。
お客様への配慮を示すことで、スムーズで心温まる電話対応へとつながりますので、ぜひ実践していただきたい改善ポイントです。
担当者が不在でも何も伝えずに電話を終える
新入社員の方が電話対応で陥りやすい失敗のひとつに、担当者が不在であることだけを伝えて、その後の対応を相手任せにしてしまうケースが挙げられます。
たとえば、「申し訳ございません、〇〇は席を外しております」と伝えたきり、電話を切ろうとしてしまったり、沈黙してしまったりすることです。
このように「〇〇は不在です」とだけ伝え、相手への具体的な次の選択肢を提示しないと、電話をかけてきた方はどうすれば良いのかわからず、困惑してしまいます。
結果として、不親切な印象を与えてしまい、会社のイメージダウンにもつながりかねません。
改善策:折り返しの可否や伝言の有無を確認し、丁寧に対応する
担当者が不在だった場合の改善策としては、必ずこちらから次のアクションを提示する「能動的な対応」を心がけることが重要です。
具体的には、「よろしければ、戻り次第こちらから折り返しお電話いたしましょうか」と担当者からの折り返しを提案するか、あるいは「もしよろしければ、ご伝言を承りましょうか」と伝言を預かる意向を伝えます。
相手がどちらかの選択肢を選んだら、その後の対応をスムーズに進めることができます。
たとえば、折り返しを希望された場合は、改めて相手の電話番号や都合の良い時間帯を確認し、復唱します。
伝言を希望された場合は、内容を正確にメモし、復唱して間違いがないか確認します。
このように、不在時でも丁寧かつ具体的な選択肢を提示することで、相手の手間を省き、ホスピタリティの高い対応ができるようになります。
電話をガチャっと切ってしまう
電話対応において、すべてのやり取りが丁寧に進んだとしても、通話の最後に受話器を乱暴に置く「ガチャ切り」は、それまでの努力を台無しにしてしまう非常に残念な行為です。
相手に不快感を与え、自分がぞんざいに扱われたと感じさせてしまうため、会社の印象まで悪くするリスクがあります。
ビジネスにおいて、電話は会社と顧客をつなぐ重要な窓口です。
そのため、通話の最初から最後まで、細部にわたるマナーが求められます。特に、通話終了時の最後の動作は、相手の心に強く残ります。
改善策:相手が切ったのを確認してから、静かに受話器を置く
通話終了時のマナーとして推奨されるのは、相手が電話を切ったことを確認してから、受話器を静かに置くことです。
具体的には、用件が終わり、お礼の言葉を伝えた後、一呼吸置いて相手が電話を切るのを待ちます。
相手が切断したのを確認したら、受話器のフックを指でそっと押すか、受話器をゆっくりと置くように心がけましょう。
この一連の動作は、相手への最後の配慮であり、最後まで丁寧な印象を与えることにつながります。
社内用電話対応マニュアルの作成方法
電話対応は、新入社員だけでなく、全社員が会社の顔として顧客と接する重要な業務です。
しかし、対応方法が属人化しやすく、人によって品質にばらつきが生じてしまうことも少なくありません。
そこで役立つのが、「社内用電話対応マニュアル」の作成です。
このマニュアルは、電話対応の品質を組織全体で標準化し、向上させるための共通のルールブックとなります。
新人研修の教材として活用できるのはもちろんのこと、経験のある社員にとっても、対応に迷った際の指針や振り返りのツールとして機能します。
明確なマニュアルがあることで、社員は自信を持って電話対応に臨めるようになり、結果として顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
よくある質問や対応例を一覧化する
電話対応マニュアルを作成するうえで、まず取り組むべきは「よくある質問(FAQ)」とその回答集を整備することです。
顧客から頻繁に寄せられる質問は多岐にわたりますが、営業時間、会社の所在地、商品やサービスの価格、支払い方法、納期、製品の仕様、あるいはウェブサイトの操作方法など、ある程度のパターンが存在します。
これらの質問に対して、あらかじめ標準化された回答を用意しておくことで、電話を受けた誰もが即座に、かつ正確な情報を提供できるようになります。
これにより、顧客をたらい回しにしたり、担当者に取り次ぐ手間を省いたりすることが可能です。
結果として、一次対応での問題解決率が向上し、顧客の待ち時間短縮にも貢献します。
よくある質問とその回答を一覧化する際は、簡潔でわかりやすい言葉遣いを心がけ、専門用語には簡単な解説を添えるなど、誰が読んでも理解しやすいように工夫することが重要です。
また、定期的に内容を見直し、最新の情報に更新していく運用体制も確立しましょう。
定型フレーズやトーク例を共有する
電話対応の品質を均一化し、社員が自信を持って応対するためには、マニュアルの中核となる「定型フレーズ」や「トークスクリプト」の整備が不可欠です。
これにより、さまざまなシチュエーションに応じた標準的な言い回しを事前に用意でき、社員はどのような状況でも迷うことなく、一貫性のある質の高い対応ができるようになります。
社名や氏名が聞き取れなかった場合の対応
電話中に相手の社名や氏名が聞き取りにくいことは珍しくありません。
しかし、聞き取れないまま対応を進めてしまうと、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
そのような時は、臆することなく丁寧に聞き返すことが重要です。
具体的なフレーズとしては、「恐れ入ります、少々お電話が遠いようですので、もう一度御社名(お名前)をお伺いしてもよろしいでしょうか」や、「誠に申し訳ございません、電波状況が悪いようですので、今一度、ゆっくりとお聞かせいただけますでしょうか」といった表現があります。
聞き返す際は、相手への配慮を示す言葉を添えることで、失礼なく正確な情報を得ることができます。
担当者が不在だった場合の案内方法
電話を取り次ごうとした際、担当者が不在であることは頻繁に起こります。
このような場合、単に「不在です」と伝えるだけでなく、その後の対応まで含めて丁寧にご案内することが重要です。
まずは、「申し訳ございません。あいにく〇〇は、ただいま席を外しております」のように、不在の状況を具体的に伝えます。
会議中であれば「会議中でございます」、外出中であれば「外出しております」など、簡潔に理由を添えると、相手も状況を把握しやすくなります。
そのうえで、相手の意向を確認しながら、次の選択肢をこちらから提案します。
たとえば、「よろしければ、戻り次第、こちらから折り返しお電話いたしましょうか」と、折り返し連絡の提案をします。
もし伝言を希望される場合は、「よろしければ、ご伝言を承りますが、いかがでしょうか」と促し、伝言内容を正確に聞き取ります。
折り返し連絡を希望された場合には、念のため連絡先と、担当者が連絡しても差し支えない時間帯を確認し、「念のため、ご連絡先のお電話番号を頂戴できますでしょうか。また、〇〇が何時頃にご連絡差し上げましょうか」といったように、丁寧に伺いましょう。
このように、相手の状況を考慮し、選択肢を提示することで、不親切な印象を与えることなく、スムーズな対応が可能です。
常に相手の立場に立った案内を心がけましょう。
即答できない場合の対応フロー
電話応対中に、専門的な質問や、自分の知識だけでは即座に回答できない内容を尋ねられることもあります。
このような場合、曖昧な返答をしたり、知ったかぶりをしたりするのは絶対に避けなければなりません。
正直に「確認いたします」と伝え、適切な対応フローを踏むことが、かえって相手に誠実な印象を与えます。
まず、「大変恐れ入りますが、その件につきましては、ただいま確認いたしますので少々お時間をいただけますでしょうか」と伝え、確認に時間を要することを明確に伝えます。
そのうえで、「このままお待ちいただけますでしょうか。または、確認次第、こちらから改めて折り返しご連絡差し上げましょうか」と、相手に選択肢を提示するようにしましょう。
相手に選択肢を与えることで、無駄に待たせることなく、状況に応じた最適な対応を取ることができます。
また、折り返し連絡をする場合は、いつまでに連絡するのか、おおよその目安を伝えることで、相手は安心して待つことができるでしょう。
迅速な確認と、誠実な情報提供を心がけることが大切です。
エスカレーション先と判断基準を明確にする
全ての電話対応を1人で完結できるとは限りません。
特に、クレームが深刻化した場合や、高度な専門知識を要する問い合わせがあった場合には、適切な担当者や上司に引き継ぐ「エスカレーション」が必要になります。
電話対応マニュアルには、このエスカレーションのルールと判断基準を明確に定めておくことが極めて重要です。
具体的には、「どのような状況になったらエスカレーションが必要か(例:顧客が激高している、技術的な質問で回答できない、個人情報に関わる内容など)」という判断基準を詳細に記載します。
そして、「誰に、どのような手段で報告・相談すべきか(例:直属の上司、特定の部署、緊急連絡網)」という連絡先や連絡フローも明記することが求められます。
エスカレーション先と判断基準が明確であれば、担当者は1人で問題を抱え込むことなく、迅速かつ適切に組織全体として対応できる体制が整います。
これにより、問題の拡大を防ぎ、顧客との信頼関係を維持することにもつながります。
まとめ
電話取次ぎは、単なる業務の一部と捉えられがちですが、実際には会社の第一印象を左右し、顧客との信頼関係を築くうえで極めて重要なコミュニケーション活動です。
本記事を参考に日々の業務に取り入れ、さらに電話対応マニュアルをチーム全体で活用することで、会社全体の電話応対品質を高めることができます。
継続的な練習と意識的な改善を重ねることで、誰もが自信を持って対応できるようになり、顧客からの信頼獲得、ひいては会社の成長へとつながるはずです。