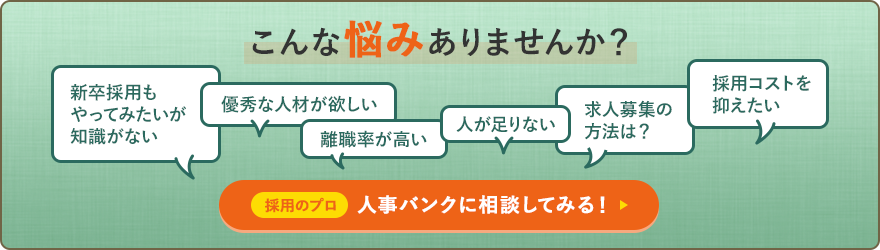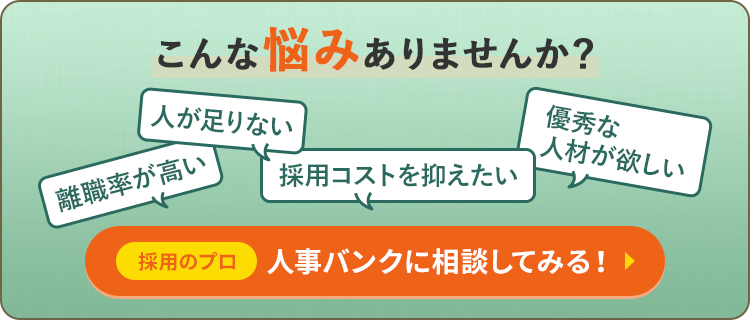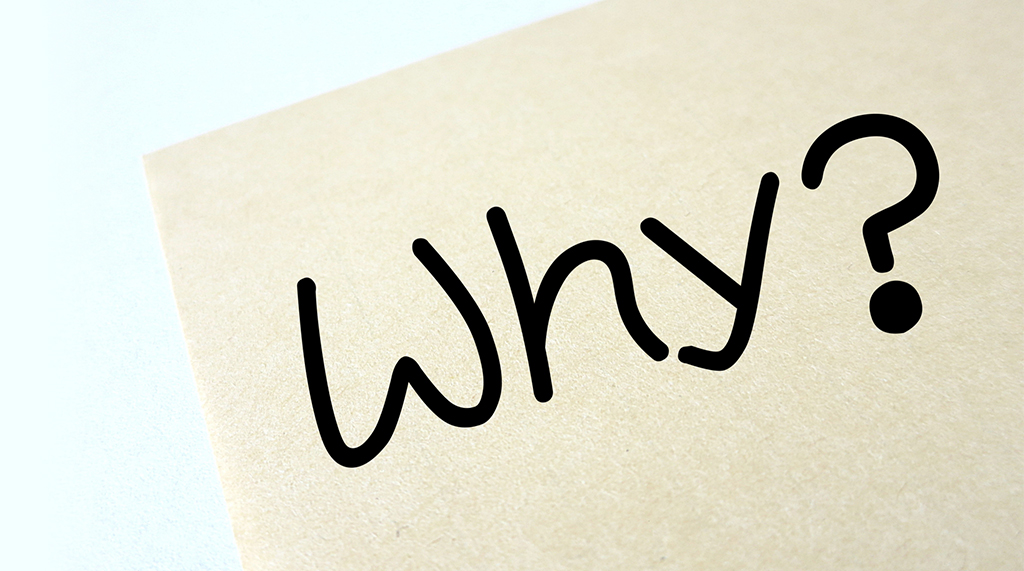1日の大半を過ごす職場では、周囲に「怒り」を感じることもあるでしょう。
怒りは、誰でも持っている感情ですが、コントロールができないと対人関係に大きな問題を起こす可能性があります。
多様な価値観・考えを持つ人たちと一緒に働く機会が増えている近年、アンガーマネジメントの重要性が高まっています。
この記事では、アンガーマネジメントの概要や必要性、実践により得られる効果などについて詳しく解説いたします。
怒りのメカニズムやタイプ、アンガーマネジメントの実践方法についてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
アンガーマネジメントとは
アンガーマネジメントとは、怒りの感情をコントロールする心理トレーニングのことです。
「怒りの感情をコントロールする」と言っても、怒らないようにトレーニングするわけではありません。
例えば、
- 感情に任せて不適切な言動を発してしまう
- 人や物にあたってしまう
- 感情を抑え込んでしまい、相手に伝わらない
など、適切な怒り方が分からず、ストレスやトラブルを抱えることがあります。
アンガーマネジメントは、怒りの感情と向き合って、適切に表現できるようトレーニングを行います。
つまり、「怒るべきときには怒り、必要のないときには怒らないようにする」ことがアンガーマネジメントの目的です。
怒りのコントロールは、仕事のパフォーマンスや生産性に大きな影響を及ぼすことから、アンガーマネジメントの研修が盛んに行われるようになっています。
アンガーマネジメントの必要性
ここでは、アンガーマネジメントの必要性が高まっている理由について解説いたします。
価値観の多様化
少子高齢化などによる労働力不足の影響から、外国人材や育児・介護、障碍などでフルタイム勤務できない人など、多様なバックグラウンドを持つ人たちの雇用が活発化しています。
また、終身雇用や年功序列制度といった日本独自の雇用慣行の終焉により、働き手の価値観も多様化しました。
価値観の多様化により、現在の管理職が新人時代に受けてきた方法での指導が通用しなくなってきています。
従来は、怒りの感情をストレートにぶつけても“指導”で済んでいたでしょうが、現在ではパワハラにつながるため、怒りを適切に表現するスキルが求められるようになったのです。
働き方改革によるハラスメントの防止強化
近年、パワハラやセクハラといった、職場でのハラスメント行為が社会問題となっており、世間からの注目度も高いです。
厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」調査によると、都道府県労働局への職場のいじめ・嫌がらせ相談は増加傾向にあり、2012年度以降の全相談の中でトップになっています。
加えて、いじめ・嫌がらせや暴行を受けたことによる、精神障害の労災認定件数も増加していることが明らかになっています。
こうした事態を受け、2019年5月パワハラ対策を企業に義務づける「改正労働施策総合推進法」が成立しました。
従業員一人ひとりがアンガーマネジメントを身につけることで、ハラスメント防止につながるため、多くの企業から注目を集めているのです。
アンガーマネジメントの効果
では、アンガーマネジメントの実践によって、企業や従業員にどのような効果を与えるのでしょうか。
感情のコントロールができる
アンガーマネジメントを身につけると、自分の感情と向き合った上で「どうするべきか」を考えられるようになるため、相手に対して不用意に怒りをぶつけなくなります。
怒りの感情をコントロールすることができれば、自分の感情に振り回されることもなくなるため、一定のパフォーマンスの発揮や冷静な対応ができるようになるでしょう。
パワハラ防止につながる
部下や後輩社員に対する怒りの感情をストレートに表現してしまうと、パワハラにつながります。
近年は働き手の意識や価値観が多様化しているため、以前は“愛のムチ”で済んでいたことも、大きな問題に発展する可能性があります。
アンガーマネジメントを身につけると、怒りの感情をコントロールできるようになるため、衝動的な言動・行動を抑えた適切なコミュニケーションを行えるようになります。
ストレスを緩和させられる
怒りの感情は、相手だけでなく自分自身にも大きなストレスを与えます。
例えば、カッとなって言葉がきつくなったり、怒鳴ったりしたあとに、「言い過ぎた」と後悔してストレスを感じる人も多いです。
アンガーマネジメントで自分の感情を客観的に把握することができれば、感情任せの言動・行動は避けられます。
感情的な言動・行動が抑えられれば、自ずとストレスは軽減されるでしょう。
コミュニケーションの活性化
人前で叱責する管理職も多いですが、人前での叱責はおすすめしません。
というのも、人前での叱責は怒られている人だけでなく、それを見聞きしている周囲の従業員にまで強いストレスを与えるからです。
こうしたことが日常的に行われている職場では、従業員が委縮してしまい、活発な意見交換が行われにくくなります。
アンガーマネジメントで感情のコントロールができるようになれば、職場の雰囲気も良くなり、コミュニケーションも活発化します。
ダイバーシティの推進に役立つ
怒りは、「こうして欲しい」「こうあるべきだ」という理想に対する、現実とのギャップで生まれやすいです。
近年は、少子高齢化やインターネットの普及、グローバル化などの影響から、様々な価値観やバックグラウンドを持った人たちが働いています。
そのため、自分の価値観に固執していては、職場のメンバーと良好な関係を築くことができませんし、ダイバーシティ推進の足かせにもなるでしょう。
アンガーマネジメントで、多様な考え・価値観があることを理解できれば、大きな怒りを感じることも少なくなります。
「そういう価値観もあるのか」と認められるだけで、冷静なコミュニケーションができるため、ダイバーシティの推進に役立ちます。
人はなぜ怒るのか?怒りの仕組み
そもそも、なぜ人は怒るのでしょうか。
アンガーマネジメントを成功させるためにも、怒りの仕組みについて理解しておきましょう。
怒りの仕組み
人は、日々の生活の中で「不安」「不満」「悲しみ」「くやしさ」「苦痛」といった、マイナスの感情(第一次感情)を心に溜め込む仕組みを持っています。
しかし、蓄積できる容量には限りがあるため、第一感情が許容量を超えてしまうと、「怒り」という第二次感情があふれ出すのです。
また、第一次感情を溜め込む容量の大きさは、人によって違います。
容量が小さくてすぐに溢れてしまう人もいれば、容量が大きくてなかなか溢れない人もいます。
そのため、容量が小さかったり、ネガティブな感情が蓄積されていたりする場合は、些細なことでも怒りやすくなってしまうのです。
怒りの種類とタイプ
怒りには、様々な種類とタイプがあります。
「自分がどういったときに怒りやすいのか」を把握しておけば、コントロールしやすくなります。
怒りの種類
怒りは自然な感情であるため、決して悪いことではありません。
ときには怒ることも必要ですが、怒りの種類によっては注意が必要です。
持続性のある怒り
過去の怒りを忘れられず、何度も思い出してしまう怒りです。
いつまでも過去に苦しめられてしまい、恨みや憎しみにつながることもあります。
強度の高い怒り
感情任せに怒鳴るなど、一度怒ると気が済むまで当たり散らしてしまう怒りです。
強度の高い怒りは、パワハラや人間関係の悪化につながります。
頻度の高い怒り
日常での些細な出来事に対して頻繁に表出する怒りです。
常に不機嫌でイライラしている状態で、周囲から「近寄りがたい人」と思われやすくなります。
攻撃性のある怒り
人や物に当たってしまう怒りです。
「相手をたたく」「物を投げつける」「ドアを叩きつける」といった行為のほか、強い自責の念から自傷行為をしてしまう人もいます。
怒りのタイプ
つづいて、怒りのタイプを見ていきましょう。
公明正大
正義感が強いタイプで、ルールや道徳から外れた人に対して怒りを感じやすい人です。
このタイプは自分の信念を大切にしており、それに反する人を見ると、権利の有無にかかわらず他人をジャッジ・正そうとする傾向にあります。
価値観は人それぞれ異なることを理解し、自分の考えを押しつけないようにすることが重要です。
博学多才
完璧主義な面があり、物事を白黒つけたがるタイプです。
向上心や前向きな気持ちが強い分他人にも厳しく、適当に考えたり、行動したりしようとする人や優柔不断な人に対して怒りを感じやすいです。
意欲的に取り組めるのは素晴らしいですが、全員が同じように取り組めるわけではありません。
白か黒かだけではなく「中間があっても良い」と考えましょう。
威風堂々
自分に自信のあるリーダーの素質を持っているタイプです。
自尊心が高く周囲の目を気にするタイプのため、物事が思い通りに進まないときや、自分を低く評価されたときに怒りを感じやすい傾向にあります。
思うような評価を得られなくても、自分自身を否定されたわけではありません。
物事が思い通りに進まないときは、「最善な判断が採用された」と考えると、ストレスが緩和されます。
天真爛漫
自分の意思や感情を素直に表現できる一方、意思表示がはっきりしない人に対して怒りを感じやすいです。
またこのタイプは、意思の表現や行動を制限されると、ストレスを感じやすくなります。
自分の意見を伝えるだけでなく、他人の意見も聞きましょう。相手に従った方がスムーズに進むこともあります。
外柔内剛
人当たりの良さとは裏腹に、自分の意見・意思を曲げない頑固なタイプです。
一本気な雰囲気があるため、人から頼まれごとをされることも多く、自分の価値観・信条に反する物事や人に出くわすと怒りを感じやすい傾向にあります。
自分の中のルールを緩やかにすると怒りが緩和されます。自分なりのストレス発散法を見つけましょう。
用心堅固
他人に対して警戒心が強く、相談や頼ることが苦手なタイプです。
急激に心理的距離感を縮めようとしてくる人に苦手意識があり、怒りやストレスを感じやすい傾向にあります。
また、自分や他人に対して固定観念を持ちやすいのも特徴です。
「こういうタイプはこうだ」と決めつけて避けていては、人間関係の構築に支障をきたします。
必要なときは周囲に頼りましょう。距離感も縮まって心も楽になります。
アンガーマネジメントの実践方法
感情任せに怒らないようにするにはどうしたら良いのでしょうか。
ここでは、アンガーマネジメントの実践方法についてご紹介いたします。
6秒ルール
怒りのピークは最長で6秒間と言われています。
大きな怒りを感じても、6秒我慢すれば怒りは収まってくるため、叱る前に心の中でゆっくりと6秒数えてから、言葉や行動に移しましょう。
また、怒りの原因を紙に書き出すのもおすすめです。
衝動的な怒りの発散を抑えられるだけでなく、要点が整理されるため、相手が理解しやすくなります。
その場から離れる
強い怒りや攻撃的な怒りを感じたときは、一旦その場から離れましょう。
短い時間でも離席するだけで気分転換になるため、冷静さを取り戻すことができます。
深呼吸を繰り返す
怒りを感じたときは、ゆっくりと深く息を吸って一旦止め、同じだけ時間をかけてゆっくり息を吐き出しましょう。
何度か繰り返すだけで副交感神経が優位になるため、心が落ち着きます。
価値観を広げる
怒りは、期待と現実のギャップによって生じることが多いです。
例えば、「こうして欲しいのにしてくれない」「理解してくれない」など、価値観や考え方の違いによってストレスを感じます。
自分と他人では価値観や考え方が異なることを理解した上で、相手に完璧を求めないようにしましょう。
最初はなかなか上手くいかないでしょうが、意識づけしていけば徐々に受け入れられるようになります。
自分でコントロールできないことは諦める
事故や天候などで交通機関の乱れや混雑が発生すると、イライラすることもあるでしょう。
しかし、これは自分でどうにかできるものではありません。
「自分でコントロールできないものに怒りを感じても、無駄なエネルギーを使うだけ」であることを理解できれば、必要のない場面で怒ることはなくなります。
アンガーマネジメントで適切なコミュニケーションを取ろう
怒りは誰にでもある感情のため、悪いことではありません。
しかし、怒りの感情をそのまま相手にぶつけてしまうと、人間関係の構築に支障をきたすばかりか、パワハラや生産性の低下にもつながります。
近年は、価値観が多様化しているため、自分の価値観に固執していると、自分自身のストレスも高まってしまいます。
アンガーマネジメントでは、「自分の価値観や考えを自分自身や他人に当てはめない」「価値観を広げる」ことが重要です。
最初は難しいと感じるでしょうが、続けていけば自分の感情をコントロールができるようになっているはずです。
グローバル化が進む今後、さらにアンガーマネジメントが重要視されていくと推測されるため、ご紹介した内容を参考に取り組んでみてはいかがでしょうか。