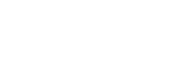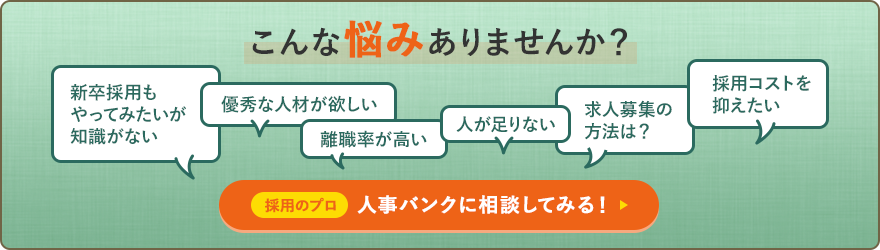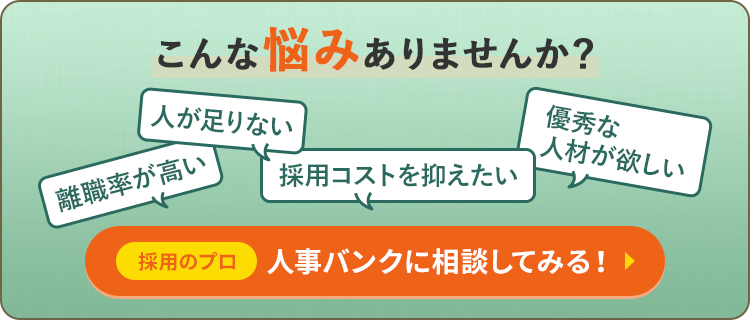即戦力として採用してみたけれど、実際に仕事を任せてみたら思っていたような活躍をしてくれないということはよくあります。
では、「能力不足」などを理由とする解雇は実際に可能なのでしょうか。
ここではその是非を確認し、能力不足の従業員との向き合い方を見ていきましょう。
実際に解雇するのは難しい?
結論から言うと、能力不足を理由とする解雇は困難です。
実際に解雇を巡って行われた裁判で、能力不足のみを理由に解雇を言い渡し、有効とされた判例はほぼないことからも、能力不足を理由とする解雇の難しさを垣間見ることができます。
解雇が認められた数少ない事例も、多くは「再三の注意にもかかわらず改善の兆しが見られない」「協調性に欠ける」「就職時に提示された経歴に虚偽があった」などの二次的、三次的な要因が絡んでいます。
中途採用者の解雇が有効とされた判例として、『フォード自動車事件(東京高裁・昭和59年3月30日判決)』が有名ですが、これは人事本部長という地位特定者を対象としたものです。
その他の判例も、管理職者や翻訳能力を考慮したスペシャリスト採用など、特殊技能や管理能力を伴う即戦力を期待されたものであり、一般的な総合職と照らし合わせて考えるのは難しいでしょう。
また、法的な理由で解雇できない従業員も存在しており、業務上の病気・怪我で出社できない従業員や産休取得中の方がそれに該当します。
休業期間中(産休中)だけでなく、復帰後30日間は解雇することができません。
『退職勧奨』で対応を
解雇が不当とみなされた場合は裁判に発展するケースもあり、双方に時間的・経済的・精神的負担がのしかかってきます。
労力の面から見ても、能力不足を理由に解雇を言い渡すのはリスクが非常に大きいと言えます。
しかしスキルが一定水準に達しておらず、協調性に欠ける従業員を雇用したままでは会社に不利益が生じるのも事実です。
従業員に問題点を改善する意思がないと判断したところですぐ動きましょう。
穏当な手段として挙げられるのが『退職勧奨』です。
文字通り、解雇の理由を具体的に伝え、自主的な退職を勧める方法です。
突然解雇を予告するのではなく、はじめに「解雇理由書」を対象となる従業員に交付し、解雇理由を丁寧に伝えます。
本人の了解を得たら、必ず退職届を提出してもらい、自己都合での退職であることを証拠として残しましょう。
従業員の納得を得られない場合はやむを得ない手段として、会社都合による解雇に踏み切る必要があります。
具体的な方法としては解雇日を記入した「解雇予告通知書」を、少なくとも解雇日の30日前に文書で交付します。
その際、口頭で事情を伝えることも忘れないようにしましょう。
トラブルを起こさないための注意点
解雇が難しい場合は退職推奨をした方がいいと説明しましたが、ただ退職推奨をすればいいというものでもありません。
ここでは、退職推奨をする際に、トラブルとならないための注意点をみていきましょう。
解雇を避けようとした姿勢を示す
従業員の能力に見合った配置転換や充分な教育・指導が行われていたことを立証できれば、裁判で解雇の正当性が認められやすくなります。
そのため、退職勧奨をする前に従業員への勤務態度の改善要求を繰り返し行うようにしましょう。
もちろん、そこで従業員に業務改善の兆しが見えればベストですが、保険として指導・改善命令をメールや文書で行い、裁判で争うことになったときの証拠として残しておくとリスクヘッジに繋がります。
退職勧奨を執拗に行わないようにする
「何回退職勧奨をしたら違法」という具体的な決まりはありませんが、「退職勧奨の回数が執拗過ぎる」として、最高裁で違法とされた判例が存在します。
執拗な誘導は違法とみなされるケースもあることを念頭に置き、従業員が自主退職を断ったら早い段階で解雇を検討し始めましょう。
就業規則に解雇の要件を明記する
解雇の要件を文書の形で労働契約時に示しておけば、解雇を通知する際に正当性が生じます。
従業員の少ない企業では就業規則そのものがないこともありますが、トラブル回避のために就業規則を文書としてまとめておくといいでしょう。
解雇が難しい場合は退職推奨を
ここでは「会社都合による解雇」もひとつの手段としてお伝えしましたが、解雇は「労働者の意思に反して、労働契約を一方的に解除するもの」であり、企業が従業員に対してとる最終手段です。
従業員から解雇が不当であると主張され、裁判で争うような事態を避けるためにも、まずは従業員への指導・業務改善命令を徹底してください。
それでも改善しない場合は、退職勧奨という形で自主的な退職を勧めるというステップを踏みましょう。
「今すぐにでも解雇したい」という不満や怒りはトラブルの元です。
経営者や人事担当者の方々は常に冷静な判断を心がけ、従業員と良好な関係づくりに努めていきましょう。