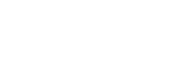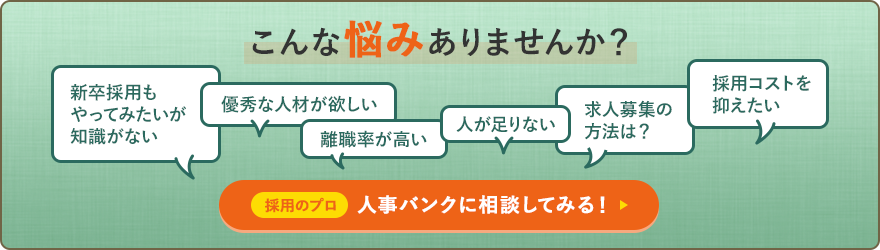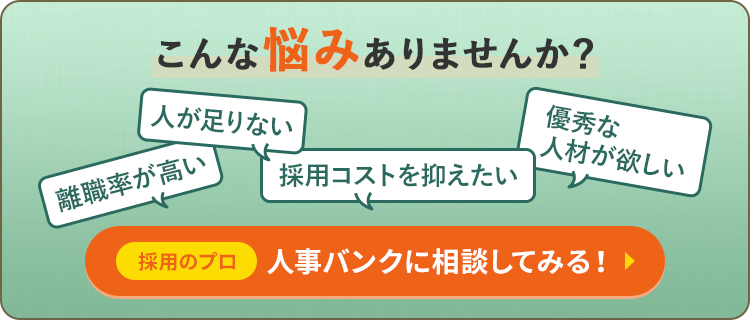ここ数年で「ベースアップ」や「ベア」というワードを耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。
バブル経済崩壊後から「ベースアップ」という言葉を聞かなくなりましたが、2014年のアベノミクスの影響により再度復活しました。
そこで今回は、「ベースアップ」と「定期昇給」とは何が違うのかを紹介していきます。
ベースアップとは
「ベースアップ」とは、略して「ベア」とも呼ばれ、基本給の水準が一律で上がることを指します。
企業と労働組合が交渉し決められることが多く、個人の業績や活躍は関係ありません。
ちなみに、企業と労働組合が賃上げに関して交渉する場を「春闘(春季闘争)」と言います。
例えば、企業で「ベースアップ3%」が決まった場合、全員の基本給が3%アップ。
「基本給30万円」だった場合は9000円アップし、「基本給30万9000円」となります。
気を付けなければならないポイントは、交渉時に企業の業績が良かったとしても、いつか悪化するかもしれないということです。
コストの圧迫になってしまう可能性もあるので、従業員への還元と今後の展開をしっかり考慮して決めていく必要があります。
ベースアップと定期昇給の違い
「定期昇給」は勤続年数や業績、年齢など何らかの機会によって基本給が上昇するので、個人の昇給に差が出ます。
「ベースアップ」は基本給そのものが一律で上昇するので、全員の給与が平等に上がります。
基本給の一律アップという点で働く側に喜ばれますが、企業にとっては人件費が増えるため負担が多くなるという面もあります。
「定期昇給」の場合は、従業員数や勤続年数から、ある程度負担が予測できますが、「ベースアップ」は交渉次第で変わるので、負担の予測ができません。
「定期昇給」と「ベースアップ」は混同されがちですが、全く違うので、正しく理解するように心がけましょう。
企業にとっての影響は?
企業にとっては人件費が増え、将来に向けてのリスクを背負うという面もあるので、春闘では活発な議論が展開されます。
「ベースアップ」は企業にとってどんな機能を担っているのでしょうか。
評価指標としての機能
労働生産性が向上し、企業収益が増加したことに対する従業員の評価として機能します。
企業の利益が増加し、賃金が手厚くなることで従業員のモチベーションアップへと繋がり、逆に労働生産性や利益が変わらない場合は、ベースアップを0にすることに正当性が認められます。
名目賃金の調整としての機能
インフレ時の物価上昇に伴う名目賃金の調整として、「ベースアップ」は役割を果たすことができます。
実質賃金の低下を防ぐ役割がありますが、21世紀に入ってからデフレの傾向が続いていたので、多くの企業でベースアップが見送られていました。
業績悪化時でも一度上げた賃金は下げることが難しいので、ベースアップは慎重に行っていきましょう。
2018年のベースアップの状況
では、現在どの程度の企業がベースアップの実施を検討しているのでしょうか。
労務行政研究所が東証上場企業を対象に実施した「賃上げ等に関するアンケート調査」によると、上場企業の33.6%がベースアップを予定しているという結果が出ました。
2010年以降はベースアップ実施に消極的な傾向が続きましたが、14年16.1%、15年35.7%と「実施する予定」が増加。
16年30.1%、17年23.7%と近年は減少をしましたが、18年は33.6%と高い割合を記録しています。
ちなみに、17年に実際にベースアップが実施された企業の割合は予定より倍近くの46.9%。
2018年も多くの企業がベースアップを実施するのではないかと考えられます。
まとめ
21世紀に入りデフレ傾向が続いたため、ベースアップという単語はしばらく目にする機会がありませんでしたが、2020年の東京オリンピック開催による景気の上向きから再度注目されました。
ただ、業績が上向きの時は良いですが、悪化するとコストを圧迫するため、リスクが高くベースアップに消極的な企業が多いのも事実です。
「ベースアップ」と「定期昇給」を正しく理解し、現状と今後の展開をしっかり見据えて、慎重に賃上げを行っていきましょう。